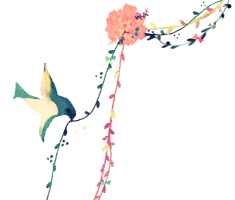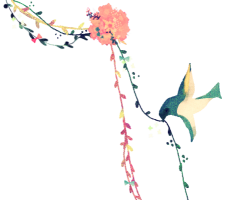彼に知っているかどうかを問うてみれば、いや知らへんけどと彼は首を横に振った。そうか、知らないかとしょんぼりと私が項垂れると名も知らぬ彼は私の頭をぽんぽんと軽く叩いて、慰めの言葉を何かかけたらしい。「ほれ、元気だし。お嬢ちゃん」
「馴れ馴れしい、近寄らないで」私は彼の手を振り解くと彼はショックを受けたようにその場に固まって動かなくなる。
「何でそんな事言うんや」
「だって、」私は彼に視線を合わせることをためらいながら、言葉を続けた。「アナタ苦手だもの」
彼は能力者だった。そしてそれ故に私も能力者であることを悟られてはならなかった。戦う事は傷つけ傷つけあう以外に意味は無いと考えている。戦う事で憎しみや悲しみしか生まれないことは知っている。
「人にモノを聞いてその態度はあかんで」
「ごめんなさい…」私は彼に気圧されて、思わず頭を下げる。と彼はぽりぽりと頭を掻いた。
「全く…正直すぎるお嬢ちゃんやな」
「…そうかもしれない」それは嘘をばれないようにするための嘘だから私は嘘つきなのよと言いたかったけれど私はその言葉を飲み込んで次の言葉を続けた。「だから今すぐにどこかへいってください」
「せっかく会うたんやから、茶でもおごるわ」
にこやかに微笑みかけてくる彼に、私は少し絶句する。何のつもりだろうか、ただの好意ならばともかくとして敵意があるならば注意が必要だった。しかし今までの流れからしてこの人物に敵意があるとも感じられない。しかし今まで私に擦り寄って来た男たちはみんなみんな能力で私を倒そうとしたから。だから、私は彼らから戦う事ができずに逃げて逃げて逃げて逃げて逃げ延びていたのに、皆一様に血相を変えて私を追ってくるから私は仕方なくその人たちをみんな倒すしかなかった。
「初対面ですから」
「遠慮なんていらへんて」
彼は私に対してやけに友好的に話しかけてくるが、こういう奴に限って悪い奴ばかりだということは今までの経験上分かりきっていた事だ。私は遠慮じゃないと態度で分かるように首を振ったが、彼は私の頭をぽんぽんと軽く叩く。心配せんでええって、とってくったりはせえへんよ。私がもう一度首を振ったところで、「ちゃん見―つけた!」と耳障りな声が聞こえる。こんな時に面倒な奴に追いつかれてしまった。こうなったら仕方ない。
「佐野清一郎くん、じゃないか。初めまして」面倒なアイツは、にこやかに作り笑いを浮かべている。
「誰やお前、……能力者か」
佐野清一郎と呼ばれた彼は、私と話していた時とは別人のようにして相手を威嚇している。だけど、そんなにぐだぐだ話している暇なんてないから、あいつはとんでもなく強いから。だから。「逃げよう、早く」
「なんやて」
逃げよう、って言ってるの。と言えば彼は何で敵に背中みせなあかんのや、と臨戦態勢に入っている。危ないからやめて、と首を横に振ればお嬢ちゃんを守るのが使命やなんて言いはじめる。「やめてってば」
私の言葉も意向も無視されてしまい、気がつけば私は佐野清一郎に庇われるようにして立っていた。
「なんで、」私が言葉にならない声をあげる。「どうして助けてくれるの」
「目の前で困っとる奴放っておくほど非道やあらへんからな」
「そんな」
「安心せぇ、俺が助けたる!」
「でも、私、初対面なのに…!」
「アホ! 初対面だろうが何だろうが目の前で困っとる奴放っておけん性分なんや」佐野清一郎は痺れを切らしたように、続ける。「つべこべ言う暇があったら巻き込まれんようにさっさと遠くに離れとき」
「嫌よ、守られてばかりなんて私」私が彼に異論を唱えようとしたところで、その言葉は最後まで届く事は無く彼に一蹴されてしまった。
「一般人は黙っとき!」
私も負けじと言い返す。
「能力者だから言ってるの!」
「なんやて」そんなやり取りを楽しそうに傍観する“アイツ”。彼はにこにこと作り笑いを浮かべながら私たちの様子を観察していた。
「だから、お願い」一緒に逃げて。その言葉は彼に受け入れられる事は無く。
「だったら尚更、戦わなあかんやろ」彼は勇敢にもアイツへと牙を剥いた。「アイツに勝ったら、一緒にお茶にでも行こうや」
不覚にも、そう言い放った彼の横顔にときめいてしまったのは言うまでもないだろう。私は気がつけば、彼の言葉に頷いていた。
(20090919:モカ色の午前)
「ねえ、佐野」
「なんや」
私は佐野に対して意味も無く問いかける。先生は、クラス委員を務めている私に彼を見張っているようにと伝言を告げて、急用があると言いながら職員室へと戻っていってしまったので教室には私と居残り組の佐野しかいない。赤く染まった夕焼けが目に染みる。
それにしても授業後に残って補習とは、彼はなんとも間の抜けたことをしたものだと私は内心苦笑した。だって佐野は本当は頭がいいのに何でそんな阿呆な間違いなんて犯すのかしら、なんてそんな事を聞いたところで彼は決まって私のため、なんて答えるのだろうけど。いや、誰が聞いたところで、それは君のためやなんて答えるのだろうけど。(彼はこういうところでキザなんだ。)まあそれを彼が自覚しているのかしていないのか分からないが。自覚していたら相当な女たらしになるのだろう。自覚していなくても女たらしであることに変わりはない。そのほうが余計にタチが悪いかもしれない。それでも彼が進めている課題は、若干の間違いを残して解き進められていた。私は親切心から、間違っていることを彼に伝える。
「これ間違ってる」私は、彼の間違った答えの書いてある解答欄を指さした。
「なんやて、どこが間違っとるっちゅうんや」
「ほらこれ」むすう、とした佐野の手元に寸分狂ったような中臣鎌足の文字。そこは中大兄皇子だと訂正してやる。
「覚えてへんわ、こんなもん」幼稚園児がふてくされたようにふいとそっぽを向く佐野。「なんではこんな無駄なもん覚えとるんや」
「だって、面白いじゃない」私は彼の様子がおもしろいのでくすくすと笑いながら答える。「歴史の人物って、結構奥が深いでしょ?」すると、ははあん、と何かひらめいたとでも言うように、佐野は確信を持ってニヤリと笑いながら私を見た。
「、お前歴女やろ」
「そうよ、石田光成は最高にカッコいいの」私はあっけらかんと答える。いかにも残念そうな表情になって、ため息をつきながら頭を掻く佐野。
「ったく、もう少しマシな返答返せるやろ!」
「関西人のようなセンスは生憎持ち合わせてないわ」
「もうちょっと可愛い答え方できひんのかい、は」
「だって、『え、なんでわかっちゃったのぉー』なんて私が言ったら気持ち悪いもの」
「言ったら気持ち悪いもなにも、今言うとるやないか!」
「あ、ごめん」私は気持ち悪かったよね、なんてくすくす笑う。
「別にかまへんけどな」
彼はそこで、会話をしながらも動き続けていた手を休めて私の髪の毛をわしゃわしゃとしたので、私の髪型はもさもさになってしまった。何するのと、むっとした表情をすれば佐野の顔がしてやったりというようにニヤリとほくそえんでいる事が確認できて少し悔しい気持ちになる。「してやられた気分ね」
「ええんとちゃうん?」
「よくないってば、今は私のが偉いんだから」
「なんやねんそれ」ハハハと佐野は笑う。「訳わかれへんわ」
「わかるって、女心だもの」
「余計にわかれへんわ」
「アナタには一生かかっても解けない問題でしょうね」
「馬鹿にしとるんかい!」
私は佐野の冗談交じりの突っ込みにくすくす笑いながら「そうよ」と一言嘯く。それを聞いて黙っている佐野ではなく、もはやすでに問題を進める手は突っ込みに回っており、解答欄の上を動いてはいなかった。全く仕方の無いクラスメイトだと思いながら「だって進んでないもの」と問題集を指差す。佐野は「鬼教官の素質でもあるんちゃうか」と嫌味をまくし立てた後に、まあ全部解き終わったら褒美の一つでも貰わんと割に合わんわとか何とか呟いていたがその声は聞き取るにはあまりにも小さすぎる独り言だったので私の耳には届かなかった。
「覚悟しとき、」
「はいはい、あと十ページ出来たら先生が赤い合格印押してくれるから」
私は彼を一通り馬鹿にすると、彼の観察を続けることにした。
(20090918:ルージュのスタンプ)
「なぁ、」
「なあに」
私は会話に若干のデジャヴを感じながらぼんやりと部屋の窓から月を眺めていた。今日は何十年に一度の皆既月食が日本で起きるとか何とかいう話で世間は持ちきりだったからだ。私はぼんやりとまだ関取のようにどしんと構えている満月を憎らしげに睨んだ。まだ、あと月食まで一時間弱はある。私は小学生の時に習った日食と月食の童話を思い出していた。私はベランダのほうに出ようかどうか迷ってやめた。出るには、まだ早い。
「あとどれくらいで欠け始めるんや、月」
「一時間ぐらい」
私のソファベッドに我が物顔で腰掛けながら佐野がテレビを見ている。私はその隣に少し間隔をあけて他人行儀に座る。丁度テレビでは特別特番の生中継を行っている最中だった。月が欠けるくらいで、異常気象のようにニュースで騒ぎ立てられるなんて、全く平和ボケした世の中である。そのほかにも報道しなくてはならない事実なんていっぱいあるはずなのに。世の中で一番狡賢いのは政治家とマスコミかもしれない。
ふと私は、一つの記憶を思い出す。
「そういえば、小学生の時日食と月食がどうして起こるようになったかっていう童話習ったよね」
「なんやそれ、そんなもん習っとったんか」
その口ぶりからして、どうやら佐野はその話を覚えていない様子だった。まあ仕方の無い事なのかもしれないけれど、記憶から消えてしまう事ほど悲しい事は無い。私もいつか彼の記憶から消えてしまうのだろうかとか、月食で月が夜に溶けてしまうように私も世間の雑踏に溶けて存在が無くなってしまうのだろうかとか、考えたらキリが無いくらいに孤独感と不安感が襲ってくる。
「ええ」私は彼の言葉に適当な相槌を打ちながら「佐野は習ってないんだ」とぼんやりと話した。
「忘れとるだけなのかもしれへんな」
「そう、か」浮かんでくる寂しさと不安を悟られないように私は微笑む。彼は私の頭をくしゃくしゃと撫でて「無理するんやないで」と言った。私は何の事かしらと、とぼける。
(20090919:月の溶けきった夜に)
そうね馬鹿みたいね、と呟いた私に佐野は、ほんまにそうやなと呟いた。
「、お前自分の立場とか色々と分かってそんな事言っとるんか」
「そうよ」
「生粋の阿呆や、何とかならへんのか」
「前言撤回すれば何とかなるかしら」
「阿保、そんな事したって何も変われへんやろ」
「でしょ、だから何もする必要性を感じない」
「せやからって」佐野は一拍言葉に詰まる。「何かすれば状況が変わるかもしれん。は何かしようとか思わへんのか」
「あなたのそういう希望的観測ができるところ、好きよ」
「今はそんな話してる場合やないって事わかるやろ」
「分かってて言っているの、空気を読んだ上で更にその空気を壊した。空気は読めているの。だからこそ、私は何もしないわ」私は続ける。「だってそうでしょう、私一人が動いたところで世界が変わるわけでもない。更に言ってしまえば私一人が死んだところで世界が変わるわけでもない。ただの中学生風情がこんな戯言を呟いたところで世間の目は冷たいのよ。私がどうこうと弁論したところで、誰も耳を傾けようとはしないわ。ただ雑踏に紛れて消えていくだけに過ぎない、だったら何もしなくても一緒じゃない。寧ろ無駄な労力を使わなくて済む分、労力分の苦労をしなくても済むから何もしないほうが私の負担としては軽いわ」
「無責任やないか」
彼は私の戯言を一言で切り捨てた。「お前の一言で誰かの心が動くかもしれん、お前が死んだら誰かの世界が変わってしまうんは確かや。人が死んで悲しまん奴なんておれへんやろ。やからこそ、世間が見てくれるかもしれへん。最初から決め付けて何もせえへんより、最初からダメモトで突っ込んでいった方が落ち込まへんやろが。必死になれば誰か一人でも心は動かせるんや。何もせえへんかったら、誰も見てくれへんのは当たり前やで。労力を惜しむくらいなら、お前は生粋の根性なしなだけや」
「そうかもしれない、でも私は諦めが悪いの」
「せや、それでこそや」
その調子でガンガン突っ走ってけ、と彼は言う。私はその様子にくすくすと苦笑すると、そろそろ一時間がたつころねと彼に告げた。ほんまか、なんて彼がソファを立ち上がり、パタパタと床を鳴らしながら窓を開けてベランダへと出ていく。私も彼の後を追えば、窓の隙間から三日月へと変貌を遂げている満月の姿が見えた。
「絶景やな」
「欠けていく月が見れるなんて情緒深い」
「いつか温泉につかりながら見たいわぁ」
「お一人でどうぞ」
私が彼を突き放すように言えば、彼は冷たい反応やなぁと苦笑した。
(20090919:クロワッサンの月)
「せやから、一緒に行こう言うとるやないか」
何で一緒に行ってくれへんのや、と佐野は懇願しているがその頼みというのもはいそうですかと簡単に二つ返事できるものではなかった。
「だって、嫌よ」と私。「なんでや」と佐野。
「嫌なものは嫌よ」
「せやから」
「嫌と言っているでしょう嫌だと言ったらてこでも動かないつもりでいるので宜しくお願いしますそれではさようならオルヴォワール」私はそのままその場を立ち去ろうと試みるが佐野に右手首を掴まれてしまい逃げようにも逃げられない状況へと陥ってしまった。なんということだろう。私は佐野へと向き直る。「私は家に帰る予定があるから、離して」
「嫌や」
駄々っ子のようにだらだらと私の手首を掴んだまま、ぶんぶんと首を横に振る佐野。諦めが悪いと言う点では私とクラスで一・二を争うのではないかと言われるほどに彼は自分がこれと決めたことに対しては諦めが悪かった。それを承知の上で私は断り続けている。私も諦めが悪い人間の一人だからだ。
「一緒に行くだけやろ」
「それが嫌なの」
彼は一向に諦める様子を見せない。最近は会うたびに「なぁ、。学校帰りに行かへんか」なんて誘ってくる始末だ。どこへというのはもう察しが付いているかもしれないが、温泉のことである。彼がとんでもなく温泉が好きの温泉フリークだと言う事は一部にしか知られていない事実ではあるし、彼が実は普段着として浴衣か着流しかそれに近いものを着用していると言う事実はもっと一部にしか知られてはいないだろうが、その事実を踏まえたところで仮にも男女の仲である。
「一緒に入るわけやあれへんで」私は少し言葉に詰まる。
「嫌だと言っているでしょう」てっきりそうだと思っていたからだ。まさかとは思っていたが、とりあえず安堵してしまう自分がいて、何を考えているのかとその安堵した気持ちを頭から追い出す。
「な? 頼むわ」
「何で私なのよ」
「誰からも断られてしまうんや」
それはまあそうだろうと頷けるところが同情に値する。当たり前だ、いきなり温泉やら銭湯やらに誘って行きたいなんて言う希少な中学生は佐野以外に見た事がない。温泉に行かないかと誘ってくる人も佐野以外に見た事がない。結論からして言えば、おいそれとついていくのはご近所づきあいを大事にしているお年寄りとかお風呂が壊れているご家庭の皆さんとかどうしても家のお風呂が使えなくなっている皆さんとかその辺りだろう。
「それは…」私が言葉に詰まっていると、頼む、とひたすらに懇願してくる佐野が視界に映る。
「な?」うぐ、と回答に詰まる私にトドメの一言。「もうしかおらへんねん」
「まあ、また今度」渋々と搾り出した回答は視線を泳がせながら出来るだけ佐野と目を合わせないように。罪悪感を軽減しながら心の中で謝りながら。……ごめん、佐野!
「ほんまか!」
私の曖昧な返事に、ぱあっと目を輝かせながらぶんぶんと掴んでいた腕を上下に振る佐野。ああうん、と適当な返事を返せば「また今度な!」なんて嵐のように走り去っていく。一体なんだったんだろうなんて、私はぼんやりと彼の後姿を視線で追いながら「まあいいか」と呟いて帰路に戻る。今度っていつや、と佐野が気づいて纏わり付いてくるのは近日中だろうなと考えると気が重くなった。
(20090919:正真正銘、四六時中)