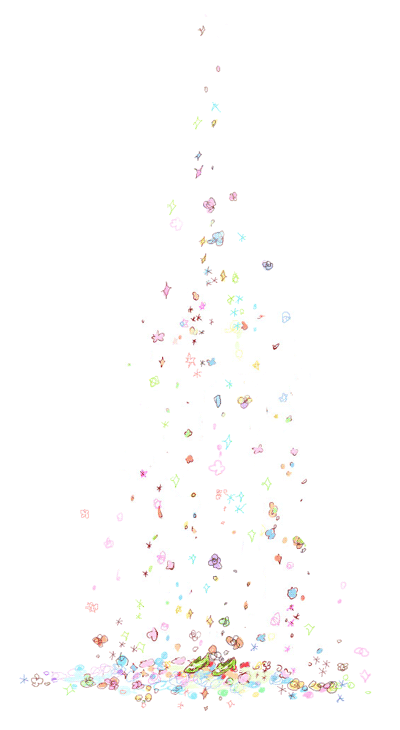01/文次郎
01/文次郎
どうしてだろうか、いつの間にか好きだと思ってしまっていた。君の側にいたいと、思うようになってしまった。
「
、ちょっと頼まれてくれ」「なんだ、潮江か」別にいいが、何の用だ? と私が彼に問いかけると、彼は会計書類を私の前にドンと置いた。現段階で私たちがいる此処は図書室である。私は普段図書委員でもないが、休み時間中と授業後は静かに出来る場所を求めて図書室に来るのが日課だ。なので大抵自室に居ない時は図書室に居る確率が高い。だからと言ってどういうわけでもないのだが。「取り敢えず頼む」彼は珍しく頭を下げてきた。まったく、人が断れない性質だということを知っているとすれば彼も人が悪い。……忍だから仕方ないのかもしれないが、それにしても此処まで必死に頼まれては断ることも出来まい。「そこまでして頼まれたら仕方ないな」私は溜息をつきながら彼の要望に答えることにした。そう答えた私の声を聞くや否や、彼はありがとうと照れくさそうに言って図書室から去っていった。跡に残されたのは、私と数冊積み上げられている会計書類。「まあこの字からして見直すのも大変だろうけどな」再び溜息をつく。全く彼も後輩に対する愛情表現が下手糞なものだとつくづく思う。鬼の会計委員長などと恐れられているくせに実態はこれだ。後輩に恥をかかせまいと多少私に点検作業を押し付けてくる。なんて健気なんだろう。健気、か。――自分で考えてから、私は何を思っているのだろうと苦笑した。しかし、そんな彼を見ていると彼も飽きないものだと関心の意すら覚える。保健委員なんぞ、まあやれ不幸だそれ不幸だと言われ続けているので、色々と周りが気を使ってくれる場合が多い。会計委員は比較的しっかりしている連中とか責任感とかある程度備わった奴が揃っているので周りは彼らを放ったらかす。実際に業務時間――仕事ではないのでこの場合は活動時間になるのだろうか――が非常に多いのは、会計委員であることを殆どの人は知らない。そして、その中でもギンギンに忍者している潮江がその中でも抜きん出て走り回っているのを大抵の人は知らない。だからそういう事が言えるのではないのだろうかと、私は思うのである。まあ別にそう言ったところで彼の立場が変わるわけではないのだが。「ああ、計算違いか」パラパラとめくっていた手を止めて、懐から墨を取り出して修正する。全く、可愛らしい間違いで微笑ましい。字の汚い奴にとって似た数字は案外盲点になる。私も一年の頃は字が下手糞だったと思い返した。大体、書道の授業自体が嫌いだった私は、通っていた書道教室にろくすっぽ顔を出さなかった。そのツケが、この学校に来て回ってきたわけなのだが。――ああ辛気臭いことを考えてしまった首を振ってその考えを取り払う。最後の帳簿の見直しを終えた所で、私は彼が大抵居座っている場所へと足を運んだ。いつの間にか夕暮れが近付いている。「潮江―」「おお、終わったか」また随分と早かったな、と彼は私の差し出した会計書類を隈の目立つ笑顔で受け取った。一段とその隈が濃い所を見るに、どうやら相当疲れているようだ。「今回はあまり目立った間違いが無かったからな」随分と成長したじゃないかお前の可愛い後輩は、と私が冷やかす。「そうだろう、優秀に決まっているじゃないか。なんてったって俺の後輩だからな」と、彼は威張って胸を張った。「全く、その言葉を後輩にそっくりそのまま聞かせてやりたいものだ」先輩がこんなことを言っているとなれば多少ながら厳しすぎだという噂も緩和されるだろうに。――子煩悩ならず、後輩煩悩というか何と言うか。それがまあ、コイツのいい所なのだがなと思いながらもそこまで言ってしまえるような勇気が無くて言えない私に内心苦笑した。まったく人の事言えたもんじゃないだろう私は、彼のほうが言葉にして言えるだけ私よりも上のレベルなのだろう。そう思うと少し悔しい気がする。――ような気がした。変な所で負けず嫌いな自分だと自嘲する。「なっ! 冗談でも、そんな事いうんじゃねえぞ!」彼はちょっとムキになって言い返してきた。「ははは! 私は冗談でなどは言わない事をお前は分かっている筈だろう?」私はそれを軽く受け流す。「本気でも言うな!」「わかったよ、内密にしておく」私は一通り笑った後、彼の頭を小突いた。潮江は少しムッとした表情になり、机の前に座る。彼の机の前には膨大な会計資料があった。また今日も徹夜なのだろうな。と私は思う。「少し手伝おうか」「いい、俺がやる」「じゃあ此処に居てやる」「分かった」私は彼の隣に腰を下ろす。横から見た彼の帳簿には、綺麗な字がつらつらと並んでいた。先程私が見ていた私と同類の書道嫌いの会計委員(だと私は思う)のものとは大きく違っているのが目に見えて分かる。まるで天と地ほどの差があるのではないかと思うほどだったが、そんな野暮ったいことは邪魔になりそうなので口にしない。真剣な時の彼の横顔は、いつものギンギンと叫んでいるような彼とは違って多少かっこよく見えた。まあ、深夜に訪れる何ともいえない高揚感が私の脳を錯覚させているだけなのかもしれないのだが。やはりちょっと、うん、まあ、そうともいえる。暫く彼の姿を見ていたのだが、時間が遅くなるにつれてだんだんと眠気が襲ってきた。うつらうつらとしていた意識が、瞼の重圧に耐え切れず私は気付けば夢の世界へと旅立っていた。そして私の意識は途絶える。
見れば隣ですうすうと気持ちの良さそうな寝息が立っていた。
はどうやら寝てしまったようだ。無理もない、もう丑三つ、いや二つ時ぐらいだろう。明日は授業が無いからいいものの女のこいつに無理はさせられない。それにしても、と考える。なぜ
は此処に居るといったのか。何をするわけでもなく、それでいて話しかけるわけでもなく。「全く、分からん奴だな」しかし、まあこのちょっとした有名人である
を独占してしまっているという事実は嬉しくないといったら嘘になる。しかも、寝顔まで見れるというサービス付だ。普通の忍たまだったらきっと理性なんてものは一分たりとも持たないだろうというのは言葉のあやというやつだとしても。――無防備に寝やがって畜生。こっちの気も少しくらい考えろよ。自分にそういう勇気がないことは重々承知なつもりだ。そしてまあそういうような気を起こさないことを知って安心してコイツはぐっすりと寝ているんだろう。その点から見ると俺は信頼されているのだろうかとか少し期待してしまう。まあきっとこんなことは寝ている
を間近で見た奴の誰もが思うことなのだろうが俺は少しでも特別なのだろうかと思うたびに内心喜んでいる自分に気付く彼女の表情で一喜一憂している自分に気付く、全く振り回されっぱなしで全く忍者らしくない寧ろこんなことでは忍者として失格だ。しかし、まあ今だけは彼女の寝顔に免じてそんなコトは忘れ去ってしまおうと思った。せめてこの瞬間だけ。せめてこの時間だけは彼女の隣で過ごす事が出来るから。会計書類を見ていたら、彼女の寝顔が予想以上に気になってしまっていつの間にか会計書類をなおざりに彼女の寝顔の方に魅入っている自分に気付いて自嘲した。
(
▲)(20080508)
 02/6い
02/6い
とてもじゃないが敵いそうに無い とてもじゃないが叶いそうに無い とてもじゃないが適いそうに無い
度重なる不幸の連続。それに耐えながら学園内を駆けずりまわり任務をこなす。保健委員になったものは必ずと言っていいほど不幸な運命に見舞われることになる、というような風潮が学園内にはある。それは一見すると信頼性の無い情報に聞こえるのだが、あながち間違いではないというのが悲しくも事実であり現実だ。現に保健委員を六年間やっている善法寺伊作を含め、その他前年度の保健委員長達がそれを物語っている。もちろん忍たま達に限らず、くのいち達にもその不名誉な伝統は残念なことに受け継がれているらしい。此処に居るのは善法寺よろしく六年間何らかの理由で保健委員をやり続けているくのいち教室の少女。
その名も、――である。彼女の功績はまさに優秀。定期考査から実技まで何かとよく出来る天才体質である。彼女は何をやらせてもずば抜けて出来るのだが、何処か行動がぬけていたり何かと不運な目にあったりして成績は上の中。本来ならば学年トップの座も狙えないことも無い筈なのだが、どこかで何かが足りないのだ。簡単に一言で言ってしまえば根本的に行動パターンがドジで天然なのである。人にもよるのだが、そこが可愛らしいと豪語するものもいるので好みは人それぞれということなのだろう。性格の方はというと、行動面とは正反対で真面目で几帳面。色恋沙汰に関する情報は皆無という今時珍しいお堅い女の子である。「善法寺! ちょと頼まれてくれないか」彼女がこういう知らせをもってくるのは、たいてい面倒なことが多い。任務とか、授業の一環であるとか、急患とか、便所紙が無いから補充に行ってくれとか、その他もろもろである。「なんだい、?」
「こんなことを頼むのは気が引けるが、」伊作が振り返るとは、保健室に入ってくるなり土下座をしていた。「女装してくれないか」「え?」脳内で、漢字への変換が行われる。――ジョソウ、助走、除草、女装。いやいや、やはり此処は草を抜く方のではないし、の様子を見るに走る訳でもないらしい。やはり、ここは『女の格好をする』意味の『女装』であるのだろうか。「もう一度言うぞ、――『女装』してくれ」は土下座して頭を下げる。「『ジョソウ』ってあの女の人の格好をする『女装』?」最もな質問を投げかけると、「それ以外に何がある」と返された。「誰かを女装させて一人でも連れて行かないと、私は不合格だ」「えええええ!」女装の方はともかくとして、6年のこの時期になって課題で不合格は辛いだろう。しかしよりによって、一番厄介な仕事を持ってきたものだなと内心苦笑する。「でもさ、。私よりも、い組の立花仙蔵とかの方が女装上手いんじゃない?」実習なら、彼を使った方がいいと思うんだけど。と伊作は的確にアドバイスしたつもりだったが彼女は立ち上がって伊作の胸倉を掴み、それを一蹴する。
「馬鹿! い組の立花なんてあの容姿だから、同学年の連中に引っ張りだこにされている上に何度も実習でくのいちに使われているから、例え合格した所で実習の点数も低い」それもそうだ、と伊作は頷く。彼ならそうなりかねないだろう、と軽く想像もついた。引っ張りだこにされて不機嫌そうな仙蔵の顔が伊作の頭に浮かぶ。ご愁傷様だな、と伊作は心の中で思う。「頼む、善法寺。お前しかいないんだ!」は胸倉を掴んでいた手を離して、頭を下げる。「……なっ!」例え課題の合否にかかわる重要な事とは言えど、やはりこういう台詞を言われると照れる。男心と言うのは、まあ色々とある訳で。「頼まれてくれるよな」顔を上げた彼女の顔があまりにも必死だったので、伊作は気が付けば頷いていた。
課題の内容については、後で詳しいことを聞いたのだが、『男子の一人を女装させて、いかに周囲に溶け込ませるか』を試すものだそうである。
ちなみにその課題の対象となる男子は上級生に限られているようで、理由を言うと下級生は変装させやすいからだという。どちらも変わらない気がするのだが、彼女らにとってそれは重要な問題点らしい。そして下級生を対象としないのはもう一つ理由がある。多分こちらのほうが主な理由となると思われるのだが。一言で言ってしまえば、その課題である女装で何人の下級生を騙せたかが課題の点数の判断材料となるのだ。
なんとも、くのいちらしい計画である。いつも通りだが、……忍タマの扱いは酷い。
数分もかからないうちに、化粧道具を大量にもってきたは伊作の前に腰を下ろした。と、同時にガラガラ、と化粧道具を包んだ風呂敷が音を立てる。さすがはくのいちといった所だろうか、その化粧道具の多さは忍タマの持つ量の倍はあるかと思うほどだ。それほどまでに、多かった。紅の種類など軽く二十種類は超えていることだろう。おおかた、の場合は時間が惜しくて部屋にあった化粧道具を適当に全部もってきたと思われる。彼女は伊作の肩を掴んで言った。「化粧は私がする」「うん」「動くなよ」「うん」「目は瞑っていた方が良い」粉が目に入る、という声に伊作は瞼を閉じた。の「始めるぞ」という声とともに、化粧道具の匂いが鼻をついた。
今現在、は手馴れた動作で伊作の顔に化粧を施している。しかし、何と言うか顔が近い。かといって、瞼を閉じているので実際にどうなっているかは分からない。だが互いの肌の感触と体温が感じられる上に吐息がかかる距離まで近付いているというこの状況は、にひそやかに想いを寄せる伊作にとって非常に嬉しいことでもある。が、同時にそんな事を知られてはいけないので冷静さを保つ事をしなければならない。「あと少しで終わるからな」「うん」少し名残惜しいな、と思っていると「緊張しているのか?」と心配して声をかけられた。「う、うん。……まあ少しは」「そうか」一旦止めた手を、は再び動かし始める。紅を入れているのだろうか。唇をなぞる指の感触が妙に柔らかくて、思わず顔がにやけそうになるのをこらえる。「じっとしていろ、と言っただろう」全くお前と言う奴は、と少し怒る声が聞こえた。「ごめん」「まあ、終わったからいいんだが」「終わったの?」驚いて聞き返す。私が女装する時は、もっと時間がかかるのに。「ああ、目を開けてもいいぞ」ゆっくりと目を開けると、の顔が私の目の前に現れてちょっと吃驚する。
「ほれ、鏡だ」から差し出されたそれを見ると、そこには善法寺伊作ならぬ別人が写っていた。髪型ぐらいしか、顔のパーツの中で変化していない所は無い。「化粧でこんなに変わるのかー」さすが、くのいちといった所だろうか。伊作のする化粧の程度とは格が違っていた。「ざっとこんなものだ、髪は判別材料だからそのままでいいとして此れがくのいちの制服なんだが」「着がえろっていうこと!?」「察しが良い奴は、話が早くて好きだ」は、どこからか取り出したくのいちの制服をこちらに投げる。「わわ、」受け取ったものの、少し失敗してぐしゃぐしゃ、と服が伊作の体に絡まる。「じゃあ私は外で待っているから着替えたら呼んでくれ」「うん、分かった」
は障子を開けて、ぱたん、と閉める。伊作は化粧が落ちないように注意しながら着替えることにした。 数分後、伊作は着替え終わったので「終わったぞー、」と約束通り、外で待つに声をかける。
ぴしゃり、と障子が開いて、満足そうに微笑んだが現れた。「よし、では行こうか」「どこに?」女装した伊作は首をかしげた。後ろで結われた髪がふわりとゆれる。「決まっているだろう、化粧が崩れないうちに山本シナ先生に見せに行く」「へえ」「確か先生は学園の裏庭の方で待機していたはずだ」とりあえず裏庭に化粧を見せに行ってから生徒のいる長屋に行き、それから一刻で何人下級生を騙せたかを試したあと再び裏庭に戻り、山本シナ先生にその騙した人数を報告しにいくのである。「大変だね、くのいちも」移動しながら伊作が言う。「まあいつも利用される一年の忍タマ諸君に比べればマシな方だ」その隣を走りながらが苦笑した。「あ、それは言えてるかもしれない」伊作も釣られて苦笑する。「だろう?」
は、ははは、と珍しく大げさに笑った。結果的に、彼女は随分と高評価を得たらしい。その後、昼の食堂で「善法寺ありがとう!」と思い切り抱きついてきたのには周囲が一斉に驚いた。一瞬、鉢屋かと疑ったが、それはまさしく正真正銘本物のだったからまた驚きだ。
「一番私が評判良かった」満面の笑みで彼女は言った。「お前のおかげだ」「わ、私は別に何も…」していない、と言いかけた所で「いや、お前が協力してくれたおかげだよ」と彼女は照れくさそうに頭をかいた。「じゃあな、感謝するぞ善法寺!」まるで嵐のごとく去っていったをぼうっと目で追っていると、隣で食べていた食満留三郎がぽつりと呟いた。「いつの間にとあんなに仲良くなったんだ、伊作」「同じ委員会だし、この間のくのいちの課題に付き合ったからだと思うけど」「げ、お前もやったのか」あからさまに顔を顰めた級友の表情を見逃す輩などはいないだろう。「あ、留もやったんだ」推測でモノを言った伊作に、留三郎は溜息をついて頷いた。「全く、仙蔵に何度笑われたことか」「何回かやったの?」「三回」「うわあ…」話によると、立花仙蔵は八回ぐらいだったそうだ。八人も同じ考えを持った輩が居たらしい。それにしてもくのいちは、おだてるのが上手いなあとつくづく感心する。何度も何度も彼を女装させるなんて凄いと思う。「それでどうだったんだ、お前の方は」留三郎は言い終わった後で気付いて笑う。「ああ、聞くまでもなかったか?」「いや、私がするのとは格が違ったよ」伊作は苦笑する。「お前が知らず知らずのうちに敵を増やしていることに気付かないのも頷けるな」留三郎が誰にも聞こえないようにボソリと呟いた。
全く、学園内でと聞いて反応しない奴が居るだろうか。否、いないだろう。容姿・性格ともに秀でており、少し行動が抜けているところ意外は非の打ち所の無いほどのくのいちである彼女に心奪われるものはこの学園内にも少なからず存在する。寧ろ、異性同姓問わずに多すぎるほどに存在する。しかし彼女がそういう色恋沙汰にめっきり興味が無いので大抵の奴はその場で振られる事が殆どだ。というのも、伝えた好意が「愛してる」ではなく「敬愛している」と彼女の内では解釈がされているようだからである。結果的に、友達として認められることはあろうとも、恋人として認められることはない。よって、彼女に恋心を伝えることは前途多難である。で、話を戻すが、そんなといちゃこらしている奴を見てよく思う奴が居るだろうか。否、いないだろう。普段無口でクールな印象の彼女は、人に抱きつかれることはあろうとも自ら率先して抱きつくことはないのである。そんな彼女が、伊作に抱きついたのだ。事態はかなり深刻である。留三郎は不幸で不運な伊作に心底同情した。
「え、何か言った?」伊作がきょとんとして聞き返す。「何も言ってない」がつがつと昼食をかき込みながら留三郎が言い放った。
(
▲)(20080524)
 03/文次郎
03/文次郎
忍者馬鹿だとか忍者過ぎるとかギンギンだとか天才は馬鹿と紙一重だとか真面目過ぎるとかそんな事をいわれていても
本当はきっとおひとよしなだけ
月末。それは委員会にとって修羅場である。委員会の中で最も体力と学力と精神力を要するギンギンな会計委員会に選ばれた忍たま達が眠気と帳簿のダブルパンチに己の精神力をすり減らしながら、必死で格闘していた。「眠いー」「弱音を吐くな! そんなことでは会計委員として失格だぞ!」こんな会話が先程から数十回と繰り広げられている。もちろん、眠いと嘆くのは主に一年生の忍たま達だ。お互いに起こし起こされの押し問答を繰り返し。
寝たり起きたりを繰り返し。寝言をぶつくさと繰り返し。文句もだらだらと繰り返し。かくして忙しい会計委員の夜は更けていく。
「、帳簿確認してくれ」「そろそろ来る頃だと思っていたよ、潮江」のんびりと屋根で寝転がりながら日光浴をしているのもとに、文次郎がすたんっ、と忍者らしく登場した。もちろん、帳簿とは昨日の会計委員が必死になって作成していたもののことである。彼が帳簿の確認をを月末になると頼みに来る理由は、いくつかあるわけなのだがその経緯はもちろんある。最初、文次郎がダメもとで頼み込んできた帳簿の確認作業をが快く引き受けて手伝ってやったのが一番の理由だ。最も、という少女は頼まれたら断れないという保健委員の典型的な性分の代表例であるので、頼まれ事を快く引き受けてしまうのは、彼女の性格的な面が主に影響していると思われる。その結果、毎月月末になると彼は必ずの前に姿を現すようになったという訳だ。さて、潮江文次郎は通称『学園一忍者している』奴なので校則はあまり破らない。そんな訳で彼は、が男子禁制であるくのいちの長屋にいない時(を見計らっているのかいないのかは兎も角として)つまり、くのいち教室の区域以外の場所に彼女が一人でいるという好条件がそろっている場所によく現われる事が多い。まあ、他の奴らがいると話がややこしくなるというのが一番の理由に挙がるからだろう。「お前ぐらいしか頼る奴がいない、頼まれてくれ」ぶっきらぼうに文次郎が言葉を放つ。「私ぐらいしか、忍たまをむやみやたらに騙さないくのいちがいないからだろう」普段の態度と一寸たりとも変わることなく、むくりと起き上がって伸びをしながらが言った。「…そうとも言う」「じゃあやるか」ふわりとが微笑む。文次郎がそれにつられてニヤリと笑う。「おう」
「だあああ、帳簿間違いだ!」盛大に潮江文次郎の声が室内に木霊した。面倒臭い、またアイツだ。とぶつくさと文句を言いながら彼は帳簿の間違いを直していく。「一年の奴か」が問いかける。不思議そうに文次郎が顔を上げ、に視線を移す。「他に誰がやるんだ」「寝ぼけた会計委員だろう」「言えてるだけに反論が出来ない…不覚!」ぐう、と普段らしからぬ彼は少し引き下がった。多分連日のように睡眠時間が少ないのが影響しているのだろう。彼らしくない、とは思う。――普段なら、きっともう少し言い返してくるはずだ。「よし、これで最後だ」が帳簿を一冊右に積み上げ、左に残っている一冊の帳簿に手を伸ばす。文次郎が、顔を上げて少々驚きの混じった目でを見た。「仕事が早いな、相変わらず。会計委員に入ったらどうだ?」「遠慮しておく、連日連夜眠れないのは流石に厳しい」「やってることは変わらないだろう」「いや、変わる」は、帳簿からフッと視線を上げた。「お前が私に頭を下げてまで頼みこまなくなる」「…な!」からかわれたと思った文次郎がばん、と机を叩く。心なしか、頬が染まっているようにも見える。「というのは冗談にして」「冗談かよ!」思いきり、ずてーという効果音とともに転ぶ文次郎。「本気のほうが良かったか? そんな事が本当だったら私は立花仙蔵並みに性格が悪くなってしまうではないか」の的を射た意見に、ぐう…一理あるな。と文次郎は机に直った。辺りに筆をさらさらと動かす時の音が響く。それから互いに暫くの沈黙が続いた後、がそれを破った。「こっちは終わったぞ」「ちょうど俺も終わった所だ」帳簿を持って立ち上がる文次郎に習って、立ち上がる。「届けに行くの手伝おうか」「頼む」それぞれに自分のこなした分の帳簿を両手いっぱいに持ちながら、廊下を早足で先生の元に向かう。職員室の戸を開けた所までは良かったが、ちょうど先生はいなかったので机に帳簿を置いてその場を立ち去る。「なあ、」「何だ、潮江」「相談があるんだが」珍しく神妙な口調に、は運んでいた足を止めて文次郎を振り返る。「私でよければ聞くぞ」「実はな…」文次郎が口火を切る。
「という訳なんだが」「盛大に作者が端折ったように見えるが、まあいいだろう。事情は分かった」「どうしたらいいか、お前なら分かるかと思ったんだが」不安そうにこちらを見る文次郎を見て、はハハハと乾いた笑い声を上げた。勿論、そんなことをされて黙っている文次郎ではない。「おい、真面目な話をしてるんだぞ!」<彼は相手が女だということも忘れてか、の胸倉を掴んだ。「不器用な奴だな、お前は」ふっ、とが苦笑する。同時に文次郎につかまれた手をサッと払い、庭の方に逃げて彼と距離をとる。<「……な! 、貴様に言われる筋合いは無いな。初心なお前に何が分かるんだ」「ははははは! 潮江に言われる筋合いも無いな、そもそもお前が相談をけしかけてきたのだろうが」「なんだとお、言ったな貴様! ぎんぎーん!」華麗に廊下から手裏剣を投げる文次郎。はギリギリでそれを回避して手裏剣が己の体に刺さることを免れる。行き場をなくした手裏剣は、後ろに生えていた木にサクサクっと音を立てて刺さった。「ちょ、手裏剣は無いだろう。顔に当たったらどうしてくれる!」潮江を思い切り振り返ったが言う。「は! 此れくらい避けられぬようではお前も忍としてはまだまだ未熟者だ!」「お前! 女には優しくしろと習わなかったのか、阿呆が」ぎんぎーんと高笑いをする潮江に低姿勢で走りながら近付いていき、潮江の目の前まで来た時点で彼の胸倉を掴む。と、突如視界が暗転する。なにやら温かい感触に包まれていると感じた時、自分が潮江に抱きしめられている事が分かった。「な、何を!」「喚くな! じっとしてろ」訳がわからないを差し置いて、潮江はの背に手を回す。「ちょ、潮江。……馬鹿、此処は廊下だぞ」「悪いが、お前の鈍感さには嫌気がさす」「はあ、何が言いたいのか分からないが」一方的に抱きしめられた状態で、は頭に疑問符を浮かべた。「此処まで言っても分からないとは、噂以上の鈍感だな」「何だと! 私は勘は鋭い方だ」「それなら、何故気付かない」「何にだ」文次郎は、の肩に手を乗せるとすうと息を吸い込んだ。「俺がお前を好きだということにだ」「はあ、それは気付かなかった」目をぱちくりと瞬かせながら、は軽い返事を返す。「人の一世一代の大勝負を軽く受け流すな」呆れた文次郎が肩を落とす。は少し悩んだ後、表情をいつも通りに戻して問いかけた。「それは、どういう意味で受け取ればいい?」「恋人になってくれという意味だ」「分かった」そこで、はクスクスと笑う。「初めてだ、そんな事を言われたのは」「本当にいいのか?」あっさりと了承を得た文次郎がきょとんとする。「お前が言ったんだろう、変な奴だな」「…な! 変とは何だ、変とは!」「お前のことだ」クスクスと笑いながら、は文次郎の背に腕を回して、ずんっ、と体重をかける。「わ!」不意を衝かれた文次郎は、ふらりとバランスを崩してもろともそのまま廊下へと仰向けに倒れこんだ。後日、それを偶然見た仙蔵に文次郎が散々からかわれるのは、また別の話。
(
▲)(20080601)
 04/長次
04/長次
君が知っているかどうかなんて知らない。私が知っているかどうはは教えない。
静かな静寂が保たれている図書室。「お願いします」今日も一人、いつものように本を借りるくのいちの姿があった。「…どうぞ」貸し出し作業の終わった図書委員長が本を少女に差し出す。「ありがとう」少女は無表情にそれを受け取ると、いつものように図書室から出ていく。中在家はその姿が見えなくなるまで目で追うとまた業務へと戻る。先程の少女は
。優秀と呼ばれるくのいち内でも一目置かれている存在の少女だ。彼女の武勇伝は後をたたず、卒業後の進路には困らないほどにいろいろな所からスカウトされているようだ。会話などと呼ばれる事は殆どしたことは無いしかし、彼女の借りる本が自分の趣味と悉く同じという事が多少気になる点ではある。面白い、と感じたりする本。興味深い、と感じたりする本自分が興味を持った本と同じ本を、彼女は借りている此処以外で話したことはない此処以外で出くわすこともないけれども此処は接点の少ない彼女と唯一同じ趣味を共有できる場所である。喩え会話は無くとも、同じ趣味だと分かる。喩え校舎内であわなくとも、同じ場所に居る。それだけで、何となく安心できた。単純だといわれても構わないかもしれない。しかし、読書という同じ趣味を持ち尚且つ同じ部類の思考回路をもっているとすると、かなり希少種な人物となる。そんな人物とこの先会う事なんて、――あるかもしれないが、ほぼ皆無に等しいといっても過言ではない。それほど、彼女という存在は、自分にとって大きなものなのだと知った。
あの本の面白さについて、彼女の観点からどう解釈するのか、あの本の見せ場へ続く伏線について、彼女はどう思うのかとか、あの本の全体の話の流れとか繋がり方について彼女はどう考えているのか、とか。そういう事が聞きたい。聞きたいのに、聞けない。自分が口下手というのは、この短い月日の中で十分に分かっているつもりだ。しかし、それに引き換えた所で、彼女から語ってもらう分には問題ないはずである。いつか、自分にもそんな勇気がもてるのだろうか。そんな事を思いながら、彼女の貸し出し票を眺める。まるで、自分の読んだ本の後を追いかけて彼女が来るみたいで。少し、自惚れてみたりもして。でも多分そんな事は無いとおもって。そう思うと、少し寂しい気分になったりもして。
そこで、――ああ、やっぱり好きなんだな。と思ったりして。でもそんなことが意味のない行動だということぐらいは分かっているつもりなんだ。
(
▲)
 05/伊作
05/伊作
その感情が何だか分からなかった。
確かに、私は通称不幸委員と呼ばれている保健委員に六年目の配属を強いられた。しかし、だ。それを差し引いた所で、この仕打ちは無いだろうと呆れた。「何故だ、…全く訳がわからない」隣の友人にぼやいたが彼女は「ま、いいじゃん」と答えるのみでいつも通りニコニコと笑みを浮かべている。畜生め、私の運は彼女が全部持っていったとしか思えなかった。そういう彼女は六年目の体育委員だそうだ。かといって私は体育委員になりたいわけではない。まあ、別に保健委員が嫌という訳ではない。保健委員であるが故に周りからの視線が何やら哀れみを含んだようなもので痛々しいのが嫌なだけだ。可哀相なものを見る目で自分のことを見られるのは、いかんせん好きではない。まあ、万人がそう思っているとは言いがたいが、大抵の奴ならば好ましくないと言うのが一般的だ。勿論、私もその部類に入るわけだが、それにしても今日は全くもってついていない。
災難が始まったのは、実践授業で行った班別行動時のことだった。実践内容は簡単。罠の仕掛けられた道を通って目的の場所までたどり着いたら合格、というものである。しかしながら、それを実際にしてのける事は非常に困難だった。「きゃあ!」どん、という音とともに煙球が炸裂した。同じグループになった少女の短い悲鳴が上がる。「――大丈夫か、一葉!」「気をつけないと危ないよーっ」上から私、その次に友人である夢子が一葉と呼ばれる先ほど悲鳴をあげた少女の身を案じて叫ぶ。煙によって、一葉の姿は見えない。「うん、大丈夫。ありがとうさん」返事が聞こえたのでそちらを振り向けば、彼女の背後500mほどの場所に何かキラリと煌くモノが動いているのに気付いた。「礼には及ばない」そう言って、私は彼女の影のほうに移動する。とまあ煙幕がやや薄れてきた所で、私はそれが手裏剣であることを確認したが、既にもう目前にそれは迫っていた。体が咄嗟に反応して、彼女を庇って地面に伏せる。彼女の髪から漂う甘ったるい香りが鼻をついた。彼女に当たるはずであった手裏剣は、何枚かは私たちの上を通り過ぎ、何枚かは私の背中に直撃した。グサグサという音とともに、激痛が背を貫く。「うっ」と、痛さで呻き声を漏らすと、「御免なさい」という言葉が聞こえた。暫く飛んできた手裏剣もシャキンという音を立てて私の足付近の地面に刺さったものを最後に、ぴたりと止んだ。私は庇っていた彼女の上から立ち退いた。上体を起こした一葉に手を差し伸べる。手をとった彼女は俯いて、掠れた蚊の鳴くような声で言った。「足手まといになって御免なさい。私がいなければさんが怪我なんてすること無かったのに!」「結局どこかしらに罠は仕掛けられている、一葉がいようがいまいが無傷で目的地につくという事は無いだろう」私は「気落ちするな」と彼女に言った。正直此処まで来て落ち込まれては迷惑だった。背中もずきずきと痛むが、だんだんと感覚はなくなってきた。これは危ういので早く目的地に着きたいところだった。一刻を争う、成績に関わる重大な試験だ。こんな所で成績を落としては今まで積み重ねてきた意味が無い。結局その後は何度か罠に引っかかりそうになったが、直前で回避したのでなんとか避ける事ができた。しかし、である。「とうちゃーっく! 、一葉、私たち最短記録だって!」夢子が先生へ報告をしにいって結果を聞くと喜んで飛び跳ねた。「そうか、それは良かった……な」私は目を細めて微笑み、夢子の方を振り向いた。が、突然めまいと立ちくらみが合わさったような症状がおこりフラリと足元がよろめく。そして視界は暗くなる。地面の衝撃をわずかに感じる。意識が遠のいていくのが分かる。「さん!」と、最後に一葉の声が聞こえたような気がした。
私は保健室で目が覚めた。どうやら軽い貧血のようだった。やはり出血多量がよくなかったらしい。目を何度か瞬かせ、うっすらとした視界の中外を見るとどうやらもう夕方だった。どうやら、私は随分と気を失っていたようだ。烏がそれを馬鹿にするかのように鳴いた。私は保健室の畳に敷かれた布団から上体だけ起こす。と、側に善法寺らしき人影が座っていた事に気付く。彼は机に突っ伏して何事か書き物をしていた。どうやら書類か何かのようだ。「善法寺、か」「あ、目が覚めた?」私が名を呼ぶと、彼はこちらを振り向いた。「ずいぶんと迷惑だったろう」「別にそんな事はないんだけど……ってうわあ!」善法寺が立ち上がろうとして、何かに足をとられて躓いた。バランスを崩してこちらに倒れてくる。どん、という衝撃。私は棚にぶつかる。「ごめん!」「……な!」何をする! と、叫ぶまもなく、その倒れた衝撃により何やら色々な物がどかどかと棚の上から降ってきた。それは、液体から薬草からトイレットペーパーまで色々と幅広く。普段なら降ってくる筈の無い物が降ってきたのだ。私はバランスを崩してしたたかに畳に頭を打ち付けた。そして液体の入った壷を、上に乗る善法寺のせいで避けきれずにもろにかぶる。壷は善法寺の頭に直撃し、彼の意識を奪ったようだ。彼の体重がずん、と重くなる。ねばねばとした粘液のような液体が頬をつたった。中身と行き場をなくした壷がごろごろところがっていく。頬にへばりついた薬草を払いのけながら、私の腰辺りに圧し掛かる善法寺を見て眉を顰めた。彼もまた、謎の液体にまみれている。粘々としてテカテカと気味悪く光るそれは何か見覚えがあるような気がした。何度か、調合の実習で使った気がする薬品だ。特に害は無かったように思える。ただ気持ち悪いだけのそれは、ぶつけた相手に不快感を与え、こちらに逃げる隙を作る。とか何とかそんな内容だったはずだ。実際問題、その通りだと私は思う。こんなもの喰らったらひとたまりも無い。私は粘々する液体と悶々とした不快感とともに考えた。善法寺は気絶していて重くて動かないので取り敢えず寝ようという考えに思い至る。不幸委員とはこういうのを指すのだろうかと、私はつくづく思った。勘弁してくれ。
目を覚ませば夜だった。寝てばかりだと思ったが仕方が無い。そして息苦しい。むくりと体を起き上がらせようとすると、起き上がらなかったので不思議に思ってイライラしながら目を瞬く。「……!」どれだけ寝相が悪いのだ、こいつは! と叫びたくなるほどに、彼は私の上に圧し掛かっていた。彼の顔が真横に合って落ち着かない。畜生、なんだこれは。起きてくれ、善法寺!「うううん」<善法寺が唸る。私は勘弁してくれと思いながら、天井を仰いだ。ぬめぬめとしている服が妙に気持ち悪い。私は起きたばかりの低血圧のまま考える。どうやって善法寺を起こすかどうかについてだ。まず始めに思いついたのが、首を絞めてみることだった。しかし喘ぎ声を少しあげただけで一向に起きる様子は無い。次に、頭を軽く殴ってみたりしたが状況は変わらなかった。他に方法も思いつかないので私は面倒臭くなってもう一度目を閉じた。そのときだった。バン、と開くふすま。「おい、善法寺いるかー。……――ってなにやってんだ!」その声で私は目を開ける。月明かりがまぶしくて目を何度か瞬くと、ぼんやりとした視界に潮江の顔が映る。「潮江…、上に乗っかって気絶してるコイツをどかしてくれないか」私は善法寺を指差す。「何が如何してそうなったんだよ」潮江も善法寺を指差す。「まさかお前……「勘違いするなよ、善法寺が転んだおかげで色々な薬品を頭からかぶってしまっただけだ」「……そうか、」潮江は考える。「じゃあどかすから動くなよ」転んで倒れてきて退こうとしたら壷に激突して気を失っている善法寺はまだ気を失ったままである。そんな善法寺をひょい、と担ぐと彼は顔を顰めた。おそらく彼に付着した粘々とした薬品に触れたからであろう。私は漸く重さから開放されて立ち上がる。布団がグチャリと水を含んだ気味のの悪い音を立てた。私も顔を顰める。取り敢えず善法寺を取り払ってくれた潮江に「ありがとう」と礼を言った。私は布団をふたつに折った、そして壁側に寄せる。その上に潮江が善法寺を乗せた。「別に、構わねえけど」彼は善法寺を置くとぶっきらぼうに言った。「いや、助かった。誰か来なかったら朝まであのままだったよ」私が苦笑して言うと、潮江は溜息をつく。「全く、無防備すぎだろ」「襲う気にでもなったか、変態め」「な…! そんな訳ねえよ!」慌てて否定してきた潮江が面白くてクスクスと笑う。開いたふすまから入ってくる夜風がひんやりとして涼しかった。くすぐったくて目を細める。所々節々が痛むのは、きっと上に乗っていた善法寺のせいだろう。動かすたびに、みしみしという音が立ちそうなほど筋肉が疲労していた。「あのさ、潮江」「何だ」とまあそこで私が善法寺のことを潮江に頼もうとした所で間が悪く夢子が入ってきた。「
―ってうわ、ぐちゃぐちゃ……もしかして事後?」「馬鹿、そういう発言は慎めと何度言ったらわかる」と、私。「わあ、知らなかった。モンジってみたいなのが趣味だったんだ…!」と、夢子。「話を飛躍させるな! おい、何とか言ってくれよ」と、潮江。「こいつに何を言っても無駄だ、潮江。こいつの頭の中は全く理解不能だからな」わたしが言うと、「そういうことじゃねえだろ!」と潮江がイライラを吐き出す。「わたしは応援するよ! 二人でも三人でも、…うーん、寧ろ三人のほうが強姦ぽいからそのほうがわたし好きだな」まだ何か反論したそうな顔をして夢子を見る潮江に、私は普段の経験から話しかける。「ほうっておけば、その内おさまるだろう。コイツはいつもこんなだから発言内容は真に受けない方がいい」「そうなのか」「そうだ。こればかりは、私にはどうもできない」私は振り返ってこちらを見た潮江と、自分の妄想を話し続ける夢子を交互に見た後、ふるふると首を振った。「大変だな、」「善法寺ほどではない」潮江が言ったのに対して私は後ろの善法寺を見る。まだ起きない所を見ると、まだ気絶しているようだ。恐るべし、壷。アレが頭に当たるのはなかなかに痛いと私は思う。当たらなくて本当に良かった。ふと外を見て、そろそろ寮に帰らないとまずいかと考える。「それじゃあ私はこいつを引き連れていくから、潮江は善法寺を頼む」「おう」「じゃあな」「ああ」軽く潮江に手を振ると、彼も手を振り返す。私はまだ妄想を語っている夢子を引っ張って寮に戻ることにした。寮に戻り、寝巻きを持って風呂に入ろうとしたらシナ先生と鉢合わせた。「どうしたの?」と聞かれたので、実習で使った薬品の壷が降ってきて善法寺ともども薬品まみれになったことを伝えた。それを話すと先生は分かってくれたようで、それは災難だったわね、と言って「まだ湯は残っているから、早くお風呂にはいってらっしゃい」と笑顔で言い残すと、仕事で急いでいるようで早々に立ち去っていった。のんびりと湯船につかろうと忍装束を脱ぎ捨てる。髪を解いて湯を浴びると付着していた薬品が流れていった。本当に今日は災難だった。うこんな事はありませんようにと思う反面、またあってもいいかもしれないと思ってしまう自分がいた。いいんだか悪いんだかよくわからない気分のまま、すっきりした気分で風呂から出る。忍装束を洗って、脱衣所で浴衣を着る。適当に髪の毛を乾かして荷物を持って自室へ向かう。既に自室ではすうすうと寝息を立てて夢子が寝ていた。どことなく寂しい気分で布団を敷いて床についた。どこからこんな気持ちが来るのかわからなかった。明日はこんな事がありませんように、と、こころなく願った。
翌日、食堂に入ると視線が集まった。何事かよく分からなかったが、夢子を睨むと彼女が怯んだので元凶は此処かと思った。ということは、まあ昨日の事がひろまったのだろう。全く迷惑千万なヤツだと思った。「さま! 潮江くんと付き合ってるとかホントですか」席に着くと、同じクラスの奴が大きな声で話しかけてきた。非常に視線が痛い。潮江は有名人だったか、はたまた人気があるのか。非常に視線が痛い。「違う」と私は短く答える。実際にそんな既成事実はない。「じゃあまさか肉体だけの関係とか」先程とは違う奴が話しかけてきた。「違う」とまた短く答える。勘弁してくれ。「じゃあ善法寺さんとはどんな関係ですか」また違う奴が問いかけてきた。「同じ委員会なだけで何も無い」私はそれだけ答えて、味噌汁をかきこんだ。「ええー!」周りから残念そうな声が上がる。周りの視線も痛い。なんだ、何が望みだお前たちは。「さまなら、誰かと関係があるかと思ったのですけど」「寧ろ私たちと付き合っていただきたいくらいで!」「だめよ、抜け駆けなんてずるい」「だめよ、さまは貴方なんて眼中に無くってよ」「ええ、それじゃあ男どもを手玉にとって遊んでほしいわ」好き勝手はなす彼女らに、私は少し耐えかねたので一蹴の言葉を向ける。「公衆の面前でそういう発言は控えておけ」「はーい」と、彼女らは口をそろえて言うと、「きゃー、さまに注意されちゃった!」などと言いながら、食堂を去っていった。なにがしたかったのかは、謎に包まれている。
「おい、と付き合ってるってホントか?」「なに言ってんだよ、仙蔵?」そんな訳無いだろ、と俺は首をかしげた。「食堂で噂になっていたぞ」「な…!」「何だ、違うのか。てっきり私はそうだと思っていた」
(
▲)(20080505)
 01/文次郎
01/文次郎