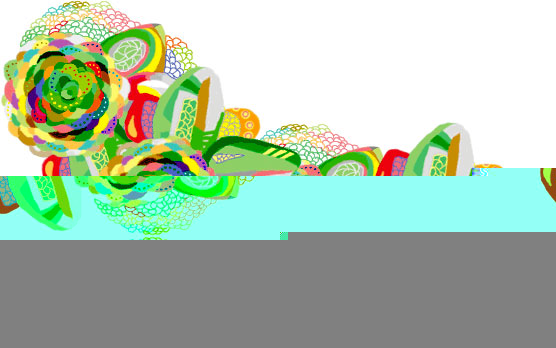 本日何度目かになる盛大なため息をついた。公園で一人のいい大人が浮かない顔をして座り込んでいるなんて、まるでリストラにでもあったみたいに見えるだろう。ほんとうに、今日はツキが回ってこなかったのだ。と、そう思えば少し気持ちがおさまったかのような錯覚を覚える。要は気持ちの問題で、何事もそう思わなければやってられないことなんていくらでも存在するのだ。普段亜麻色をした髪は、過度のストレスと憂鬱な気持ちから白銀まで白くなっている。これは老化ではなく、私の使いどころのないNEXTの能力である。 今日は本当に嫌な日だった。いつもならミスしないはずの一つ下の後輩が作成した営業のグラフの数字が間違っていたらしく関係のない私が上司からとばっちりをくらったし、後輩は後輩でそのまま数字を入力しただけですと上司が間違えていたらしい元データのコピーを私に押し付けてきたし、それを上司に伝えるべきか悩んでいたら掃除のおばさんとぶつかってその拍子でひっくり返ったバケツの水を避けきれずにスーツの上から下までべっしょりと濡れてしまったし、資料もパアになってしまった。ゴミ箱に使えなくなった資料をぶち込んで、私が上司の元に報告に戻れば彼は営業時間が終わったために帰ったと言う。なんて勝手な上司だ。大きな社会に平社員ごときが牙なんてむけられるはずもないのに。 私は先程から脳内でリフレインしている、上司から言われたねちねちとした嫌味の言葉たちを頭から追い払う。確認したとして、元のデータから間違っていたなら確認のしようがないじゃないか。と口をすぼめた。しばらく何も考えないようにしながら、いらいらとした気持ちで噴水を見つめていたが気づけばもう日が傾き見事なオレンジ色の夕焼けが広がっている。綺麗な夕日にうっとりとして一瞬頭がまっしろになったが、ふと時計を見ればもう六時半を回っている。会社を出たのが五時ごろで、その後に服屋で買い物ついでに服を着替えてそのまま公園に来たことを考えると、かれこれ一時間程度座っていたらしい。もうこんな時間、と席を立とうかと思った瞬間だった。 「隣に座っても?」 「え、ええ」 声のした方へ顔を向ければ、ふわりとした金髪の男性が立っている。ジャケットに、Tシャツに、ジーンズ、という至って普通の組み合わせを着こなし、隣にはゴールデンレトリバー。ホリの深めな顔立ちで、鼻が高かった。公園には空いているベンチならまだいくつかあったはずだったのに、なぜ彼はここを選んだのだろうか。定位置だったのなら、少し申し訳なく思う。私は立ち上がるのが気まずくなって、そのまま姿勢を正すだけに終わった。 「君は私の知り合いによく似ている」 「え?」 「今から話す事は私の独り言だと思って、聞き流してくれると嬉しい。そして嬉しい」 私はその人の話す言葉に、ぼんやりと頷いた。その後に続く彼の話を要約していくと、主にこうだ。悩みを親身になって聞いてくれていた彼女にお礼が言えなかった事を後悔しているということ。そして彼女に思いを伝えたかったということ。色恋沙汰なんて会社に入ってからは縁遠い話になっていた私だったから、そんな初々しい話をこの男の人から聴くことになるとは思いもしなかった。 「彼女に、そっくりなんだ」 私は噴水から男性へ目を向ける。透き通るような青い瞳がすうっと細くなって、彼は人のよさそうな笑顔を向ける。ぱちぱちと目を瞬かせるだけの私に、彼は軽快な笑い声をあげた。「おかしいだろう? 出会ったばかりの君に君に一目惚れしてしまったなんて」 「あ、あの、え? どういう」 動揺する私をそのままに、彼は話を進めていく。ぐるぐると私の頭の中で「一目ぼれしてしまったなんて」という言葉がまわっていく。じわじわと浸食されるように、私の頭がその言葉の真意を理解しようと奔走している。ここで会ったのは何かの縁なのだろうか。わからないままほんわりと空気に流されている私がいて、頭がぐるぐるとまわる。と、突然視界が真っ赤に染まり、ふんわりといい匂いが鼻をかすめた。 「よかったらどうか、今度一度お食事でも?」 あらかじめ用意されていたような、真っ赤なバラの花束だった。 「わあ綺麗…、でも私が受け取っても…? その方に渡さなくてもいいのですか?」 「もう大丈夫なんだ。だから、その…君が受け取ってくれれば、私も嬉しいのだけれど…」 にこりとはにかむように笑う彼の笑顔に、気づけば自然と私もつられて笑っていた。張りつめていたようななにかがぷつんと切れたみたいに。 「じゃあ、花束。貰ってもいいですか?」 「本当かい?」 「本当です」 彼は瞳を大きく見開いて、私の手を花束ごと包み込んだ。ぐいっと近づく彼の顔に反射から私の背がのけぞる。そのまま数秒こう着状態がつづいて、彼がおもむろに俯いて震えはじめた。どうしたのだろうと彼を下から覗きこめば、彼は急に顔を上げて大きな声で「ありがとう! そしてありがとう!」と感謝の言葉を唱え始める。何やらどこかで聞いたようなフレーズだと頭の中を探してみたけれどぱっと思い当らない。 「おっと、まだ私の名前を名乗っていなかったね」 「あ」 「私は、キース。キース・グッドマンだ。よかったら君の名前を教えてはくれないかい?」 「です」 「、素敵な名前だ…」 彼が言葉を発した瞬間、びーびーとなにかの発信音が鳴る。「おっと、呼び出しみたいだ」と彼がはにかむように笑った。「私の連絡先はここに、」と彼が指差した先にはバラの花束に埋もれているメッセージカード。よく見れば綺麗な文字で電話番号のようなものが書いてあるように見える。「ではまた会おう!」なんて、どこかで聞いたような台詞を言いながら走り去っていく彼を、私はぽつんとつったったまま見つめていた。まるで嵐の去ったような静けさの中、私は真っ赤に染まった髪と真っ赤なバラの花束と共に鼻歌交じりで帰っていく。 (20111030:素材)空シスの回の後日談的おはなし。素敵な企画ありがとうございました! |