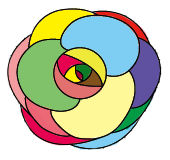 どろり、流れるような感情が流れる。寝覚めはとても最悪だった。半身をベッドから起して、がいない事を確認する。もう既に仕事に行ってしまったのだろうか、大きなあくびを一つするけれど眠気は冷めない。僕は重い体に鞭打ちながらベッドを下りて台所へと向かう。いつも彼女は忽然とやってきて、空気のようにいなくなる。幽霊ではないけれども僕が都合のいいような男なのかもしれない、という考えに至るのに時間はかからなかった。がそのつもりがなかったとしても、携帯の電話もたまにしか通じないしメールも8割型帰ってこない。一度「それって本当につきあってるの?」と聞かれたことがあるけれど、でも僕はこうしていることでしか彼女とつながっていることができない。ため息をつく。これじゃあただの意気地のない男だった。はっきりと恋人と名乗れるような関係でもなくて、ただ依存しているだけのような関係。それでも僕は彼女がいないと何かが欠けているようなもやもやとした気持ちになるし恐らく彼女の場合も僕に会いに来ることが生活の一部として成立しているのだろう。だからこそ成り立っているだけの脆い関係だと思う。冷蔵庫の前で立ち止まり扉を開いて水の入ったペットボトルを出す。ぱたんと閉めると拗ねたようにブーンという音がする。ペットボトルのふたを開けながらリビングへと行けば、彼女はじっとこちらを見ていた。 「会社は?」 「イワンが起きるのを待ってみたの、」ふたつの黒い瞳がこちらを見つめている。「今日は昼から出勤だから」 「そうなんだ、珍しい」 何を考えているか分からない彼女の黒い二つの瞳には、僕が考えていることすべてを見透かされていそうで少しだけ恐ろしくもある。けれどもその瞳は虚のようでもありながらガラスのように僕の姿を反射しながら映していて、時折ゆらりとゆれる光できらりとひかるのだった。純粋にその眼がきれいでうつくしくて目が離せなくなる。まるで獲物を狙う猫のような、それでいて静かな嵐の前のような静かな瞳だ。が自分で焼いたらしいトーストをシャリシャリと齧りながら、そのさらりとした黒い髪を耳にかけた。テーブルの上に載っているもう一人分の皿の上にちょんと載っているトーストをとって、僕はシャリシャリと食べ始める。 「なにか着たら?」 彼女は不思議そうに首をかしげた。そこで初めて僕は上半身に何もまとっていないことに気付く。 「ご、ごめん」 バターの塗ってあったトーストを皿に戻すと、僕は慌てて寝室に戻り適当な服に袖を通す。そういえばそうだった、なんて意識が妙に覚醒してくる感覚がおそってきて昨晩の出来事が少しだけ鮮明に脳裏によみがえる。胸の奥の方がぎゅうっとなるこの感じは、スプーンで体の中を内側から抉られているような気分になる。少しだけベッドに横になると、スプリングがぎしりと鳴った。彼女が立ち上がったらしい、ぱたん、と言う音が子気味良く響く。 「イワン」 「なに、」 またその眼だ。 「今月の家賃、」は僕の家に来るたびに毎月宿代と称していくらか置いていく。「これね」 茶封筒をベッド脇のチェストに置く。いらないと言ったら私の愛が受け取れないの、と珍しくその端正な顔を顰めた事をよく覚えている。よく膨らんだ茶封筒はそれだけで一般社員の月給くらいはあるのではないか、と思うほどによく肥えている。もしかしたらそれよりも多いのかもしれない。ここの家賃の数倍はあるだろう封筒を、簡単に僕は受け取るわけにはいかないし、その金が何の金なのかはあまり考えたくはなかった。 「僕は、がいればいいっていったのに」 その金に僕が手をつけたことは一度も無くて、今もベッド脇のチェストの棚に全部入っている。恐らく相当な額になっているだろうそれに、まだ彼女は気がついていない。そのほうが都合がよかったし、僕も何かよくわからないものに手を出すのは罪悪感から少し気が引けた。 「まあいいけど」彼女はため息をついて、僕の横たわる隣に腰かける。少しだけスプリングが軋んだ。 少しだけ沈黙があった。カチカチと時計の秒針の音が聞こえる程度の静寂。半身をゆっくり起こせばスプリングの軋みと共に彼女の瞳に落ちる影が一瞬だけ見えた。声をかければ、がはっとしたように僕の方を振り向いた。どうしてそんな表情をするのだろうか、彼女は少しだけ目を伏せる。その瞳がゆらゆらと揺れている。動揺しているのだろうか、だとしたら、いったい何に。 「、何かあったら僕に言ってって、」僕はの肩を両手で引き寄せる。「そう言ったはずだけど」 「別にそこまでの事でもないから」 大丈夫よ、と彼女は弱弱しく笑う。 「の嘘、そんなに下手だったかな?」 「嘘じゃないよ」 は表情を悟られないようになのか、僕の胸板に頭をぐりぐりと押し付けてくる。ため息をついた。 「一人で抱え込まなくても僕がいるじゃないか。僕ってそんなに頼りないかな」 びくりと彼女の肩が震える。が何かを抱えていて葛藤しているのは間違いなく事実で、僕が信用されていようが信頼まではされていないのを顕著に物語っていた。それがとても悔しくて、もどかしい。、僕の。 「ごめん、今は話せないの」 でも話すから、と一言だけ。彼女の仕事はいかがわしい仕事ではないが、好まれた仕事ではないのは何となくわかっている。恐らく仕事上のトラブルが原因なのだろうとも、僕でも分かる。けれども、僕は悔やんだところで彼女に縋るしか術は無かったし、それは恐らく彼女も同じだったから。問い詰める事はしない。周りに何を言われようが、僕は結局彼女に依存しているのだ。 「わかった」 一言だけ、彼女に告げて僕は静かに腕の中のを抱きしめた。 (20110818:素材)企画の副産物ですん。始終胸糞悪い話もだいすきなのでRADWIMPSを聞きながら江国香織さんを思い浮かべていたらイワシとイワンが見分けつかないくらいになってきてイワンをイワシに空目しすぎてシリアスな場面で爆笑の嵐でした きっとイワシでも見切れるでござるシュッシュ |