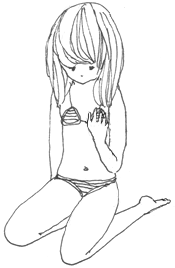 涙が出る。何が悲しくてこの仕事をしなくてはいけなくなったのか、理由をさかのぼればいろいろとあるので私はもう何も言及しないことにする。ああもうどうにでもなればいい、諦めてにこりとカメラに笑顔。いいねー、というカメラマンの声に、私は内心ため息をついた。事の始まりはこの下着メーカーとアポロンメディアが協賛して下着を作ったのがきっかけだ。下着メーカーのポスターのあおり文句による女性からの人気の殺到、そしてただの一般社員が本来の姿である私はうっかり正体不明のモデルとして活動することになってしまったのである。もちろんヒーローの二人とはうっかり会社で鉢合わせしてしまう事もあるのだが、正体が全くばれてはいない。これは奇跡に近いだろうと私は何となく思った。化粧一つで女が全く別人になるものとは初めて知った。 「ありがとうございました」 今日の撮影が終わり、カメラマンに挨拶をする。うっかり最新の下着を撮影の後にいくつか貰えちゃうのがこの仕事のいい所なのだけれども、なにか大事なものを毎回毎回失っている気がするのは気のせいではないはずだ。でも買うと高いこの下着がただで貰えてその上にギャラも給料に上乗せしてつくなんて。とてもうれしい、と思う自分はなんと現金な奴なのだろう。いや、お金も下着も大事だ。あいにくの所、地味な一般社員である私が下着を見せる相手なんていないけれども。 そそくさとコートを羽織り、スタジオを出て控え室へと急ぐ。今日はマネージャ(同僚)は仕事で忙しいとかそんな理由で不在だった。簡単な仕事だったので恐らくアフターファイブと称される時間帯から合コンにでも行くのだろう。羨ましい奴だ。私は控室で派手な化粧と下着を着替えていつもの事務服に戻る。下着をなんとか袋に戻して鞄の中につめて、段ボールの中に入った下着を見つめる。これで今月三箱目だった。宛先を書いてこれを受付に渡しておくと、家に届くらしい。なんとも便利でお得だった。もちろん送料は会社持ちである。びりびりとガムテープで段ボールが開かないように蓋を固定する。郵便配達の紙に宛名を書いて段ボールに張り付け、ぱぱっと後片付けを済ませるとコートを羽織る。忘れ物は無い。扉を開けて段ボールを持ち、外へ出てから扉を閉める。前の見えなくなるような大きな段ボールは、一人で運ぶのには少し骨が折れるような代物だったけれども、それくらいの価値はあるものなので文句は言わない。 廊下にチラチラとモデルとしての私のポスターが貼ってあり、前回の非常に恥ずかしいポーズとキャッチコピーが視界をかすめる。ちょっぴりクールなキャラクターとして売り出しているらしく、モデルとしてインタビューや会話に参加するなんて仕事はまずないということだった。救われた気分になったけれども、それとは別にどうやらメディアが血眼になって正体を探っているらしい。テレビの取材も御法度なので、本格的に謎に包まれているミステリアスガールの正体を探れ、なんて番組も持ち上がっているらしい。けれども私はいつも通りに事務の作業をこなすだけだったし、それ以上でもそれ以下でもない。ロイズさんはその手の質問が来ても一切知らぬ存ぜぬで通せと、いつも通りの口調である。そのつもりですよ、と内心で思いながら返事をした記憶は新しい。そんな事を考えながらぼんやりと歩いていたせいか、前から来た人に思いきりぶつかった。段ボールが宙を舞い、しりもちをつく。じんわりとお尻から痛みが伝わってくる。あいたたた、と自分の腰に手を当てる。 「す、すみません。前が見えなくて」 謝る癖がついているせいか、いたいと口から出るよりもはやく謝礼の言葉が出てきた。自分の右手でお尻をさすりながら段ボールを避けて立ち上がろうとする。が腰が抜けているらしく立ち上がれない。相手の大丈夫ですか、と聞き覚えのある声に目の前にあるすらりとした足をたどって視線をうえに向ければそこにいたのは誰かと間違えるはずもないイケメンヒーローのバーナビー・ブルックス・Jrであった。なんということだ。驚いて「お怪我はありませんか」と言ってしまったが、逆に怪我をしているのは貴方じゃないですか、みたいな目線を向けられてぎくりとする。平常心、平常心と自分を落ち着かせる。 「大丈夫ですか?」 「え、ええ、大丈夫です」そうだ、不自然じゃない。全然不自然じゃない、と自分に言い聞かせながら対応する。しかし腰が抜けているので立ち上がる事が出来ない。しどろもどろになりながら、「ほんとうに大丈夫ですか?」というバーナビーの言葉に答える。「あの、……やっぱり、いえ、ちょっと腰が抜けたみたいです」 「……やっぱり大丈夫じゃないじゃないですか」 「す、すみません。手を貸していただけますか?」 問いかければ、バーナビーはにこやかな営業スマイルを張り付けてすっと手を差し出した。いたた、と腰をさすりながら私は立ち上がる。ぷるぷると足が震えて、まるで生まれたてのこじかみたいだと思ったらなんだか悲しくなった。私も貧弱になったものだとがっかりする。相手に「ありがとう」と笑いかければ、少しだけ距離の近くなったバーナビーの眉間にしわが寄った。あれ、おかしいなと思ったのもつかの間。彼の口から発せられた言葉に私の全身が凍りつく。 「えっ? すいませんもう一度……」 「あの、さんですよね」 「違います」自分の中の何かが警鐘を鳴らすが、ここは知らぬ存ぜぬで通すのがセオリーだ。 「目が泳いでますよ」 「そんな訳ないじゃないですか」 ぽん、と肩をがっちりと両手でホールド。目の前にバーナビーという女性においしい状況に置かれて私の頬に冷や汗が流れる。奇跡的にばれていなかったとかそんなフラグはいらなかった。バレている。言い訳を言っている余裕もなく、なぜ彼が私の名前を知っているのか問いただす余裕もなく、薄化粧の私はまっすぐすぎる彼の目線を受け止められずにいた。こんなイケメンを真正面から見たら流されると知っていたから。 「僕の方を見てちゃんとそれが言えますか? ねぇ、さん」 「うっ、私はでは……」 カッコよすぎて何か出そうだ。イケメンに名前を呼ばれただけでも倒れそうなのに、正体をばらしてはいけないと言う上司との規約があるばかりに私はそれを否定しなければいけない使命がある。だ、だめだ頷いてはだめだ。私はごくりと固唾を飲む。こんなカッコ悪い所でばれるなんて私の失態だ。どうしよう、首が飛びかねない。 「そうですよね」バーナビーという男は諦めの悪い男であった。私がその言葉に彼の顔を見てぱあっと顔を輝かせそうになったのもつかの間。「僕が貴方を間違えると思っていますか?」と、間髪入れずにぐいっと距離を詰められた。顔が近い。もう少しでキスでも余裕でできるんじゃないかというくらいに近い。心臓の音が彼に聞こえてしまうんじゃないかとか、匂わないかとか、そんな簡素な事しか思えないくらいに私は動揺していた。バーナビーの香水の香りがふわりと香る。どんな香水をつけているのだろうか、きっと有名なバーナビーのことなのだから身だしなみも気を使って高そうなものをつけているに違いないと私は踏んでいる。 「えっと、そ、そういう訳でも」 「さんなんですよね」 「いや、それは違って……」 「どうなんですか」 しどろもどろになってもう少しで折れかかっているところだった。私が少し彼から視線を逸らす。恐らく彼は最初はカマをかけただけだったのだろうが、私がいかにもな反応をしてしまったので確信を得てしまったのかもしれない。けれども 「あ、ちゃん丁度良かった」 馬鹿野郎うううう! と叫ばずにはいられないバッドタイミングでスタッフが駆け寄ってくる。「これこれ」と渡してきたのは映画のチケット。「お取込み中悪いけどさ、さっき差し入れで女優さんにたくさん貰ってね。僕達で分けて余ったから、君に差し入れだよ。じゃあね!」 その背中をぼんやりと追いかけながら、私は盛大なため息を吐いた。 「やっぱり、あなたでしたか」 「ぜーったい内密にしてください!」 「さぁ、どうしましょうね」 ぞわりと背筋が寒くなって、なんだか蛇に睨まれた蛙のような気持ちになった。 (20110822:素材)(20110920) もう九月も終わりに近づいててやぁねぇ、 |