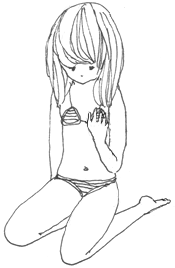 「嫌です嫌です!」 「そんなこと言わないで、はいはい大丈夫きみならできるから」 「ほおおお、ロイズさん無茶な事言わないでください!」 「上司の命令に逆らうつもりかね、君は」 ぐ、と目頭にたまりつつある涙を流してしまわないように堪える。ロイズさんはさも楽しげに仕事の話を進めた。私がいかにメディアに出たくないかと論じても軽く受け流され、ヒーローでもないのに広告に載るという無茶な仕事を勝手に引き受けてしまった彼は鼻歌を歌いかねない勢いだった。いくら報酬がはずむとはいえ、報酬よりも私は身の保身を考える。 「あ、そうだそれってロイズさんパワハラですよ!」 「ん? 何か言ったかね、最近年のせいか耳が遠くなっていてね……ではここに詳細は書いてあるから目を通しておくように、いいね?」 その有無を言わせない瞳に私はもはや頷くことしかできず、それを見た彼はまたにこやかな営業スマイルに戻る。私はひきつる顔を必死に普通の表情にしようと懸命に努力するが、ロイズさんはそんなことお構いなしに次の会議へといそいそと出かけていく。やはり上司には逆らえないのだろうか、私はため息をつきながら書類へと目を落とした。 控室にいると、同僚が水着の大量に入っていそうな衣装ケースをもって入ってくる。本当にやるのか、と思いながらも私は上司命令だしなあとぐっとこらえる。「じゃあこれ」と差し出される水着を見れば、コルセットのような作りのセパレートタイプのもので前が編上げの紐止めになっており横の部分の布はほとんど無く後ろの生地とは五センチほどの紐で繋がれている。どうやら後ろでコルセットのように締め上げるタイプのものらしい。下はガターベルトのようなセクシーな下着のような造形になっている。肝心な部分は隠れるもののこんな下着のようなマニアックな水着を着て世間に出ると考えればもうお嫁になんていけない、そう思ってため息をつく。 「それにしてもどっからこんなの仕入れたのかしら」 同僚が首をかしげながらリオのカーニバルで使用されているような布面積の少ない水着を衣装ケースから取り出し顔を顰める。それは絶対に着ない、という必死な視線を送れば、同僚はそりゃ要相談だわ、と苦笑した。 「ねえ、こんな水着初めて見たから着方が分からないんだけど」 「コルセットくらい着方分かるでしょ、はい、全部脱いで―」 きゃあきゃあと騒ぎながらコルセット風の水着を同僚と共に装着していく。「胸のとこおさえときなさいよー」と言う同僚の言葉に、私は必死に頷いた。もうここまできたらどうにでもなればいい、と開き直ることにする。ぎゅうぎゅうと器用にコルセットを絞めていく同僚に私は感動せざるをえなかった。こんな技術どこで覚えたんだろうか。 「終わったわよ」 その言葉に鏡を見れば、実際に見た時よりも際どい姿の自分の姿。 「こ、こんなので撮るの!? っていうか社の宣伝ならタイガーとバーナビーがいるのに!」涙目になりながら同僚を見れば、彼女はあー、と言葉を濁した。「多分それは男性人気も取ろうと」「私みたいな可愛くない子じゃ人気なんて取れないって、下がるって、なんでも露出すればいいってわけじゃないんだって!」もう、と怒れば彼女は分かってないなあと首を振った。「まあいいけどさっさと下も着替えてね、あれならあっち向いてるし」 冷たくあしらう同僚の言葉に涙を飲みながら、私は着替えを進めた。 『どうして、ねえどうしているの!』 小声で同僚に怒るが、「さあねぇ」と軽くかわされる。さては知っていたのだろうか、彼女はふんふんと鼻歌を歌う。着替えた後にメイクをメイクさんに行ってもらい、ウィッグをかぶらされヘアメイクをされ、あれよあれよとお人形のようにされた私はお人形よろしくロングジャケットに身を包んでいた。私の指差す先には、今人気急上昇の話題沸騰ヒーローであるわが社の広告塔バーナビーとワイルドタイガーの二人である。バーナビーはピシッとしたスーツ姿だが少しだけ乱れたようなシャツを着ており、緩めたネクタイをつけている。まあワイルドタイガーもおなじみのマスクをつけて似たような服装をしているのだが、まさか同じ撮影ではないだろうと背中を嫌な汗が流れた。彼らと話していたロイズさんがばっとこちらを振り返る。 「遅かったじゃないか!」 にこやかにほほ笑むロイズさんに、私は今世紀最大の恐怖を覚えた。終わった、と脳内が告げる。「すみません」とひきつりそうになる笑顔を無理やり作る。同僚は隣でびしっとスーツなんて決めて秘書気取りか、と悪態をつきたくなる。彼女が「本日はよろしくお願いいたします」と口を開いて一礼するものだから一発殴りたい衝動に駆られたが、そんなことしたら後が怖かった。 「彼女がそうですか」 「ああそうだよ、今日はわが社の宣伝としてよろしく頼む!」 はっはっは、と笑いだしそうな勢いでロイズさんはとてもにこやかに笑った。 「まっ、こちらこそ宜しくな!」 ぞわぁ、と緊張と有名人を前にした焦りのあまり鳥肌がたつ。差し出された手を握って「こ、こちらこそ宜しくお願いします」と頭を下げると「そんなガッチガチで大丈夫か?」と心配されてしまった。ワイルドタイガーは緊張とは無縁そうだな、と失礼な事を考えていると、横からロイズさんが「この子、撮影は初めてでね。紹介するよ、だ」なんてにこやかな対応。私は先が思いやられる思いでいっぱいだったが、私と撮影を共にする二人は余裕の表情をしていた。さすがヒーローとしてメディアに広く取り上げられているだけはあるな、としみじみと感じる。もともと住む世界が違う人間のはずなのに、どうしてこうなったのか私には理解が及ばなかった。ロイズさんを私はきっと一生許さない。こんな恥ずかしい恰好で撮るなんてきっと一生の恥さらしになるに違いない。ぎゅっと手を握れば、何か掴んだような違和感。はっと気づけば私はワイルドタイガーの手を握ったままだった。はずかしくなって、ぱっと手を離す。 「すすすすいません!」 「ん? あ、ああ俺は全然大丈夫だよ?」 ぺこぺこと頭を下げているとはぁ、と私ではないため息がこぼれる。恐らくバーナビーさんだろうと彼をみれば、呆れ半分そして営業用の笑顔が半分張り付いていた。もはや弁解の余地もない、と思っていたところの「スタンバイお願いします!」と言う声。やれやれと言ったように「よろしくお願いしますね」とさわやかに笑うバーナビーさんに不覚にもどきりとする。綺麗すぎる彼のとなりに私のような者がいて申し訳ありませんと言う気持ちでいっぱいである。人気獲得どころかファンに殺されかねない勢いである。果たして大丈夫なのだろうかという不安を胸に撮影が開始される。 「あ、それ脱いできて!」 「え、もう脱ぐんですか!」 「邪魔でしょ、早く早く」 撮影スタッフに止められて、もじもじとしながら私はジッパーを下げる。 「ええええええええええええ! バニーこれ何の撮影だよ!」 「社のイメージアップ広告としか聞いていませんが」 私が一番疑問です、と言いたい気持ちをぐっとこらえて、同僚に投げるように渡す。恥ずかしくて顔から火が出そうだった。 「はいがんばれー」「くそう、他人事みたいに言いやがって後で見てろよくそう!」「あんたにそれが出来ればなんかおごってやるから、はいがんばれー」「が、がんばる!」現金な奴め、と思ったように同僚が顔を顰めるが、私は「お願いします!」と撮影スタッフに一礼する。すうすうとする足はピンヒールの編上げのブーツを履かされている。水着(と言えるのか怪しい)と同じ色の白で統一されており、そういえばウィッグも白銀色をしていた。セットをよくみればあれ、ベッドとかおかしくないか、なんて疑問がふつふつとわき上がってくる。疑問符ばかりで頭のなかがぐるぐるしてきた私にスタッフが、はいベッドの真ん中、あそうそうそのへんにすわっててーと的確な指示を近くにきて出す。バーナビーさんとワイルドタイガーがちょっと近すぎるくらいの距離にいてなんだかぞわりとする。もうすでに密着に近い状態なのにもかかわらずカメラマンが無茶な要望。「ハイ二人とも腕を彼女の腰のあたりに回して―」 「「え」」 戸惑うワイルドタイガーと私をよそに、バーナビーさんただ一人が私の腰に手を回す。私の顔が引きつるけれども彼は涼しげにしていた。さすがイケメンだった。何をしても似合った。「タイガーさんはやく」とカメラマンさんが言うのに、ワイルドタイガーは「すまんな」なんて言いながらバーナビーさんとは逆の腰に手を回す。これだけで終わるかと思いきや終わらなかった。 もはやいったい何の撮影だ、と突っ込みたくなる衝動に駆られるがもう我慢するしかない。向こうで笑いをこらえている同僚には高級イタリアンを奢らせることを決めて、私は言われた通りのポーズをとる。 「はいはい、いいかんじねー。それで足組んで」 ようやく構図が決まったらしい。「はい首かしげてー」なんて言葉に私とワイルドタイガーが同時に首をかしげて、「タイガーさんじゃないよー」と注意を受ける。「色っぽい目線お願いしまーす」とか無茶なお願いをどうしようかと考えながら、カメラを睨む。とりあえずカメラ目線なら大丈夫なんじゃないのか。何度かの取り直しと、カメラマンの野次の末にようやく終わったと思った撮影はまだ続く。 「ポーズ変えていきまーす」 と同時にタイガーさん休憩でーすと言う声。妙な緊張感の中で、私とバーナビーさんだけが残された。 「ハイじゃあ押し倒して―」 何の撮影だかわからなくて頭が真っ白になる私をバーナビーさんが押し倒す。はっとする私に「仕事ですよ、あなたもアイドルならアイドルとして自覚を持ったらどうです」なんて耳元に口を寄せて囁く。パシャパシャ、とフラッシュ。ぱちくりと目を瞬く私は思わず「私アイドルなんかじゃ……」と口走ってはっとする。バーナビーさんが眉をしかめたのだ。多分上司に話を合わせないと後々まずいと思いながら「あ、そのまだなったばっかりで実感がわかないので」と言葉を紡ぐ。「視線が泳いでますよ」 その後の撮影はいろいろと気が気ではなくてよく覚えてはいないが、タイガーさんの膝に向かい合って乗ったり、ほんとにこれは必要なのか分からない写真が多く取られた。社のイメージアップ広告と言うよりなんだかいかがわしい雑誌の撮影みたいで妙な気分だ。 「ちょ、あの! ロイズさん! ど、どこにつかうんですかこんなのっ!」 「ほら、うちとちょっと有名な下着メーカーが協賛して作った下着の宣伝に。ほら、先日うちのメカニックが必死に書類をまとめていただろう? 君もそうしていれば別人のように綺麗だからね。宣伝には変わりないから嘘はついていないだろう?」 「えっ、ていうか水着じゃないんですか?」 「君がそういう性格で助かったよ、また頼むからね! この分のギャラはちゃんとつくから安心したまえ!」 「えっ、ロイズさああん! そりゃないですよおおおお!」 (20110822:素材)実はヒロインを脱がせたかっただけのおはなしでした\(^o^)/ナンテコッタ |