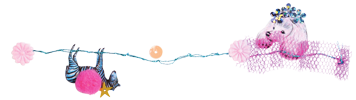 世界をふらふらとしていた獅郎がようやく安定を求めて日本に住み着いたのはそれからしばらく経ってからで、私は何だか嫉妬心に駆られていたような気がする。私自身から何だか遠ざかって行ってしまうような獅郎を、もどかしい気持ちで見ながら追いかける事の出来ない意気地なしの私を私は苦虫をかみつぶしたような表情で見ていた。彼は何も教えてはくれない。のらりくらりと、私に汚いものを見せないように努めてくれているのかもしれない。その優しさが時に残酷な事を彼は知らないから、私の事をそうやって気遣ってくれているのだろう。くすくすと笑いがこみ上げてくる。なんてお人好しなのだろうか、本当に人間は分からない。でもそこが好きだ。 もしかしたら獅郎は優しいという思い込み自体が錯覚なのかもしれない恐怖が、私を浸食していることもまた彼は知らないのだろう。もしくは知っていたところで見なかったふりをしているだけなのかもしれないのだけれど、そんな些細なものから徐々に失う恐怖が芽生えだす。いっそ失くしてしまったら気が楽なのだろうか。その方が何も気に病む必要もないのかもしれない。けれども恐らく私の中で失いたくないくらい、彼の存在は大きくなっていた。どうしようもないくらいに、焦がれているから、だからそんな簡単に失えるものではない。私は頭をぶんぶんと横に振って、妙な考えを振り払った。 こんな事しか考えられなくなっているなんて、本当に末期だった。 今から失う事しか考えられないなんて、本当に馬鹿としか言いようがない。 今日も獅郎は任務らしい。何故か私の大好きなマタタビ酒を持って出て行ったけれども用途は分からない。私はぶらぶらと日本を散策に出かけていた。家に引きこもっているのも少し飽きてきたところだったし、他の国の様子もちらちらと見ておきたかったというのもある。知識としてのみの日本が頭に存在していたのにもかかわらず自由に行動することが許されておらず、行動制限を受けていたころの私は本当に惨めだった。でも今は違う。こうしていろいろな文化に触れあう事ができるのだ。少しだけ、頬がほころんだ。ふわふわとした空気が気持ちいい。先程パン屋に寄ってパリジャンを二斤買った。ぱりぱりとした食感がたまらなくおいしくて、このお店にはいつもお世話になっている。紙袋を抱きしめながらこんなにおいしいものが物質界にあるなんて幸せだなぁ、としみじみと感じた。 「こんなところで何してるんです?」 「あらフェレス卿、久しぶり」 ぼんやりと歩いていたせいか、ちょこちょこと足元に犬の姿のフェレス卿がいたことに気が付かなかった。できるだけ平静を装って、ちらりと彼を見てまた前へと視線を戻す。イマイチだらしのない表情を彼に見られていたと思うと何だか自分が情けない気持ちになってくる。にしてもこの男、どこから現れたのだろうか。いつも不思議に思うけれども、神出鬼没も甚だしく私は非常に不快だ。先ほどのふわふわした空気も一瞬にして氷点下へと冷え切っていた。 「今日も全くつれない態度ですね」 「あなたを釣る気はまったくないのよ」 「これはこれは失礼いたしました☆ ふふふ、いつデレ期がくるのか楽しみですねぇ」 「デレキ? それはエレキギターの親戚か何かかしら?」 「おやおや、私の独り言ですよ。気にしないでください」 やはり非常に不快だった。私はもやもやとする気持ちを頭の中から振り払う。フェレス卿がいると、どうも彼にペースを持って行かれてしまう。自分自身が見えなくなる。挙句、彼の掌の上で転がされている駒として扱われているのだ。そういうのはもうご免だと言ったところで私の立場が劇的に変化するわけでもなければ、彼の掌の上から逃れられるわけでもない。フェレス卿と関わった時点で彼は持ち駒として誰でも利用するものだから、彼に流されないように精一杯抗うしかない。しかしフェレス卿なんて奴はとんでもなく性質が悪いのだ。付き合いが長ければ長いほど、これはひしひしと伝わってきた。さすが悪魔の子である。 フェレス卿がニヤリとする。これは何か企んでいるときの顔だ。 「ところで」 「だが断る!」 「まだ何も言ってませんよ!」 「フェレス卿の言う事は滅茶苦茶だから絶対に聞かないわ、頼みごとなら他をあたってよ!」 「まあまあまだ何も話していませんから、落ち着いて聞いてくださいよ……ね?」 首を横に振った私は少し早足になる。フェレス卿がちょこちょこと足元をついてくるが所詮小動物、私の方が足の長さ的にリーチが長い分距離を引き離せる。小動物にしか化けられないのが運の尽きだったのだろう。私はまだちょこちょことついてくるフェレス卿を見下ろしてため息をつく。まだついてくる気か、と私がため息をつけば、彼はまだ話が終わってないと憤慨したように言った。 バチカン近辺をふらふらとしていた時は何度となくこんな事があった気がする。獅郎もいて、シュラちゃんもいて、それからフェレス卿が面倒事を持ってきて。本当に騒がしい毎日だったけれど、一番私の中で輝いているのは獅郎と過ごした思い出。今もそれは継続中だけれど、前の主人の事もその前の主人の事も今ではもううっすらとしか覚えていないくらいに今私の中で獅郎の存在は大きいものに変化してしまっていた。 ぱたりと足を止める。 フェレス卿が息を切らして、私の横に並んだ。まだついてきていたのか、という視線を向ければ彼は酷い人ですね。と悪態をついた。私は「貴方ほどではないけれどね」と悪態を返して、また歩を進める。だめだ、と思ってもあふれてくる感情。幸せと隣り合わせに潜んでいる『不幸』と言う名の魔物の存在を一瞬感じてぞわりとした。全身の毛穴が冷え切って、頭に合ったものすべてがどこかに吸収されていくような感覚。一瞬にして押し寄せて、一瞬にして去っていく。かけがえのない幸せで満ち足りた思いも、この一瞬の衝動的な何かにすべて吸収されていく無力感。これは何なのかわからないけれども、恐らく不安なのだろう。 「どうかしましたか?」 「いいえ何も」 「嘘はすぐにばれますよ」 「貴方にばれる程度の嘘はつかないから安心して」 「本当にあなたは、」 フェレス卿は何か言葉をつなげようとして、ため息をついた。私はクスクスと笑う。 獅郎を失ってしまったらどうすればいいのか、私には未だ答えが出せずにいる。 失ってしまってからの事を考えるよりも今を精一杯楽しむ方が まだ先決だった あの日。  (20110814:titleソザイ |