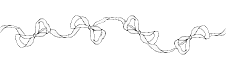
|
※落ち込むエルエルフに一瞬喝をいれるだけのはなし。 完璧であった。まだ腕はなまってないな、とわたしは鏡を見ながら身なりを整え、虚構の彼女に成りすました。服の調達なんていくらでも宛てはあったのだ、クリムヒルトに頼んで彼女の服を持ってきてもらい、そしてわたしの変装技術を駆使した今の姿は、完璧に見てくれは彼女である。そう、リーゼロッテそのものだ。 はぁ、とため息をついた。 愛した人を失った悲しさは、知っている。わたしだって、と奥歯をかみしめ、鏡を殴りそうになって思いとどまった。この姿で、こんなことするのは少し気が引けた。だがしかしこんなところで手をこまねいているわけにもいかないのだ。彼には早急に立ち直ってもらわなければ、そうでなければこの戦況は不利になるばかりだ。わたしは意を決してエルエルフのひきこもる部屋に向かう。考えながら向かっていたせいか、わたしは自分の姿のことを一瞬ばかり忘れていた。これはわたしの失策だ。 「き、君は!」 「しっ! 時縞ハルト、黙って」 「えっ、君は、でも、どうして」と、取り乱す彼にわたしはため息をつく。 「落ち着いて、時縞ハルト」とわたしが声をかければ彼は一応黙る形でわたしの話に耳を傾ける。「わたし、リーゼロッテじゃないわ。こんなのただの変装よ。このままエルエルフがあんな風になっていることこの国にとってはマイナスだわ。起爆剤が必要なのよ、だからちょっとこの姿を借りるだけ。悪いように使うわけじゃない、アイツのためなんかじゃない、不利な状況からいかに立て直すかを考えるのが今のわたしにとって最善。改善するにはアイツの力は必須なの、だから誰かが救ってやらなきゃいけない……なんて所詮わたしのエゴだけどね。うまくいくかなんてわからない、でもわたしにできるのはこれくらいだから」 愛した人を失うつらさは、わたしも分かってるから。幻想でもいい、わたしは会いたいからさ。 そう言って笑えばハルトも笑った。「……シャル。ホントにスパイみたいだ。でも、あのエルエルフだ。アイツのことだしすぐ気づくんじゃ…」 「いいえ、わたしただのスパイなのよ」それに、とわたしは続ける。「これは、騙される騙されないの問題じゃない。今の彼はもうすでに、彼女に会いたいって欲望のが勝ってるからさ。会いに行ってあげなくちゃ」 時縞ハルトと別れ、エルエルフのいる部屋の前へとやってきた。彼に場所を聞いたら教えてくれたものの、いざ入るとなると緊張してくるのも確かだ。あんなことを言ったものの所詮は虚勢にすぎなかった。それでも、強がらなきゃいけない時はあるのだ。かちゃり、と意を消してドアを開ける。ドアの音にも反応しない。誰だ、と声が飛んでくることもない。今なら簡単に死んでしまいそうな、小さな背中。本当にこれがエルエルフなのだろうかと疑いたくなるような、その人物に、わたしは後ろから手を伸ばして抱きしめていた。 「いつまでそうしているのですか、ミハエル」 声色を真似してはいるが、彼女の声などほとんど聞いたことなどない。ヴァルヴレイヴに残っていた音声データをもとに複製しているだけにすぎない。それでも彼にとっては、わたし、いや、彼女の存在はイレギュラーであったらしい。誰だ、とようやくそこで振り返る彼はわたしの姿をみて眼を丸くした。 「どうして、……っ……リーゼロッテ、生きて……」 かすれた声、まるで生気のない隈のできた目元に目をそむけたくなる。でもわたしの仕事はまだ始まったばかりなのだ、遂行しなければ。わたしは平静を装い、彼女のように笑った。 「リーゼロッテ、……もう、会えないかと思っていた……」 わたしの姿を愛しそうに見て、力のない笑みを浮かべ、そしてその胸の中に抱き留められる。残酷だ、わたしは。こうしてここに来たのは軽い気持ちではなかった、それでも彼の傷を抉っているのは確かだ。再起不能なまでに落ち込む彼をわたしはさらに追い詰めているのだ。それでも、やらなければならない。彼は知っているはずだ、知っていて尚幻想に縋り付こうともがき続けている。 「わたしは、また会えると思っていました。あなたには伝えなければならないことが、あったから」 「…愛してる、リーゼロッテ。君が生きてここにいることが、俺の救いだ。君を助けられなかったらどうしようかと思っていた。あの時からずっと考えていた、絶対に助からなかったと思っていた、それでも俺の前に、確かに存在している……今度こそ、俺は成功したよ、リーゼロッテ……」 愛してる、とささやく彼にわたしはまだ残酷な言葉をかけられないまま、少しだけ彼女のままで彼の背中に腕を回した。 |