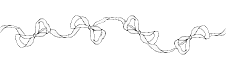
|
※ハーノに襲われるだけ|ハーノにもいい思いをさせてやってもいいぜ、っていう上から目線 「げ、」 油断したわたしが悪かった。潜入したハーノインらのことを失念していたわけではない。ただ指南ショーコの安全確認のために出てきたのはいいもののイレギュラーな6号機に先を越され、そのうえ彼に見つかった。それだけならまだ良かったのである。見つかったわたしは目の前の光景に目を奪われていたあまり、周囲の状況確認が疎かになっていた。原因はわたしにある。そして敗因もわたしのせいだ。わたしは自分のふがいなさにため息をついた。運悪く見つかって取り押さえられたわたしは、彼らに両手足を拘束され、口には猿ぐつわ。こんなのすぐに抜け出せる。でも相手が相手なのだ、油断はできない。 船内の一室にわたしは閉じ込められていた。目の前には先の元凶ハーノインがいる。彼ただ一人だが油断はできない。カルルスタイン卒業、ということはわたしと同等それ以上の実力があるといって間違いないのである。そのうえ男女の体格差を考えれば優劣などわかりきったことだ。さらにわたしは頭脳派、見たところ彼は脳筋である。 「なぁ、ファウツヴァイちゃーん。向こうに行って何の連絡もなかった間、君はナニしてたの?」 「…別にわざと連絡をしなかったわけじゃない。ちょっと色々あっただけ、端末も不良品だったし連絡を取ろうにも取れなかった。これでいいかしら」 「そんなの、俺が信用するとでも?」 「知ってる。でもわたしの端末を見ればそんな事はすぐにわかるはずよ。ねぇ、それより、知ってるんでしょ。大佐のこと、」 見たんでしょ、と言えばハーノインの目がす、と細くなる。鋭い目つきだ。きっとなにか掴んでいる、彼も。 「教えてあげる、かわりにわたしの自由を約束しなさい。口裏を合わせるのなんてお得意なんでしょ? サボり魔のハーノインさん」 「俺相手に交渉なんて、ファウツヴァイちゃんも隅におけないねぇ」 「伊達に諜報はしてないわ、情報は有益な取引の条件になり得るものよ。時には命よりも重い」 わたしは袖口のナイフで腕の縄を切った後、そのまま足の縄も切断する。椅子から立ち上がり手首を動かせばこきりと骨が鳴った。「チョロい縄ね、まるで抜け出せと言ってるみたい。わたしにこんな紐が通用するとでも思った?」 「おっとぉ、お姫様はまだこの部屋で監禁中だ」 しかし縄を切断したところで、すかさずハーノインに抑え込まれ床に押し倒される。ここまではわたしの計算通りだ。 「前払いなんてわたしの趣味じゃないわ、後払いじゃだめかしら」 「ダーメ、わがままなお姫様にはオシオキしてあげなくっちゃ」 「……この色ボケ男」ハーノインから唇を落とされて、わたしは気づく。忘れてた、コイツはこういう奴だ。そう、まるでわたしの仲間と同じだ。これがイクスアインあたりであればうまくいったかもしれない。あいつは真面目だ。こういう義理堅いのはこいつには通じないらしい、仕掛けた相手が不味かったのか。全く、情報不足はなはだしい。失策だった。任務なら、死んでた。 「なんとでもどうぞ」 それじゃ、いただくとしますかね。彼はそう言うとわたしの制服を脱がしにかかる。ボタンが一つ二つと外されていき、下着が上に押し上げられる。「へぇ、意外といい身体」 つう、と彼の冷たい手のひらが腹から上へ這ってくる。ぞわりと身の毛がよだち、「ひ、」と小さく声を漏らせば彼はかわいい声だせるじゃん、とニヤリと笑う。 「声なんて我慢しなくていいんだぜ、ファウツちゃん。ここは完全防音なんだしぃ?」 「別に我慢してるわけじゃ、」 う、と呻くわたしの両足の間にハーノインが身体をねじこみ、タイツがショーツごとびり、と音を立ててナイフで裂かれる。と思えば、次の瞬間頭の横にナイフが突き刺さり、一瞬そちらに気を取られたわたしの唇に、また彼の唇が重なった。今度は深く絡み合うような、息が詰まるくらい深いキス。わたしが窒息しかけるかしないかという何分かのあと、彼は唇を話すと、口から伝う銀糸をぬぐってニヒルな笑みを浮かべた。 「ちょーっと痛いかもしれないけど、まあ我慢してくれよ。お姫様」 「ま、待って、……うぁ、!」 深いキスが降ってくる。胸を弄ばれ、ずるずると下半身に熱が浸食してくる。徐々に快楽に流される、身体が熱く火照る。まるで獣のようだ、と思った。本能のままに欲望を吐き出す。まるで人間とはかけ離れたかのような激しい動きにわたしはただ翻弄されるだけで、そのまま何度も何度も彼の欲望が胎内に吐き出されていくのを(契約だから)とこれといった抵抗もせずに彼を赦してしまったのは、おそらくわたしもそういう彼にながされていただけなのかもしれない。およそ何度目かわからなくなってきた欲を受け止めたとき、彼ははぁ、とため息をついて口を開いた。 「なんで、息の一つも、切れてないかな。この、生意気な、お嬢さんは」 いつの間にか鍛え上げられた上半身を露わにした彼は、肩で息をしながらわたしの頬を撫でた。わたしはそれがなぜか心地よくて目を細める。 「だって仮にもわたし、軍人だもの。このくらいで息が切れるような生半可な訓練なんて受けてないわ」 そう言えば彼は少し驚いたような表情の後少し笑って、もう一回ヤッとく?と悪戯気に笑った。夜はまだ長いらしい。 |