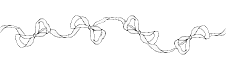
|
へぇ、と感嘆の声をあげるファウツヴァイを確かにこいつはすごい奴だと思った。的確な判断力、適切な対応。俺に対しての信頼関係、その他エトセトラエトセトラ。挙げればきりはないが、こんなに使えるビジネスパートナーはここにはこいつくらいしかいない。まだこの新生ジオールは、肉弾戦になればてんで弱い。ヴァルヴレイヴでもっているようなものなのだ。 「あっ、そういや忘れてた」 そういやアードライがエルエルフに会ったら何故裏切ったか理由を聞けって言ってたわ、と彼女はヴァルヴレイヴを傍目にカツサンドを頬張る。「アードライはさ、エルエルフのこと最後まで信じてたよ」 「今更なにを言い出したかと思えば」 「わたしも、あなたのこと割と信じてる」 ヴァルヴレイヴってさ、わたしたちには乗れないのね。もどかしいわ。と彼女はあくびをして立ち上がった。 「別に今更理由を問いただそうとかそういうんじゃないわ。あなた合理主義でできることにしか手を出さない、お堅い奴だと思ってたけど。あっイクスとは別のお堅さね」 「何が言いたい」 「あー、なんていうかみんな元気してるかなって思っただけ。わたしの元いた部隊も気になるし」 「ホームシックか」 「そんなとこ。元いたとこはさ、みんな男あさりして情報漁ってた連中ばっかだったからみんな戦闘力も頭の良さもわたしより悪かったんだけど、ドルシアでも有名な美女ぞろいだったなぁなんて。でも、わたしの部隊もとうとう頭のない身体に、なっちゃったかな」 「どういうことだ」 「脳筋」 「…適切な表現だ」 わたしが思い浮かべた彼女らが、エルエルフも思い浮かんだらしい。色仕掛けをいつも仕掛けられていた彼は結局誰にもなびかなかった。そりゃそうだ、可愛らしい彼女が待ってるんだもの。 「あいつらなんだかんだわたしのこと好きだからさ、拗らせて病んでないといいんだけど。わたしがこちら側についたとなれば、恐らく3人全員寝返っちゃったりして……ふふ。なーんて、ね」 冗談よ、とわたしは笑う。 「つまりは、ドルシアにスパイとして彼女らを置けると」 「だから冗談だってば、確信は持てないもの。ただ一つだけ言えるのは彼女たちはわたしに盲信的に忠実よ。死ねと言えばおそらく死ぬわ。ただし全てはドルシアの犬だったころの話だけどね」 |