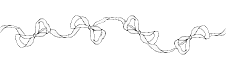
|
(※痛みにまけるな!) ファウツヴァイ、とわたしを呼ぶ声がしていた。生きている感覚はしているが痛覚がまだ戻らない。いや、むしろ戻らなくてよかったのかもしれない。ぬちゃぬちゃとわたしの秘所に挿入されているそれはかなり凶器であった。それでいて、狂気のかたまりでもあった。愛してる、ファウツヴァイ、愛してる。と繰り返す言葉が事務的で、そしてゆれる腰にいよいよ鈍痛が戻りつつある。 わたしの上で必死になってその銀髪をゆらし、服を乱し、呼吸を荒くする。未だかつて、こんな必死なアードライを見たことがあっただろうか。……わたしは無い。初めて見た男の顔に、鈍痛がひどくなる。 ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ、ファウツヴァイ… …愛してる、 「いい、加減に……私のものになると、いう、気は無いのか」 「どうして、こんなこと」 「どうして、受け入れてくれない…」 「……ッあぁ!」思わず声が漏れる。「………その、名前はもう…」 「君の名前を呼んで何が悪い…愛してる、……愛してるんだ…」 アードライは愛してる、とまるでうわごとのようにつぶやきながらわたしに覆いかぶさるように抱きついた。 |