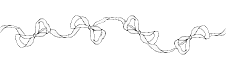
|
(地に落ちたイカロスの続編|別館リクエスト) さて、クリスマスである。 イエスキリストの生誕祭であるが、キリスト教徒ではないわたしたち日本人の無神論者がなぜわいわいと祝っているのか甚だ疑問であった。聖書も読んだことのない人々、キリストの誕生日とすらわかっていない人々、とりあえず乗っかって騒ぐ人々。誕生日だし騒々しいくらいがいいのかもしれないけれど、とりあえずワイワイ騒いじゃう?サンタもいるし、っていう安易な考えが見え隠れしている。道行くイルミネーションが目に痛い。隣を歩くナイス君が、なぜか恋人つなぎをしているのは、少し気になる。色んな意味で。 さて、近日ナイス君が異常にわたしに執着している理由について。 推論に過ぎない未だ仮説である点をいくつかあげるとするならば、彼の責任感もしくは倫理観、いやむしろ人間的な感情の一部欠如からなるなにかしらの隙間に、依頼人であるわたしというイレギュラーが何らかの理由で介入してしまったという点があげられるのではないだろうか。ナイス君に対して、嫌いとか好きとか、よくわからない。でも興味をそそられている存在であるのも確かであった。 学校帰りにナイス君が校門の前で待ち伏せていて(このあたり、彼はいつも通りだ。いろいろあってから、彼はよく校門で待っている。依頼はいいのか、と聞けば済ませたと返事があった。)、うっかりノーウェアまでついてきてしまい、いつも通りわたしはミルクティを注文して砂糖を4つその中に放り込む。このあたりも彼の策略の中なのだろうか。わたしはくるくるとティースプーンを回しながら、少し熱すぎる紅茶のカップを手に取り手の中で暖をとる。冬の寒さにはやさしいあたたかさである。それにしても、である。 「不思議ね。まるで人に興味ないってくらい人に執着することのないあなたがわたしに対して入れ込んでいるなんて。あなたってもっと他人に対して淡泊なのかと思っていたわ。案外、情があるものなのね。意外だわ」 「まーたお前は難しいこと考えてんの? いーじゃん俺が勝手にやってるだけなんだし」 紅茶を一口すすればまだ熱かった。少し火傷した舌を出しながらハンカチで口を拭う。 「いいえ、通常の考察を繰り返していただけ。そうね、強いて言うなら人間観察かしら。ねえナイス君。わたしの護衛をいくら繰り返そうと今依頼料はでないわ。それを考えて、あなたがどうして…いえ、やめておくわ。……あなた変わっているわ、とっても。まあ今まで出会った人も随分と変な趣向の人ばかりであったけれどね」 「さぁ、俺が損得で動いてると思ってんの?」 「いいえ、そうであれば今頃お金に困ってはいないでしょうね」 「ハハ、相変わらず手厳しーな」 「あなたほど手厳しくはないつもりよ、ナイス君」こつん、と彼の額を人差し指で小突けば彼はへらりと笑った。 「知ってる」 「そんで何? さ、最近変わったことはねーの」 「…………いいえ、ないわ」 「…なんだよ、そのちょっとした間! また俺に言えないことでもあんのかよッ…! あーもうホント女子ってこれだからなー。お前の行動からして、なんか隠してんのは確かなんだけど」 「女の子には隠し事の一つや二つあるものよ。隠し事のない女子は女子だけど慎ましさが足りないわね」 「お前の隠し事ってだいたいヤバいことばっかじゃん? 本当にヤバくなるまえに俺んとこ来いっていつも言ってんじゃんか。なーんで信用無いかな?」 「別に、信用無いわけじゃないわ」わたしは紅茶を啜る。ちょうどよくぬるい、甘ったるさが口の中に広がる。「ま、今回のことはちょっと違うのよ。あなたの手を煩わせるって訳にはいかなかったわけ、わかりなさいよね。この鈍感」 「は? …え?」 がさごそと鞄をあさる。かわいらしくラッピングされたのは彼の好きそうな食べ物。ナイス君はいつもお腹空かせてる、という印象が強すぎて何をあげようか悩む以前に足が勝手にお菓子屋さんに向いていた。ナイス君の視線がプレゼントとわたしとを交互に移動する。 「クリスマスプレゼント。あなたのことだからきっとわたしの行動の異変には気付いてると思ってたけど。でも、ま、日ごろの御礼として仕方な…」 最後までわたしのセリフは紡がれることなく、彼の唇でふさがれていた。 「サンキュ、! やっぱ俺の愛って通じてたわ!」 きょとんとするわたしに、「愛してるぜ」とささやいて頬にキスを落としながら、彼は懐から箱を取り出す。手慣れたようにするするとリボンをほどいてその中身を出し、何をするかと思えば、さも当然だというかのように、それを真剣な顔をしてわたしの左薬指に嵌めた。 「ここ、俺のためにあけといてくれよな」 ほんと、ナイス君の行動には頭を抱える。 |