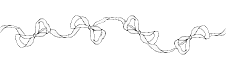
|
※10.5話くらい//ノーウェアに来る前の会話 「はファクルタースの闇でした。私たちが研究に研究を重ね、そして毎日のように血液を採り、実験を重ね、抗生物質を打ち込み、そして天才的頭脳を用いたスパイ潜入用捜査員を育成するための第1号。3年前の事件でうっかり能力に副作用のようなものが出てしまって、血を吸わなければ能力が思うように使えなくなってしまった。使い物にならなくなった彼女をひきとったのは私だった。彼女は実に頭のいい子でね。ああ確かちょうどその時だったかな、彼女の学園内での記憶がほぼ全て消し飛んでしまったのは。そう、私はそんな彼女を外の世界に出したらどうなるか、とても興味があった。一人のミニマムホルダーが何も知らない状態で、どう力を制御できるのかをね。それで提案したのさ、監視付きでスパイ捜査員にできないかってね。まあそんなのは建て前で、彼女をとりまく余計な虫には早々に消えてもらったのだけれど。ああ、彼らにはもちろん素材として協力をしてもらったけれどね。ちょうど私がその素材を持って帰ってきた、その時だったかな。彼女はそこにあった普通のパソコンで既にハッキング技術の才能を発揮し始めていたのだよ。誰に教えられるわけでもなく、身体が覚えているんだろうね。記憶がいくら消えようとその人を取り巻く感覚は消えないものらしい。彼女は5歳のころにはもうすでに難度Sの防壁をこえるまでの天才であった。彼女は一大勢力を築いていてね。きっと君も聞いたことがあるんじゃないかな、『ラプンツェル』。童話を基にしたハッキング集団。私は彼女の勢力に忍び込んでスパイをしようとしたことがあった。もちろん門前払いされてしまったし、私がスパイだということも一瞬でバレてしまったけれども。それでも」 彼は言う。 「すべては機関の闇だった。それを暴いてしまうなんてやっぱり君は天才なのかもしれないね、ナイス君。そしてこの私までたどり着いたことも、やはり運命なのかもしれない。彼女は才能に愛されすぎていた。スパイとしての才能も、技術も、そしてその美しさも一際目立っていてね。彼女に不貞を働こうとする輩から、私は彼女を守ってあげた。彼女に恩を売るのは、いずれ自分に返ってくる利益を考えた私の姑息な手段だ。彼女は私にべったりだったよ。それこそ私の後をちょこちょことついてきて愛らしい小動物のようではあったが、打算的な私の考えをすべて見抜いたうえで私について回っていたのだから彼女も彼女でずいぶんと頭のいい少女だったよ。ああ、そうそう。彼女の両親だったね。それは秘匿されているけれど、実際のところはもう機関に殺されたのさ。知りすぎてしまった彼らはもうすでに脅威だったし、私にとっても脅威だった。死んでくれてよかった。本当にね。そうそう、彼女からアルバムを預かっているんだ。これを見せれば勘のいい彼女のことだ、君が話してあげればきっと思い出すだろう。その後、彼女がどうなるかなんて私の知ったことではないけれど、私の科学的な興味はそそられる」 彼は言う。 「すべては、愛のためだ。私が愛するは、完璧でなければならなかった。何もをってしてもかなわない孤高の天才。そう、ナイス君、きみもそうだ。その孤独から救ってあげたいと心底思えるような愛しい愛しい。私の存在は孤独を救うために存在しているに過ぎない。私が救ってあげなければ、誰が救うのかといえば、そう、それは私しかいないでしょう。私以外に救えない、彼女の過去を知る者も、私しかいない。ただ一つ、過去を知ったものは残念なことにほとんどその命を散らしている。まあ、そう仕向けているのは私だけれどね」 彼は言う。 「彼女は私の光だ。私の全てと言ってもいい、私の研究の全てを彼女が握っているといっても過言ではない。私が抜け出させた、だからこそ秘匿されている存在……私は、平等な世界のために、彼女の能力を使いたかった。それだけのためにわたしは彼女を救いました。すべては私の自分勝手な理由から彼女を救った。そして、彼女を取り込んで、それでも彼女は記憶を失っていた。失ってしまったものを取り戻すことは長きを要することだったと私は気づくことができなかった。そうしているうちに彼女はいつの間にか私の前から消えていましたよ。一度捕まえたと思えばすぐにまたするりとどこかに逃げてしまう。まるで、イタチごっこのようだ」 「そう、それから私はまだ彼女に再会できずにいる。彼女の居場所を特定すらもできない。彼女は元気でしたか、ナイス君。私は彼女を心配しています」 「そっかお前も知らねーのか、」俺はそこで口を開いた。「アイツは俺が会ったときは気に食わねーくらい元気してたよ」 |