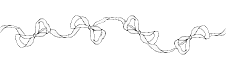
|
気づけば、白い天井が広がっていた。はっと気づいて飛び起きて、腹部の激痛にもう一度ベッドに収まった。ここは病院だ。いったいどうしてここに運ばれたのかは不明だが、きっと 誰かが助けてくれたのだろう。 かつんかつん、と忍び寄る足音がなんだか懐かしいような気がしてそちらを向けば、眉をひそめ怖い顔をしたレシオがこちらに近づいていた。 「絶対安静にしていろ…という前にお前という奴は…今日はベッドから動くな、いいか?」 「レシオ、ごめん」 謝罪の言葉を並べれば、レシオはため息を漏らしながらお説教モードに入る。 「もう少し銃弾が右にずれていたら、お前は生きている保証は無かった。発見がもう少し遅れていたらお前はまた出血し過ぎて暴走しかける寸前だったんだぞ。周りに心配をかける前に、もう少し身の程を知れ」 「…ごめん」 「今日は丁度出勤だったから面倒をみてやれるが…今度は無いからな」 「うん」 「何があった、銃弾で腹を撃たれるくらい危険な状況にいながら俺たちに頼らなかったのは何故だ」 「女の子には秘密にしたいことくらいあるのよ」 「いいか、お前には危機感が欠如している。今度出かけるときは必ず連絡しろ、護衛でもなんでもしてやる。だから、これ以上、心配をかけてくれるな…」 ベッドサイドに腰掛けたレシオはわたしの右手を握って、そして掌に口付けをおとした。 「俺が守ってやるから、無茶だけはするなよ」 「ありがとうレシオ」 |