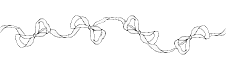
|
「はぁ……本当に問題が山積みだよ。事件のことも君のことも」 真っ暗な部屋の中、奇妙に増築されて並ぶ3つのディスプレイの明かりだけがチラチラとしている。そんな中で彼女はチョコレートを頬張りながらディスプレイの前にちょこんと座りキーボードをカタカタと鳴らしていた。僕が近づけば、くるりと首をこちらに向けにこりと笑う。かわいい少女だった。一般的に見れば美しく、さながらどこかのお嬢様のような風貌。彼女の過去は一切不明。本人も記憶無し。 「お帰りなさい、アート警視。ごはんにする? お風呂にする? それとも、わ・た・し?」 「……、また君は僕に悩みの種を増やさせる気かい?」 「バースデイがこうすればアートも喜ぶって言ってたわ、どう?喜ばしい気持ちになった?」 はぁ、とため息が漏れる。(本当に彼女は…)頬に手を触れて彼女を見つめれば、彼女は指を絡めてきた。「だめだった?」 「女子高生を匿ってるってだけでも危うい立場だっていうのに、君は本当におイタが好きだね」 コンビニの袋からカサカサとカロリーメイトを探り出しチョコレート味を一つとるとパリパリと袋をあけて食べ始める。カロリーメイトを咥える彼女に少しだけいやらしい妄想をしたなんてことは、断じて、ない。 「アートはちゃんとご飯をくれるから好きよ、栄養食は楽よね」 「人の気持ちも知らないで好き放題してくれるよ、君は」 「そういえばこないだの件だけど、」彼女はパリ、とカロリーメイトを齧ると、片手でぽちぽちとボタンを推し進めてエンターキーを押した。「潜在ミニマムホルダーと後発ミニマムホルダーについて、これを一旦まとめるならば、前者は生まれつきミニマムの備わった者でありファクルタース学園に通っていた者であることが大半である。且つ前者においては適正があり、ミニマムホルダーとして登録されている。それでいてアート警視、あなたのような優秀な人間を政府有能機関へ送り込み、一般人にバレないように世間に溶け込んでいる。後者については何者かによる薬品投与により後発ミニマムホルダーとして覚醒。そして自らの欲望を満たすため、様々な犯罪を犯している様子。後発ミニマムホルダーについて、必要とされるものとしてミニマムホルダーの脳髄が必要とされることが判明しており、先のミニマムホルダー連続殺害事件と関連している可能性が極めて高い」 ふーむ。と持論を繰り広げながら事件の記事と外部サイトをハッキングする彼女。「ねえミニマムってなんだろうね、こんなことまでして手に入れたいもんかな。ファクルタースの秀才、アート警視」 これ、資料だよん。こっちが参考元ね、と資料の入ったファイルを渡してくる彼女には感嘆の声も漏れない。おそらく嫌そうな顔を一瞬浮かべた僕を振り向きもせず、彼女はもぐもぐとカロリーメイトを咀嚼し、それから、と続ける彼女はやはりというべきか、せわしなく切り替わる画面から目を離さずに指をカタカタと動かしながら淡々と答えた。こんな無防備なところを後ろから攻撃されたら、危ないだろうに。と思ってしまう僕は、少し異常かもしれない。 「あ、そうそう。これを見て。ちょっとある場所の監視カメラの捉えた映像なんだけど」 「これは…」僕はため息をつく。本当にどうなっているのだ……「君は本当に恐ろしくも頼もしいよ」 警察内部でしか公開されていない情報だ。これについて思うんだけど、とまた自論を繰り広げはじめた彼女に僕はただ自分との力の差を見せつけられているような気分になる。彼女も、また天才なのだ。世界を股にかけ、情報という情報を売り情報を求め、情報を取引する。それが彼女という人間であることを改めて思い知らされる。さすが、一世を風靡したネット犯罪組織のトップ。クラック技術は今までのどのハッカーやクラッカーたちよりも上手であり華麗。と、全ハッカーの尊敬と羨望を独占し、そして一瞬で消えたとされる彼女。ひょんなところから彼女と繋がりが生まれ半ば押しかけられてはいるが、僕としては捕まえなければならない存在であることは確かで、それでも実際のところこうして彼女の技術に甘んじている。矛盾している関係だな、と失笑した。笑えない。それでも彼女は僕の経済力がある限り、僕の元でその技術をふるうのだ。 「あなたが知りたいならどこまでも調べるわ。でも覚えておいて、人生知らないほうがいいこともたくさんあるってこと」 「ありがとう、。わかってる。ちゃーんと肝に銘じておくよ」 僕は彼女の隣に腰を下ろし、彼女の額に軽く口付ける。すると彼女は僕の右手をとり、手の甲に、まるでおとぎ話のおうじさまみたいに口付けた。本当に彼女は一枚上手だ。 「お仕事お疲れ様。アート警視」 「ところで、…僕のシフォンケーキを食べたね? 悪い子はお仕置きだよ」 「やだ、バレてたのね。一口でやめようと思ったけどあんまりにも美味しかったから頂いてしまったわ」 「ばれてましたよ、お姫様」 「ごちそうさま、王子様」 これで許して、と言う彼女からカロリーメイトの味のする、深いキスが降ってきた。ああ、もう、本当にこの子は策士である。知らぬ間にどんどん堕とされていくのだ。 |