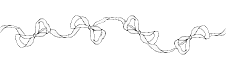
|
「ふーん、女子大生の護衛? 行ってらっしゃい。わたしは大人しくここではじめちゃんと留守番してるわ」 ね〜、とカウンターに座るはじめに笑いかければ「あげる」と一口カレーライスをいただいた。先ほど私がはじめに頼んであげたものだ。ありがと、とわしゃわしゃ頭を撫でてやるときもちよさそうに目を細める。小動物のような彼女の髪にちゅ、とキスをすればバースデイが「俺には?」とうるさく言うので袖口をひっぱって屈んでいただく。右頬にちゅ、とキスをしてやって「これでいい?」と言えば彼は満足したようにわたしの頭を撫でた。 「いいかー? ちゃぁ〜んと愛しの俺のこと待ってろよ、」 「はいはい」 「。くれぐれもカロリーの摂取には気を付けるように。お前の摂取量は一日の成人女性の平均カロリーに足りていない。栄養不足で倒れられては困るからな、何か頼んで食べておけ」 「はいはい」返事を返せば、「返事は一回だ」とお怒りの声が飛んできて「はーい」ともう一度返事を返した。適当に彼らを送り出した後、マスターにカレーとカツサンドとコーヒーを頼む。ゆっくりとマスターが準備をはじめたのを傍目に、コネコが口を開いた。 「そういえばちゃん、ファクルターズには通ってないんでしたっけ」 「ええ、たぶんね」 「…たぶんって、どういうこと?」はじめがこてん、と首をかしげる。 「正直、高校に通うまでの記憶あんまりなくてどこで何をしてたのか、自分が何者なのか、イマイチわからないの。だからいろいろ調べてる途中。でも政府からの書類も何もきてないし、正直自分のことがよくわからないわ」 「えっ、てことはちゃん記憶喪失なんですかぁ!?」 「さあ? レシオが言うには、PTSD…ストレス性記憶障害みたいなものって言っていたわ」 「お待たせお嬢さん」コーヒーが出てくる。続いてカレーとカツサンドも。「で、本当にその記憶。思い出しちまって大丈夫なのか? 人生知らなくていいことも、世の中にはたくさんあるもんだ」 「いただきます」わたしはそれにあいまいに笑って答えた。「ま、そうは思うんですけどね」 「でも、自分の過去がすっぽり抜けてるってちょっと不安じゃありませんか?」 「ええ、それが本当に思い出していいことなのか、思い出してはいけないことなのか。いまだに掴めないのがもどかしいかな。女の子は複雑なんですよ、たぶんね。どっちでもいいきもするけど、どっちでもよくないきもするの。まあそうやって悩んでること自体が、無為なことなのかもしれないわね」 もぐもぐとカレーをほおばりながらカツサンドを食べる。ここのマスターのごはんはまことに美味である。 |