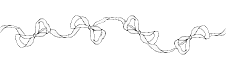
|
(レシオ続き*ヒロインが割と誘い受け)※寸止め? 首筋からどくどくと血液が吸われていく感覚を、奇妙な感覚だと冷静に考えている自分がいた。 レシオの上で夢中になって血を吸う彼女はまるで本物の吸血鬼のようであり、しかしそうではなかった。首筋から唇を離した彼女をみて、ようやく終わりか、と一瞬思ったのもつかの間、気づけば唇をふさがれていた。こんなこと聞いていない、何をするんだと文句が溢れてくるが、気づけば舌が口内に侵入してきて先程の鉄くさい血の味が口の中に広がる。むせ返りそうになるその息も彼女にからめとられて飲み込まれているようでまるで窒息死するのではないかと思った。いや、事実窒息しかけていた。 ようやく息が吸えたと思えば、もう一度口づけが降ってきて、身体が火照りはじめる。 喉がやけるようにあつい。 「ごめんね、この能力ちょっと厄介でさ。血が足りなくなると自制心が全部吹っ切れちゃうの」 だから、ゆるして? かわいらしく笑う少女に、己の理性が飛びそうだった。「貴様、何をした…」 「わたしは何もしてないの。わたしの自制心がふっきれたことによる血液感染みたいなものかな…? あなたの本能がわたしの解放されたポテンシャルに疼いてるだけ」 「…うぐ…! これ以上は…」 「ね、こんなに固くして…やっぱ興奮しちゃった?」 「…生理的現象だ」 「苦しいんなら言えばいいのに」 「女子高生とよろしく性交する趣味はあいにく持ち合わせていない、年の差を考えろ。割と犯罪に近い」 「まだ、そんなこと言ってる余裕あるの?」 くすくす、と己の上にまたがる少女が笑う。ゆらゆら腰の上でレシオのものを擦りあげ、時々小さな喘ぎ声を漏らしながらレシオのズボンに手をかけた。「それ以上はやめろ、のちのち後悔することになるぞ」 「しないよ、大丈夫」 そういっている間にも少女はレシオのモノに触れながらゆらゆらと右手を上下に動かしていたが、ぴたり、とその手が止められる。ほかでもないレシオの手によって少女の腕は拘束されていた。もはやすでに軽く乱闘である。 「ダメだと言っているのがわからないのか、」荒くなる息を落ち着かせながら紅潮する頬のまま少女の腕を握る力が強くなる。少女は顔をしかめて、う、と唸ったが同じように呼吸を荒くしていた。これじゃあまるで俺が襲っているみたいじゃないか。 「おにいさんのいけず、わたしだってこんなことしたくてしてるわけじゃないのに」 「……なら何故」 「血がたりないとね、ちょっと身体が止まんなくなっちゃって。欲望とかおさえてるストッパー全部外れちゃうの、おにいさんの血は美味しいからさ、ええっと、興奮しちゃって……ええっとだからちょっとその、言いにくいんだけど血液量が足りるまでは止まらなくて、でも血を吸いすぎると人が死んじゃうでしょ? そうならないためにこうやって代わりになりそうなほかの体液をもらってるっていうか、なんか説明しにくいんだけど」 「つまりは、」口を開きかけたところで、少女の顔が近づいてくる。また少女に押し倒される形になり、気づけば口の中を犯されていた。からむ舌が唾液を吸い取っていくようで酸素を求めて思わず彼女を引き離した。不服そうな赤い目の少女はちゅ、とレシオに軽く口づけをする。「血液で補えない分、体液がほしいと?」 「そういうこと。ちなみに輸血はダメなの。最初に病院で試したら次の日には隣のビルが一個壊れてたから。人に流れている新鮮なのじゃないと満足できないの、面倒でしょ?」 だからできるだけ血を流さないようにしてるんだけど、今回はあなたのせいね、と少女は悪戯気にくすりとわらった。 |