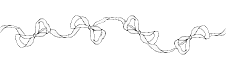
|
深夜:ヨコハマ郊外、路地裏。 うぐ、と低いうめき声が上がる。 「何をする、貴様っ!」 刃のようなものが腕をかすめそうになり、とっさにレシオはミニマムを発動させて防ぐ。そうでもしなければ腕が吹きとばされていたかもしれない、そんな威力であった。真っ赤な刃はどれだけの血を吸ったのか、奇妙に赤黒くきらめいている。暗闇の中ではいっそうその薄気味悪さが際立った。 レシオは目の前の少女に困惑していた。襲われていたのは少女のほうで、事実出血量も半端じゃなかった。それなのにこの瞬発力と、そして目の前に転がる瀕死の男はなんだ。そこから導き出される結論として、(この女、ミニマムホルダーか。)と推測するのは簡単であった。白銀のような長髪、真っ赤に染まる瞳、そして口から滴る血液というのはまるでおとぎ話の吸血鬼を連想させる。 (足元に滴る血液は、男のものか、少女のものか?) 水たまりのように広がる流血に、レシオは少し戸惑った。ほぼ一人分の致死量に近い血液が、どくどくと地面に流れている。レシオから見て彼女という存在はミニマムホルダーであるという点以外においても異端であった。こんな能力、見たことがない。 「おにいさん、おいしそうね」 「何のつもりだ」 「ねぇ、ちょっと味見させてくれるだけでいいの。いいでしょ?」 こてん、と首を横に傾げる彼女はまるで純粋ですといわんばかりのしぐさではあるが言っていることとまったく噛み合ってはいない。ぴりぴりとした殺気のような緊張感が走る中で、レシオは少女を一瞬見失った。いや、見失ったのではない。一瞬のうちに視界から消えたのだ。 「ぅ…!!! ぅぐッ!」 気づけば組み敷かれて首筋に噛みつかれていた。刺されたような痛みと激痛がはしり、傷口が熱くなる。 「あは! やっぱりおいしいね、おにいさん」 真黒なセーラー服を着た少女は、まるで吸血鬼であった。 |