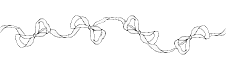
|
「いい子にしてるんだぞ、。くれぐれも能力は発動しないようにな」 と、レシオにくぎを刺された彼女は少し青白い顔で無言のままレシオをにらんでいた。カフェノーウェアが妙な緊張感に包まれる中、と呼ばれた美少女はレシオのほうに向けていた視線をふとはずしてこちらを見た。人形のように精巧な顔立ちをした彼女は、腕を後ろ手に拘束されている点以外においては通常の美少女であった。そう、なぜ腕を縛られているのか、というのは疑問ではあったが。 「れ、レシオさん美少女になんてことを…」 コネコがあわあわと慌てるがバースデイがやれやれと首を振る。 「まーこの格好についてはいろいろと理由があるみたいなんだけどレシオちゃん教えてくんなくってさー」 「こいつの能力に関係している」 「そーそー、これの一点張り。趣味でさせてんのか俺も疑ったんだけどさー、レシオちゃんにかぎってそんな事ないみたいだしー?」 「放置しておくのは危険すぎる、だがしかし一人にさせておくのも危険すぎる。依頼が終わるまで少しだけ預かっていてほしい。くれぐれも拘束は解かないように……死にたくなければな」 「ったく、こ〜んな美少女が人なんて殺せないって! まぁーったくレシオちゃんってば心配性ぉ〜」 「行くぞ、バースデイ。依頼人が待っている」 「ほいほーい。じゃ、またねぇ〜! ちゃんのことよろしくぅ〜!」 (一体どうしろというのだ)というのが周囲の疑問であった。 よくみれば高校生のようで、このあたりではわりと有名なお嬢様学校の制服を着ている。黒いセーラー服に真黒なタイツ。灰色の瞳はまるでこちらが何を考えているか見透かしているように冷たくひかっていた。沈黙に耐えかねてコネコがマスターに視線を向けると、マスターが口を開く。 「ご注文は何にいたしますか?」 誰もがそうじゃないだろ!と心の中でツッコミをいれているなかで、はぱちくりと眼を見開いた後に「ミルクティー」と答えた。「アイスで」 マスターが注文を作っている中、また重い沈黙が流れかけたがナイスが「なぁ」と口を開いて少女の隣に移動する。「アンタ、っていったっけ。お前レシオに何したんだ」 「何って、なにも………ただ、…ちょっと迷惑かけた、かも?」 「なにも、ねぇ……アンタの能力は?」 「さぁ? レシオは血のミニマムって言ってたわ。わたしにはイマイチわからないけど」 「ふぅん」 アイスティが少女の目の前にでてきて、マスターが「アイスティーでございます」と少女に目を向けた。 「ね、きみ暇ならストローさしてよ」 ナイスのほうをみて少女が言うので仕方なく紙包装から出したストローをアイスティーにさしてやる。つう、と飲む少女がすこし扇情的でどきりとした。願わくばはやくレシオが帰ってくることを祈りながらごくりと喉を鳴らすおおきな猫のような彼女を、じっとみていた。 |