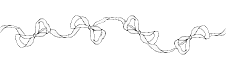
|
(※別館リクエスト) だん、と急に地面に押し倒された。固い地面が背中にひんやりと冷たい。目の前のアートは不機嫌な顔をしていて、その原因がわからなくてわたしはどうしようもなく不安に駆り立てられていた。一体何だというのだろう、彼の気に障ることなんて何も心当たりがない。そんな感情が表に出ていたのだろうか、彼はわたしの目の前にまで顔を近づけ額を押し当てた、顔が近い。 「アート、どうしたっていきなりこんなこと」 「君が悪いんだ、」アートはさっきからこればっかりだ。「君が、君のせいで…ッ!」 理由を問いただしても彼がこの状態ではまともな返答は期待できない。訳の分からない、アートらしくもない言い訳に内心でため息をつけば、彼はそっとわたしの唇に軽いキスを落とす。一瞬唇が離れた、と思えばもう一度くっついて、どんどん深いものに変わっていく。「アート!」と声を荒げようとしたが、言葉にはならずただ喘ぎ声のように消えた。まるで別人のようにわたしの唇に噛みつくようなキスをする彼は、一体何を抱えているのだろうか。 「アート」 唇が離れたところをみはからって、声をかける。いまにも泣きそうな顔をする彼は、わたしの頬を撫でるとそのまま下のほうへ手を滑らせ、わたしのボタンを一つ二つと外し始めた。こんなの間違ってるよ、とわたしは言う。一瞬ためらったかのように手を止めた彼だったが、その一瞬の後にはもうすでにその手は動き始めていた。何が彼を突き動かしているのだろう。それでも、こうまでして彼が躍起になっているのは何か理由があるはずなのだ。 「ごめん、でも黙って」 「そんなの、」わたしが納得できないじゃない。という言葉はまたかき消される。脳に酸素がいきわたらない。呼吸が乱れる。ショーツの中に細く冷ややかな体温の掌がわたしの中に入ってくる。あ、と小さく声が漏れて右手で口を塞ぐ。ほぼ着衣のままで、くちゃくちゃと淫猥な音だけがこだまする。何分かわからない愛撫のあとに、彼はおもむろに自身のズボンのチャックをおろし彼のかわいらしさの残る顔からは想像できないグロテスクにそそりたつ雄をわたしの入り口にあてがっていた。「ちょ、」避妊は、なんていう間もなくずぶずぶとそれがわたしのなかに吸い込まれていく。あ、とわたしのものではないかのような高い嬌声があがる。膣が収縮して、彼のものを締め上げる。誰が言ったか身体は正直なわけじゃなく、ただ本能のままに彼の欲を吸い込んでいた。 はあはあ、と彼の荒くなっていく息遣いが聞こえる。ぱんぱん、と彼の腰が欲望に合わせて動くのをぼんやりとした意識の中で眺めていた。まるで第三者から見ているような他人事のように。わたしの上にまたがって、ひたすら腰を振り続ける彼が、なんだかまるでわたしよりも苦しそうに見えた。どうして無理矢理犯されているわたしよりも、彼のほうがよっぽどわたしよりもくるしそうなんだろうか。好きな人と結ばれるなら無理矢理でもいい、ってちょっとでも歪んだ感情を持った、そんなわたしよりもよっぽど。 何が真面目代表であるかのような彼をそうさせたんだろう。また、身体のなかに彼の欲望を感じる。彼がわたしに崩れ落ちるように覆いかぶさって、ぽたぽたと彼から水滴が滴ってくる。汗だろうか、と彼の頬をつう、となぞればそれはまるで、……いや、違う。これは。 「 、君はどうして僕だけを見てはくれないんだ」 違う、そんなわけない。わたしはずっと。 伝えようと思った言葉は、急に降ってきた唇に奪われて、結局彼に伝えることなどかなわなかった。 |