   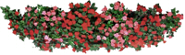 (学園捏造・ハロウィンネタ)  居た、と目的の人物を見つけてどきりとする。みんながみんなお菓子を異常なペースで作っていたのはこういう意図があったみたいで、遠くから見てるだけでいいよ!()なんて言うわたしの意見はことごとく無視されて今に至る。要するに最初から仕組まれているのだ。わたしが田中君にお菓子を渡す担当に無理やりされていることも、なにもかも。渡したフリをして自分で食べてしまっても構わないけれど、それでは田中君だけお菓子をもらわなかったことになってなんだか不憫だし…そういうポジションはどちらかというと左右田くんのほうだ。ため息をつきそうになればわたしが立ち止まっていることに気づいた田中君のほうがずかずかとわたしの方に近づいてきて一瞬だけ足がすくむ。 「貴様…いつまでそこで立ち止まっているつもりだ…」 声をかける前に用があると見抜かれてしまうような習慣に慣れてきたのはいつだっただろうか。私がわかりやすいのか、はたまた彼が鋭すぎるのかはわからないけれど、気がついたときにはいつも彼に行動が見破られていることが多い。おそらく、言っている事はわからないにしても、カンは鋭い方なのだろう。そうでなければ予測不能の行動をとりやすい動物たちの扱いなどはできないはずだ、というのがわたしの結論だ。 「えっと、用ってほどじゃないけど、ほら、その、ハロウィンだったし女子みんなで一緒に作ったのが余ったからみんなに配ってるんだけどね」 今日ってハロウィンでしょ? と言いながらマフィンを手渡す。「花村くんの作った料理よりおいしくはないし田中君が人間の作ったものが口に合うかわからないんだけど」 「確かに人間が作ったものなど俺様の口にあうはずもないが、お前は…そうだな、そういった点から見て特異点と言えなくもない…いいだろう。泣いて懇願するならば、その供物を貰ってやる! フハハハハ! 貴様、ありがたく思うがいいぞ!」 「そっか、貰ってくれるんだね! ありがとう」 「…いや、その、ありがとう」 「ど、どういたしまして」 なんだか恥ずかしくなって少し俯けば、ちらりと澪田ちゃんの角が陰に隠れたのが見えた。わたしはじゃあね、と一言残してその場をぱたぱたと走り去る。 (▲)(20121104:ある程度の予感はソザイ |