   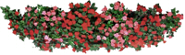 状況証拠ばかりがあがっていく中で、わたしはなにも言う事ができずに彼のほうに視線をあわせないように目を伏せた。どうして彼がやったのかという疑問と、これ以上暴くのはもうやめてほしい気持ちが渦巻く。もう聞きたくはなかった。もういいのだ。結局のところ今回も、告白もできずにいるわたしがいけないのだ。左右田君のように好きだと感情的になるような事もできずに、人知れず諦めるような一方的な恋。数日間の中でじわじわとわたしの中を浸食していくものは、まさしくそれだけだった。第一印象はなんだか怖そうだったけれどそういう人の方が逆にいいことをしたときにすごくいい人に見えてしまうなんて単純な心理のはたらきに、いとも簡単にわたしはひっかかってしまった。そして気づけばいつでも彼の事ばかり考えて、馬鹿みたい。未練なんていくらでもあるけれど、きっとこの恋も、いずれ風化してしまうだろう。いままでのかわいそうな恋とおなじように、わたしの心の奥に鍵をかけて出られないようにするだけ。 犯行を認める彼も、そしてドッキリハウスも、もうどうでもよかったのかもしれない。今はもう、忘れてしまいたい。記憶を全部消して、それでまた島に来た時からやりなおすんだ。ほんとうにこれで終わりなのだろうか。でも諦めは、諦めなきゃいけないのは突きつけられたものだ。さようなら、わたしのかわいそうな恋。 そしてかちゃりと鍵をかける。少し深呼吸をすれば、もう投票の時間のようで、わたしはボタンを押す。決定したそれはとてもあっけのないもので、それまで通りに処刑の実行が行われる。それは決定事項だ。特例は無い。これは一体いつまで続くのだろうか。(…最後の一人まで?)そして誰もいなくなるのだろうか、結末はわたしには見えなかった。ぼんやりとしていれば、不意に田中君がなにかをわたしのパーカーのポケットに押し込んだ。 「落としたぞ、人間」わたしは何も落としたものなんてなかったと思っていたのだけれど、その時はよくわからなくて曖昧にありがとうと言って笑った。きっと全然うまく笑えてないんだろうな。せっかく最後にはなしかけてもらったのに。 「さらばだ」 その言葉を最後に、田中君は、 何日かぶりにコテージに戻る。わたしは誰とも話す気力もなく、ひとりきりでスーパーに寄って食べられそうなものを適当に頂戴した。ごっそりとレジ袋に入れたそれをけだるげに持ち上げて、たらたらとした足取りで道を歩く。疲れていた。それ以上に、いろいろなものを失った。コテージのドアを開ければ、数日しかいなかったのになぜだか懐かしい我が家に帰ってきたような気持ちになる。なんにも思い入れなんてないのに、と肩を下ろしながら、重たい袋を下ろした。 とたんにこらえていた涙が、ぽろぽろと溢れ出す。どうしてこんなことになっちゃったんだろう。こんなにも好きだったのに、どうして。涙腺の緩んだわたしの瞳からは、わきだす泉のようにとめどなくあふれてくる。シャワーを浴びよう。体の表面についたわずかなほこりのように、この気持ちも全部洗い流してしまえればいいのに。わたしは着ているパーカーを脱ぎながらシャワールームへ向かう。シャワールームに入ったと同時に、パーカーからするりとなにか落ちてきたみたいだ。なんだろうとそれを屈んで拾えば、それは大したことのない、紙切れのようなものだった。 なんだろう、と折りたたまれるそれを開けば、何事か書いてあるようだ。暗号のようなそれは、田中君がよく話していた言葉に似ていた。わたしの記憶にないそれは、まるであの時に田中君がわざわざあんな嘘までついてわたしに何かを伝えようとしたのだろうか。ぱちぱちと意味もなく瞬きを繰り返す。ぼやけて見えにくくなった文字を、ちゃんと見るために目をごしごしこすった。文字を、じっと見つめる。わたしはどきどきしながらその紙をパーカーに押し込んで、服を脱いで蛇口をひねる。 わからなかったけれど、確かにそこには書かれていたのだ。閉じ込めたはずの気持ちだったのに、外側の壁が剥がれ落ちてあふれッ出してくる。鍵なんて意味のないものみたいに、ざあざああと流れるシャワーの音に消えた。めちゃくちゃになったわたしの中身。涙かシャワーの水かわからなくなったそれはぽたぽたと、抜けた髪の毛と一緒に排水溝に流れていく。 「言い逃げなんてずるいよ、ばか」 誰にも聞き取れないような、声になっているか分からないような声が出て、一瞬誰の声かと疑う。わたしの声だ。「ひどい声」 壁に反響した声は、わたしの声じゃないみたいだった。蛇口をひねって水を止める。バスタオルで身体を拭いて適当なネグリジェに身を包めば、全身を疲れが襲ってきた。田中君の筆跡でかかれたであろう紙を思い出しながら部屋の中を歩いてぽすん、と布団に倒れこんだ。何も考えたくないのに考えてしまうのはきっとわたしの悪い癖だ。たらりとまた体を起こすと、がさがさとビニール袋を漁る。適当なポテチの袋を開ければ不健康そうにも関わらず香ばしく食欲をそそる油のにおいが部屋の中に広がった。 (素直にいえばよかった) 素直になれないわたしと、なにもしらないまま死んでいくあなた |