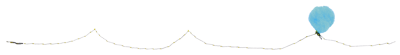 「これはこれは初めまして、可愛いお嬢さん。アスの噂によると闇口衆の子だと聞くじゃないか、ふんふん、試験をするのが楽しみだ。何だったかな、アスが君の主人を殺してしまったとかだったかな。それにしても君は強い精神力を持ち合わせているようだね。主人が殺されたと言うのに、主人を殺した張本人であるとも分からない殺人鬼にホイホイと付いてきてしまうのだからね、実に興味深いじゃないか。確か名前はちゃんだったよね、私の事は是非『お兄ちゃん』と呼ぶといい」 「……」 「私の存在を意に介さないように振舞うというのは一向に構わないけれどもやっぱり可愛い女の子には『お兄ちゃん』と呼ばれたいのが心情という所だがどうかね、と問いかけても君は全く反応をしてくれないように見える。どうしたらいいか我ながら悩む所だね、うふふ」 ツンデレだね、それもいいかもしれないなとか何とか言いながら、またしても、うふふと笑う。 「まあ、突然の所悪い事は重々承知ってところな訳なのだけれどどうやら君には零崎としての素質があるらしい、可愛い女の子とはいえ無条件に『お兄ちゃん』と呼べとか理不尽な事は言わないが条件をつけるならば君にその十分な実力が伴っているならば『お兄ちゃん』と呼ぶことを特別に許可しよう! どうだい、この条件なら何も文句は無いだろう。まあ君が私に勝てるという仮定条件をつけるなんて野暮な事はしないけれど、負けた場合にも『お兄ちゃん』と私を呼ぶ事に関しては大いに大賛成だから安心したまえ!」 「……」 「そうか、感動して言葉も出ないか!」 「……」 感動ではない、絶句しているのである。 「それでは、――」 《二十番目の地獄》は、その、自らの二つ名と同じ名前のマインドレンデルと呼ばれる鋏というには少し大きな造形物を取り出す。 「零崎を、開始します」 時は数日前までさかのぼり、《街》こと零崎軋識による出会いがあった事が引き金となったのはご存知の通りだ。それはまあ別の話なのでここでは割愛するとしよう。しかし、そもそもは《闇口》である故に、《零崎》とは相容れない存在であるのには変わりない。だからといって《零崎》ではないと誰が言い切れるだろうか。口で言い切ることは簡単であっても、本質的な意味でそうであるかどうかという事は分からない。誰にも、本人にすら自覚の無い時が、稀にある。一般人からでも唐突に才能が開花する場合のある《零崎》のこと、殺し名から《零崎》が出た所でなんら疑問はない。今までにそのケースが無かった事の方が、異状だったのかもしれない。今までにあったという事実が無かった事が異常だったのかもしれない。 《零崎》はどこにでも現れる。 だからこそ、《零崎》。 それでこそ、《零崎》。 血の繋がらない家族、《零崎一賊》。 振り下ろされた一撃をひらりと左にサイドステップで跳びながら交わす、非常に甘い一撃だった。コンクリートの道路が少しえぐれて、そうかまあそんなものだろうなとは単純にそう思う。重たい一撃、さすが戦闘に特化していると言っても過言ではない。一人一人の個人技はともかくとして、集団としての恐ろしさを誇る彼らには手を出すなと上から十重に仰せつかっている身としては少しばかり謀反を起こしているような複雑な気持ちのだったが、それでもこの状況は然るべくしてなったという感が否めなかったのである。 致命傷とはいかなくとも、数箇所に切り傷があった。しかし相手にもが攻撃したダメージは徐々に効いてきているようだった。お互いに少しずつ運動量と体力の消耗によって息があがってくる。はポケットに仕込んである虫ピンを何本か取り出した。あくまでも、これはおとりとしての誘導だ。 「苦戦しているようだけど、調子はどうだい?」 「……」 軽口を叩く余裕はあるのだろう、双識はうふふと笑う。 「言葉も出ないくらい苦戦しているかい?」 「…いいえ」 「そうかいそうかい、ならいいんだ! っていうかずっと無視されてたから本気でちょっと落ち込みかけてたんだよ? お兄ちゃん泣いちゃうかもよ、とか思ってたんだけど、実に喜ばしい事じゃないか初会話だなんて素晴らしい! お兄ちゃん感動して泣いちゃうかもよ!」 は少し絶句すると、虫ピンを何本か投げて《春霞》を抜刀して高く跳躍しながら斬りかかる。双識はマインドレンデルで虫ピンを弾き飛ばし、《春霞》を受け止める。双識の左足がぐっと地面にめり込んだ。 「成る程、暗殺だけが仕事じゃないようだね。しかし、今時パンチらの一つや二つないなんてどうかしていると思うけれど少しだけ大目に見よう」 「……《自殺志願》、実は変態だったのですね。それはさておき、いい加減手を抜いて戦いながら様子を見るのは辞めていただきたいのですが」 愛刀である《春霞》でマインドレンデルをはじき、距離をとる。 「うふふ、」 と、双識が笑う。 「女の子相手に、本気を出すのは気が引けるというものなんだけれどね、君がどうしてもと言うのなら」 「……」 「ちょっと、頑張っちゃうよ」 ただし、お兄ちゃんと呼んでくれたらの話だけど。 「どうして、そんなにこだわるんですか」 「呼ばれたいからに決まってるじゃないか、他に理由なんて無いさ」 「そんな、ものですか」 「そんなものだよ」 針金細工のような細い腕を使ってくるくるとマインドレンデルをもてあそびながら、双識はうふふ、と笑った。 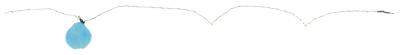 (20100330:ソザイ |