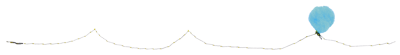 がらり、と いままでの物が崩れるような感覚に陥る。私は、うっかり友人かと思い三時に裏庭に来たのだけれどそこに待っていたのは見知らぬ男子生徒である。あれは誰だろうという疑問から状況を把握する能力が少しだけ後れて、私は気づく。この状況に気づく事が出来ないほどに間の抜けたような生活は送っていないはずだ。しかし、私は現段階で不破大地という彼氏(改めて言うと少し照れる)が存在しているわけだし、残念ながら彼に気持ちが傾くなんてことは地球が崩壊してもありえないことなので、これは断る事になるのだけれど。 もし、告白されたら、という過程の話である。 もしかすると、知らず知らずの間に私が何者かに恨みを買っていて、その復讐というか逆恨みで呼び出して決闘しろとかそういう類の者かもしれない。その可能性だって否めないのだ。事実、そういう呼び出しも何度かある。私はマズイ所に呼び出されてしまったなあ、とため息をつくと、相手はこちらに気づいたようだった。 「さん」 相手がおずおずと私の名前を呼ぶ。私はいたって平静を装いながら、内心面倒ごとに巻き込まれてしまったのを悔やみながら落ち着いた雰囲気で返事をする。 「何でしょう」 「俺と、付き合ってもらえませんか」 「無理です」 即答。二つ返事でノーに決まっている。 「どうしてですか、どうして俺じゃ駄目なんですか。俺のほうがさんをしあわせにできる」 その理由は所詮、言いがかり。仮定とされる推論に過ぎない。現に私は不破君が隣にいてくれるだけで幸せだし、『俺のほうが』と言っているあたりで私と不破君との関係は承知の上でのことなのだろう。ならば断られるということも目に見えて分かったはず。 「私には今付き合っている人がいるし、それで幸せなの。それじゃ理由にならないかな」 「あんな奴の、どこがいいんだよ!」 「君には分からないかもしれないけれど、私は今が幸せだから」 へらり、と私が笑うと彼は納得いかないと言いたげな表情を浮かべ、不満の色をありありと露呈する。その自信がどこから来るのだろうか、私はその自信の由来に基づく推論が気になって気になって仕方がなくなってくる。こういうところは、一緒にいると似てくるものなのだろうか。知りたいという欲求は、人間が切り離すことのできない欲求の一つであるような気がする。人間は考える葦であるというのは、よく言ったものだ。私はそう言っている彼を大尊敬しているので少しにやりと口角があがりそうになって、それに気づかれないように口を押えた。 「ほんとさんって変わってるよなぁ」 「そうかしら?」 「変わってるって、…でもそんなことが理由で俺はさんのこと諦めないからさ」 「私の気持ちが揺らぐことなんて天変地異が起こってもないけど」 「手厳しいなあ」 「まあストーカーにならない程度にしたらいいと思うわ、じゃあね」 私は立ち去り際、ひらひらと彼に手を振ってその場を後にする。物語の最終章というものはいずれ訪れるものだけれど、それは今ではないのだ。 私は待ち合わせに遅れないように、小走りになりながら歩道を急ぐ。 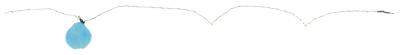 (20102128:ソザイ |