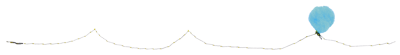 頭を撫でられる、その感触が好きだった。その中でもひときわ大好きだったてのひら。それが、あの人だった。それだけの事でしかなかったなにかが、変わってしまったのかもしれない。好きだった。その背中はいつしか遠くなっていた。徐々に遠くなる背中を必死に追おうとした。それでもあの人の足取りは、私に追いつけるようなものではなくて、転んでそのまま泣いている私の頭を撫でたかと思えば、また遠くへと言ってしまう。その繰り返しで。いつでもその繰り返しで。そして、いつしか、ぷつんと、 途切れる。 彼に会ったのは、私がまだ小さいころだった。物心ついたころの私は、彼が輝く太陽を背にして立っていてとても大きい人だったという事しか覚えていない。あの人の掌は、まるで大きなおひさまのように温かくて、私の頭をつつんでくれた。(、)と私の名前を呼ぶ声も、ぜんぶぜんぶ、大好きで、あの人が世界の中心みたいな、そんな気がしていた。それくらい、彼は私の人生に多大なる影響を与えている。でも、きっと彼は、そんなこと知らない。もしかしたら、何食わぬ顔で全部知っているかもしれないけれど。 彼にあこがれて、中忍まではこぎつけてきたけれど、全然実力が追い付かないのが現状だった。やっぱり私が追い付けるような人ではないのかもしれない。 「なーに、悩んじゃってんの?」 「か、カカシ先生」 ぎくり、と背後から現れた気配に慌てて立ち上がる。先ほどまでぼんやりと考え込んでいたせいで、やっぱり私はどこか注意力が足りないと、また嫌味でも飛んでくるかもしれないと、目を伏せた。ほんとうに、私は何をやってもだめなのかもしれない。追い付こうとしても、追い付けなくて、そんな自分がもどかしくて、それでもどうしようもできない。そんな屑みたいな。 「背後の気配に気づかないなんて、マダマダだーね」 「注意力不足でした。……それで、何か私に用でも……?」 おそるおそる顔をあげれば、目の前にカカシ先生の顔がおおきくあって、思わず一歩後ずさりながらひい、っと悲鳴を上げてしまう。カカシ先生は頭をぽりぽりと掻きながら、んーと唸った。この人の考えている事は、イマイチ私には理解できなかった。これはずっとそうだ。この人が担当にならなくて安堵している。「…そんなにされると、ちょーっと傷つくなァ」 「……」 「あー! はいはい! わかったわかった! 悩みなら聞くから、ね? そこの甘味処で!」 私のじっとりとした無言の視線に、彼は耐えられなくなったのか甘味処での話し合いを提案してきたようで。まだ怪しい、と心の中でいぶかしみながらじっとりとした視線を向け続ける私に、「ほら、特別サービスで御代持つし、ネ?」と、くりっと首をかしげる始末。よけいに怪しくなるとは思わないのだろうか。私はいかにも罠のように怪しい誘いに困惑していた。どうしてこのタイミングでこの人は甘味処なんかに。考え、というか何か謀っているに決まっているのだ。この人の場合、イマイチ信用できないようなひょうひょうとした態度の割に、計算しつくされた考えで行動をしている。だから、 「ほーら! 行くよちゃん!」 結局私はずるずると引きずられる形で、甘味処へと足を運ぶことになる。 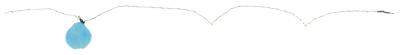 (20112128:ソザイ |