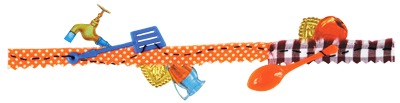 その日の私は町にふらふらと繰り出して、ニューヨーク市街を散策していた。カメラをぶら下げて、お気に入りのワンピースに身を包み、買ったばかりのつば広帽をかぶって、ぶらぶらと。そんな私の一人歩きには、うってつけの天気のよさと、きらきらとした太陽の日差し。片手で日をよけながら、私は空を見上げて目を細めた。まぶしい。丁度昼ごろだからだろうか、空高くまで上がった日差しに手をかざせば、きらきらとした太陽光を浴びて手のひらを流れる血液の色が透き通って朱色に見えた。とてもきれいだ。いきている。 私がスリにあったのは、それからしばらくしてからだった。オシャレなブティックを何件かはしごし、それが並ぶ大通りを少しだけ外れた脇道にあったカフェに入る。思えばそれがいけなかったのだけれど、気づいた時には右手にあったカバンは無くなっていた。先ほどぶつかっていった男がその拍子にスっていったらしい。カバンを盗られてしまうなんて何と間抜けなのだろう、と落ち込みながら私は「スリよ!」と叫ぶ気力もなくして落胆していた。それでもカバンへの執着心が薄いわけではないので、ぱたぱたと男を追いかける。「すいません! スリです!」 男が袋小路かと思った脇道を右に曲がった時だった。私はもうだめだ、と思っていたのだけれど、その時恐るべきことが起こった。右へ曲がった男が、勢いよく吹っ飛ばされてきたのである。私の目の前をびゅん、と通り過ぎて左の壁に鈍い音を立てて激突した男は、ごふ、と奇妙な音と共に血を吐いて、ぱらぱらと壁の破片と共に地面に崩れ落ちるようにして倒れた。とても痛そうであった。私の鞄は、同じように吹き飛ばされてしまったらしく、どうも見当たらない。きょろきょろとしていれば、男の声が聞こえた。ひっと声を上げそうになるのを堪えて物陰に隠れる。 「ったく、何だコイツ。急にぶつかってきたと思えば誰が童顔でチビだって?」 地面にへばりついた男は答えない。ゴス、という音と共に男の腹部に、少年のような男の蹴りが入る。茶色の髪にモスグリーンのような帽子。普通の人ではないような雰囲気をまとっているのは何となく分かるのだけれど、その容姿でずいぶんと普通の人に見える。おそらく、その少年のような風貌をずいぶんと過剰に気にしているらしいことが男の様子から見てとれるので、そこは触れない方がいいのだろう。少年のような容姿の男は、「好きでこんな風にうまれたわけじゃねーっつーの!」とむっすりとした様子で腕を組んだ。その腕に私のカバンがある。あろうことか、あの怖そうな人が助けてくれたらしいが、私のカバンの運命もちょっとここで怪しい事になり始めてしまったのかもしれない。 どうしようどうしよう、とあたふたしてみたが、どうやら男はこちらに気付いてはいないらしいしまだ勝機はあった。何に対しての勝機といえば、私が無事に逃げ帰れる勝機だ。逃げ切れれば勝ちだった。あの人にはあまり関わりたくはないと本能が告げている。見たところ私とそう年齢は変わらないように見えるが、本人が童顔というのを気にしているのならばもう少し年を重ねているのだろう。かといって三十代であろうはずもないと見える。もしかしたらという可能性も無きにしも非ずと言う所ではあるけれど。 「ちょっと、そこの御嬢さん」 「ひいい、すいませんでした! さよなら!」 ばれていた。私はなりふり構わずにその場からもうダッシュで逃げ出した。後の事は知らない。何かに任せればいい。カバンはもうなんとかなるだろう。お金が入っていた気がするけれど、きっとそんなに大した額ではなかった。そう思う事にしよう。あのような物騒な人と関わり合いになるなんて、やっぱり駄目だ。いくらちょっとだけ見た目がよかったとしても、絶対に怖い人に決まっている。だって路地裏で、男を吹っ飛ばしたのだから。助けてもらった(勝手に助けられる形になっただけだ!)のはありがたいけれども、話してしまったら私の人生がなにか少しだけおかしい方向に行ってしまう気がする。そんな事を考えながら走っていたせいか、足がもつれてバランスを崩してしまった。思わず目をつぶる。 「っ……危ない!」 来るはずの衝撃が無い事におそるおそる目を開けば、ぐいっと力強くひっぱられて浮遊感が私を襲う。気づいたらその男に体重を支えられていた。どうしようどうしようと頭の中で警鐘が鳴っている。ぞわりと身の毛がよだつ。顔が近い!「おいアンタ大丈夫か、怪我はないか」 「すいませんごめんなさい大丈夫ですからお金はあげますから」 「は? なに言って……」 「だって…怖い人でしょう?」 少しだけ視界が揺らぐ。どうやら気づかないうちに目に涙が溜まっているらしい。「喧嘩はだめです」と言った私の頬には気づけばぽろぽろと涙があふれていた。 「と、言う訳なんだけど」 そりゃお前、フィーロが悪いだろ。そうだそうだ、という野次が飛ぶ中で私はなぜか『蜂の巣』というお店に来ていた。どうやら彼(この少年はフィーロと言うらしい)はここの常連らしく、あの後に偶然通りかかったマイザーさんという彼の上司(らしい)方に連れられてここまで来たと言う訳だ。道端でぼろぼろと泣いてしまったのはとても恥ずかしい事だとは思うのだけれど、この人もちょっと怖かったしあのままマイザーさんのような紳士的な人が通りかからなかったらぐだぐだしたままだったと思う。というかカバンも置いて逃げて帰らざるを得なかったかもしれない。ちょっと不信感は残りながらも、まあ根っからの悪い人ではないという事が分かっただけでもよかったと思う事にする。 「怖かったね、もう大丈夫だよ」 ぽんぽん、と私の頭を撫でてくれるマイザーさんはにこにことして優しそうだ。店に入って帽子を膝の上に乗せる私の周りには、それでも堅気ではない人たちと思しき人が何人かいたのでやっぱり少しだけ怖いと言えば怖いのだけれど。「君のカバンもフィーロが取り返して無事みたいだし、君も怪我をしていないみたいだし良かったよ」 「ありがとうございます」 ばつの悪い私は、少しだけ俯いて答えた。 「それにしても、フィーロもついに色恋沙汰に巻き込まれるようになったのかと思ったんですが、とんだ勘違いだったようですね」 「なっ、マイザーさん!」フィーロくんが慌てる。「そういうのやめてくださいよ!」 「誰だってあの状況を見れば、ねぇ? フィーロくんが悪いように見えますよね」 わいわいと騒ぐ中でちらりとフィーロくんを見れば、偶然にも少しだけ目が合って、これ以上気まずくなるのもアレなのでちょっとだけ笑顔を作ってみる。ちょっと引きつっていたかもしれないけれど、フィーロくんもちょっとだけ笑ってくれた。何笑ってんだよ、とフィーロくんに対してか私に対してかわからないような野次がとんできて、ちょっとだけこんな日常もいいか、と思ったそんな日。
まるでハッピーエンドみたい
(20120708:▲) 「大丈夫か、毛が無いか」って一発変換で出てきたときにはパソコンに石を投げそうになったしフィーロくんの失礼さに全私が号泣しリクエストの甘い空気が吹っ飛んでいったという最悪の事態になった初フィーロくんで研究しすぎた末にキャラが迷子。リクエストありがとうございました。 |