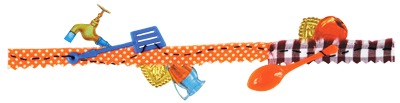 まじかよ、と誰かが単語を繋げるようにぎこちない発音で言った。誰かは分からなかったがおそらくの推測は立っている。 「それがどうかしたのか」と問いかければ別に何も、と反応が返ってくる。心拍数、脈拍共におそらく正常値ではなく、目が泳いでいた。挙動も不審だった。その時点で『別に何も、』であるはずはないことは誰の目からも明らかである。だからなんというのだ、という訳でもないのだが、だいたいどうしてこのような状況に陥ったのか、俺にははなはだ疑問でしかない。しかし仮説は事実であるということが証明されたので俺の中でのひとつの疑問は解決へと誘われたということになる。すっきりだ。さて、先ほどの返答に関してだが、そもそも質問をしてきた事柄に対して返答をしただけにもかかわらず、どうして相手が挙動不審になる必要性があるのだろうか。可能性としてあげられるのは、第一に俺に彼女がいるという事実を受け入れることができないこと、第二に考えたくはない可能性として相手が俺に好意を持っており少なからずショックを受けたということ、第三に彼女という存在に心当たりがあるということ、第四に第三の可能性を仮定して彼女のことを相手が好いていたということ。可能性として考えられるのならば、第一にあげた仮定である可能性が高い。しかし、そこまで驚く程のことなのだろうか。通常この年齢になった男女に恋人がいてもおかしくはない。つまり、恋人がいるという事実上の問題に驚いてるわけではないのだ。では何に驚いているのだろうか。考えられるのは、友人・あるいは身近な人物に恋人ができたことに対して焦りを感じているか、もしくは、できるはずのないであろう男に先を越されていることがにわかに信じがたいと思っているということになるのだろう。まあ、ある程度アルコールが入っているというのも挙動不審の理由には挙がるが、動揺を見るのは易くなる。 ふむ、とひとり頷くと隣に座る風祭が「不破くんの彼女ってどんなひとなの?」と問う。 普通だろう、と口を開きかけて閉じた。今まで普通だ普通だと疑問に感じたことはなかったが、俺とつきあえる時点で普通ではないのだろうか。気づけばもう何年も家に住み着いているような彼女の笑った顔を思い浮かべながら俺は少し言葉を濁して、答える。「いや、目下検討中だ」 「げ、不破の彼女って並大抵の神経じゃもたねぇよなぁ…」 そう漏らしたのは若菜だ。俺の前に座る若菜ももうビールのジョッキが何回か変わったらしく、頬が紅潮しており若干アルコールが回っているらしいことが伺える。「おまえ彼女に感謝しとけよ、女なんかいつヒステリーになるかわかったもんじゃねぇしさ」 「ふむ…、そういうものなのだろうか」 「そーそー」ケラケラと若菜が笑う。 「それって結人の彼女だけだろ」 「ばっか、かじゅまちゃんの経験の低さじゃわかんねーって」 「それは結人がいかに顔だけで選んでるかの証明になるんじゃない?」 「なんだと英士! じゃあ英士はないのかよ!」 「ないね」さらりと安いワインを飲みながら交わす郭に若菜が詰め寄っている。 さて酒のすすむ席で、東京選抜の面々の男ばかりが集まりだらだらと話し込んでサッカーの話題もそこそこ尽きてくると自然とこの流れになるということは誰かに聞いたことがあったのだが、実際に来てみるのは初めてだったので実証するに至らなかった。しかしながら、風祭に誘われてきた今、その仮説は事実であるということが頷ける。結論として、話題が尽きはじめた頃には『色恋沙汰に関する話題』が多く持ち寄られる事が証明された。しかし、では他の飲み会などではどうなのだろうか。行く機会があまりない俺にとっては、滅多に検証しに行くことができないのがもどかしい。 「そういえばアイツはいままでにヒステリーを起こすようなことはしたことがないな……」 「えっ」 「む…では、質問だが風祭はヒステリーを起こすのか?」 「ううん…僕はあまりないかな」 「あまりということは、少なからずあるということだな?」 「まあ、ヒステリーってほどじゃないかもしれないけど怒ったりすることはあるよ」 「そうか、ではやはり怒るという負の感情がすっかり抜け落ちているのかもしれん」 彼女という俗称にしばられているではあるが、他人に対しても自分に対してもヒステリックに怒鳴り散らしたり泣きわめいたり叫んだりしないことに変わりない。落ち込むことはあるのかもしれないが、表面的にそう言う面を出すことは極端に少なかった。ふと、新たな疑問が沸き上がってくることに気づく。 「そうかな?」 「というと、どういう事だ。お前は何か分かるというのか?」 「ううん、ちょっと僕の考え方なんだけど。それってため込んでるだけかもしれないよ」 「俺が頼りにならないということか?」 「そうじゃなくって…ええと、何て説明したらいいのかな」風祭はあわてたように否定すると、「心配かけたくないんだよ」という。 ふむ、まあその可能性も無くもない。は日本人らしい日本人だ。ヤマトナデシコと称される類の俺の後ろに三歩下がって付いてくるような特徴もある。自分のことで心配をかけ、俺が熱中しているものの邪魔をしたくないのだろうか。だからといって、俺は彼女のことをないがしろにしている訳ではない。しかしそれが自己満足であったとしたら、という可能性を考えて俺は頭を振った。 「わからん、どういうことか説明しろ風祭」 「ええと……」 目を泳がせ始めた風祭に、隣の水野が助け船を出した。「わからないなら彼女に聞けよな、彼女なんだろ」 「…そうか…その手があったな……、まあいい。貴重な時間だったが俺は此処で帰宅する」 「え、不破くんもう帰っちゃうの?」 「家に一人で待たせるわけにもいかんだろう」 後ろからいろいろな野次が飛んできたが、幹事の渋沢に代金を払って俺は店をでた。帰ったらどうやって証明させるか。自然と口元がゆるんでいく。
エデンの沈黙
(20120628:▲) ヒロインが愛されすぎて不在というよくわからない事態いちゃらぶしてるのを求めてらしたらすいませ…こういう話の不破君は書いててすごい楽しかったですリクエストありがとうございました。 |