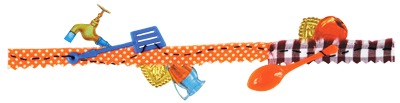 蜃気楼がゆらゆらとゆれている夏の暑い日。こんな日に雪が降ればいいのに、と突拍子もなく考えながら、そんな事絶対にありえるはずなんてないのに、ちらちらと脳裏をよぎるのは、この夏の暑さのせいなのかもしれない。暑かった、部屋の中にいてもじっとりとまとわりつくような熱気と湿気。どこへ行っても逃れられないような暑さに脳までとろけそうだ。とろとろ、流れ落ちていくような脳髄。沸騰したような頭の回転の遅さに、私はごろりと部屋の畳にころがった。 「熱い、とろけちゃいそう。どろどろアイスになっちゃう」 そういった所で暑さが和らぐわけでも、増すわけでも無い。自覚することによって暑さが肌に余計まとわりつく気がするだけかもしれない。それでも熱いと言わなければ何だかやってられない気がして、もうどうにでもなればいいと私はけだるい上半身を起こした。どうせ転がっているならアイスでも食べながら転がりたい。シャリシャリのアイスがいい。氷みたいなシャリシャリアイス。冷たくて、甘くて、ちょっとだけパチパチと口の中で弾ける。 「アイス食べたい」 思い立ったら吉日。アイスを買いに行くことしか頭にない私は、ことわざの意味が合っているか間違っているかなんてそんな些細なことはもうどちらでもよかった。ただアイスを食べるという自身の食欲の為に動いているだけのただの動物のようなものだった。少なくともこの時の私はそうだった。私はくるりと勢いよく跳ね上がって机の上にあった財布をひっつかむと、ばね細工のように勢いよく外へと飛び出した。 外はじりじりと照りつける太陽が大地を焼くような熱を放出しながら天から見下していた。本当に迷惑だ。私は手をぱたぱたとしながら気休め程度にしかならない風を起こす。ぬるい風が頬をかすめて何だかとても気持ちが悪かった。そもそも湿度が高い事かもはや耐えられない。額を流れる汗をぬぐうと、ふと前から涼やかに歩いてくる人影を発見する。わたしは瞬きをぱちぱちと繰り返す。どうやら蜃気楼の類ではないらしい。ぼんやりと突っ立っていたのだろう、気づけば10メートルもしないところに、その人は立っていた。暑そうな長い髪は、さらりとわたしをあざ笑うかのように揺れている。不覚にも、すこしだけどきりとした。 「こんなところで、偶然だな」 「どうも、ネジさんは何をしに行くんですか?」 ふっと口から出たのは社交辞令だった。わたしはただ干からびないためにアイスを買うだけなのだけれど、きっとこの人はこんな暑い日にも修行をしているに違いない。なんといってもわたしとは違ってとても優秀なのだ。優秀と平凡な劣等生は日ごろの生活の仕方から違うのだろうか。それを続けようとしてもイマイチ続かない時のほうが多いわたしは、いったい何様のつもりなのだろうか。 「アイスを買いに」 その言葉が一瞬、自分の口から出たのではないかと慌てて口をふさいだ。 「えっ?」 この優等生がアイスを食べる? 本当に? 「アイスを買いに来たんだ。ほら、そこの店のだ」 「えっ?」 ネジさんの指をさした方向を見れば、その店はわたしたちのすぐ隣に鎮座していた。いつの間にわたしはこんなところまで来ていたのだろうか。ネジさんに気を取られているうちに、少しだけ距離感をつかみ損ねていたらしい。わたしははっとして、「わたしもその店にアイスを買いに来たんです、偶然ですね」と、髪の毛を耳にかけながらへらりと笑ってごまかした。上手く笑えているだろうか。 扉をくぐれば、ひんやりとした空気が流れてくる。「涼しい、」わたしの口からおもわずぽろりとこぼれ出てきた言葉は、偶然にも隣にいた優等生が同じことを思っていたらしく同じタイミングで見事ハミングすることになった。少しだけ息苦しさが楽になって、わたしは一直線にアイス売り場に向かった。適当に棚を開けふたつみっつ手に取るとレジのおばさんに「これください」と差し出した。わたしは一刻も早くアイスが食べたいのである。この際味は問わなかった。お金を払い、受け取ったアイスを一つ、さっそく袋から取り出した。木の棒に刺さったアイスをぱくり、とかじりつけば口の中にさわやかなソーダの味が広がる。ぱちぱちと下の上で氷が解けていく。 「じゃあね、ネジさん」 「またな」 そんな短いやり取りの後で、すこしだけ親近感を感じている。それどころか、今までろくにに話してもいないのに、じゃあな、と片手をあげる彼のしぐさが、それから、偶然だな、と言いながら笑う表情が。今まで気にならなかったことが、どんどん気なって仕方ない。しゃりしゃりとわたしの口の中でとけていくアイスのように、わたしの心もとけているのだろうか。ネジさんに、じわじわと内側からとかされているのだろうか。どきり、と心臓が震える。ぺしゃりと地面に落ちるアイスが、まるでわたしの心をあらわしているみたいで、そのアイスの当たりくじが当たったこともいつもならすごくうれしいはずなのに、全然喜ぶことが出来なくて、わたしはアイスの当たりくじを袋に突っ込んで、思いきり家まで走った。 まさかそんな、そんなことなんてない。 家に着いたころには、アイスは半分がどろどろの液体になっていた。チョコレートアイスに至っては、表面のチョコが無いという大惨事で、わたしはそれを一気に口に押し込んで、木の棒をひき抜いて、一緒にごくりと飲んだ。コーラとチョコレートが器官で妙な味になる。うっ、と呻いてわたしは急いでキッチンへと向かった。コップに水を注いで、一気に流し込む。生ぬるい水が、ぬるり、と喉を通った。そのままへなへなと床にへたり込んで先ほど飲むように食べたアイスの棒を見れば、それは2本ともあたりの文字を主張していて、ああ、当たったんだな、とぼんやりと思った。ああ、わたしネジさんのこと、やっぱり。 わたしはあたり棒をそのあたりに投げて、そのまま床に転がった。多分私の心はどろどろに蕩けていた。アイスも液体から沸騰するくらい、意識したら全部ふっとんでいくぐらいに。アイスと一緒に落ちていく。 「ああ、やっぱり好きだわ」
夏の空が落ちていく
(20120628:▲) 久しぶりにナルトからネジくんを呼び出したけどこの人いつかいても動かない奴だ…/(^o^)\ |