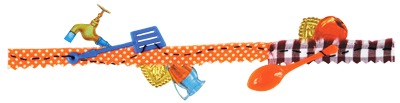 ぐるりぐるりと回るようなめまいに私はふらりと今まで保っていた体勢を崩して重力に逆らえず地面に伏した。ばたん、と音がしてくるくると視界がぼやけては、きえていく。どうやら倒れたらしいと気づくのに数十秒も要した。だって自分が熱にやられるだなんてみじんも考えてはいなかったのだから。私はぼんやりとする意識の中で、死ぬのか死なないのかを懸命に考えていた。もしここで私が死んでしまったとして、私がこの先準備して手に入れるはずだった将来を手に入れられないのは実にもったいないと思う。とても現金なのかもしれないけれども、私は自分自身の未来がつかめなくなるなんてとても、いやだ。 (誰かが懸命に私に声をかけている) けれども私には、その感覚すら事実であるのかがあやしいのだ。ぼんやりとしていた。虚像のように実態がつかめず、私が手を伸ばしたら遠くへとすり抜けていってしまいそうなくらいに。おとこの人だろうか、髪は短いように見える。黒っぽいような髪で、きれいな瞳をしている。誰だろう、とぐるぐる考えているとふわりと浮遊感が私の体を襲った。まるで空を飛んでいるみたいに自分の体が不意に軽くなった。ああ、もう死ぬのかもしれない。うすぼんやりとした意識の中に、わたしはずるずると引き込まれるように沈んでいく。海底に引き込まれる感覚に、似ているのかもしれない。実際に溺れたことは一度もないのだけれど、きっと海の中はこんな感じなのだろう。ふわふわと、でも確実に下へと、重力に逆らえずに落ちていくのだ。私は短い高校生活にも普通の人にしては少し短い人生にもさようならを告げようと、少しだけ覚悟を決める。 だとすれば、なんのための努力なのか。 自分を幸福にせず、誰を幸福にするのか。自分から進んで何か事をなさなければ堕落していく世の中だからこそ私は強くなろうと決めたのだ。なのに熱ごときにうなされて倒れているなんて世の中にとってはいいざまなのかもしれない。いや、もしくは、それ以下の無関心を貫き通すのかもしれない。それならば、本当に私はどうして生まれてここにいるのか、ただ怠惰に過ごすためだけに生まれてきたわけではないはずだった。だからこそ、何か一つでも心にのこりそうなものをつくれたらきっと私はそれでいいのかもしれない。少しだけ光が見えたような、気がした。 誰かが私を呼んでいる。 頬に鈍い感覚。 うう、と意識が、視界がまた現実だろう世界に戻ってくる。だれそれが人間は考える葦であると、有名な言葉を残していたけれども私はその考えが非常に的を得ている考えだと思う。考えて行動し、コミュニケーションを図り、言葉を用いる。思考があって感情があり物事の分別ができる、それが誰かの自己保身に過ぎなかったとしても本能的にそんな行動をそれとなくとっているのは人類の不思議だと私は思う。 「大丈夫か」 そんな声に私は起きる。ちらりとその声の主の方を見れば、まつ毛の長い少年だった。綺麗な瞳をしている。視たことのあるような顔だな、なんて思ってふと気づく。私は廊下で倒れたはずなのに、下にある感触はとてもやわらかくベッドシーツのそれだった。消毒液独特のにおいが鼻につんとする。私はゆっくりと、ぐわんぐわんとなる頭を持ち上げながら半身を起こした。 「おい、そんなに早く動いては……君は倒れたんだぞ!」 「大丈夫、少しなら平気」 わたわたと私を止めに入る少年は私と同じクラスの椿君だった。副会長である彼がとても堅物であり正義感に強い人物だと言うのは皆が知っている事実であり、彼自身が誇っていもいいくらいに立派な事だと私はぼんやりとしながら思った。 「椿君、椿君が運んでくれたの?」 恐らく当たり前の事であろう事を確かめる私に、椿君が少しだけ眉をひそめる。「君はそれでも高校生の女子か」「ちゃんと食べているのか」なんて一人暮らしの女子大生にかけるような台詞が彼の口から飛び出してくる。「……身長の割に軽すぎるぞ」なんて、父親からならわかるけれどもまさかクラスメイトに言われるなんて思っても見なかった事で、私は思わず目をおおきくみひらいてぱちぱちと瞬きを繰り返した。少しだけ驚いた。その私の反応を見た椿君がまた驚いて肩をびくりと揺らす。 「た、倒れている生徒をほおっておくわけにはいかないだろう!!」 彼は「失礼する」なんて言って、早々に保健室を出て行ってしまった。保険医の先生が、「あなたが目覚めるまでずっとそこにいたのよ、お礼きちんと言ってらっしゃい?」なんていうものだから、私は少しだけ恥ずかしくててれくさくてくすぐったいような気持で失礼しますとそこを出た。
そこに理想はない
(20110816:▲) 椿くんらぶ! |