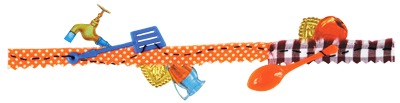 不破君は私を見つけるとこちらへ近づいてきた。 私が電信柱にもたれかかるのをやめて彼に軽く手を振ると、不破君は口元だけ笑って白い息を吐き出しながら「早いな」と言った。不破君が笑うなんていう彼と話す以前には殆ど見られなかった貴重なシーンも、こうしてお互いの用件に付き合って行動しているうちに徐々に見られるようになった…ように感じる。他の人に話しても気味悪がられるだけなので話そうとは思わない。私だけ知っていればいいなんて傲慢な考えと葛藤しながら、私は首元に巻いたマフラーに顔を少しだけうずめた。 「ちょっと早くついちゃって」 「そうか」 そんな他愛も無い会話を繰り広げながら、私たちは今日の目的の場所へと自然と歩みを進めた。 目的地は、本屋。一言に本屋と言っても今回の場合その一軒だけではなく、五・六件の本屋をハシゴして回るちょっとした『本屋めぐりツアー』のようなものだ。 事の発端は私が「本屋にでも行こうかな」なんて図書室で呟いた独り言を不破君が隣で聞いていたという偶然。不破君と共に本屋をめぐる事になった。私個人としては私の目的の本なんて一軒回るだけで見つかると鷹をくくっていたのだが、不破君曰く、現在その本の書店入荷率は極めて低いということだった。私が残念だとでも言わんばかりの顔をしていると、彼が知っている本屋を紹介すると親切にも案内してもらう事になったのである。 「一軒目は何処の本屋に行くの?」 「武蔵野森中周辺にある古本屋だ」 「あったまいい! 確かに古本屋なら見つかるかもしれない。あの本、発行年度も古いし」 「当たり前だ、俺の頭が悪かったら俺以外の奴はどうなる」 「そうだね、みんな馬鹿になっちゃう」 くすくす、と控えめに笑いながら私は彼の表情を伺う。無愛想だとか無表情だとか言われながらも若干の表情の起伏があるのが彼で。それが少し分かるようになってきた私は、彼と話しているのが楽しくてしかたなくなってきてしまった。ただそれだけのことなのかもしれないけれど、確かに不破君に現在進行形で恋をしているような事は確かで。自覚なんてしなければ良かったのに、なんて今さら思ってももう手遅れだった。 「着いたぞ」 と、不破君の声。私がおお、と感嘆の声を上げてその古本屋を見上げれば、中規模の店舗が眼前に広がっていた。私が大きいね、なんて言いながら彼を振り返ると普通だろう、と単調な返事が返ってきた。 「あ、この本とこの本、探してた本だから買っちゃおう」 「ふむ、作者買いか。ちなみに右手の本よりも左手の本のほうが比較的演出が凝っていたな」 「そうなんだ」そして一拍遅れて、彼の言葉の意味に気づく。「あれ、不破君もこの本読んだの?」 「二年前に一度読んだな」 「ふうん」私は本棚から本を物色しながら、目当ての本を探すがなかなか見当たらない。 「こっちには無いな」 そんな声が聞こえるので、不破君のいるところにもどうやら私の探している本は無いようだった。私はもう二・三冊棚から良さそうな本を抜き取ると、場所を移して目当ての本を探す。一段目、二段目、三段目、四段目……と探してみたが、こちらの棚にも無いようだった。不破君のほうを見ると、首を振って「無い」と一言。一通りぐるりと店内を捜索したが私も不破君もノー収穫だった。目当ての本よりも優先順位の低い本ならば何冊か見つかったのだが。 「そっか、」私はため息をつくと、この古本屋で見つけた本たちを会計へと持っていく。店の店主と思しきおじさんは気さくな笑みを浮かべていらっしゃいませ、なんて人の良さそうな態度で接客してくれた。私はリュックの中に本を詰め込んで不破君と共に二件目に再出発した。 二件目の本屋は、一軒目の古本屋から歩いてすぐの所にあった。普通のオーソドックスな本屋である。オシャレな照明器具が店内に配置されており、都会の本屋と言う感じがした。先ほどの古本屋はいかにもな感じの古本屋であったが、それにしても本屋同士がこんな至近距離で営業妨害ではないのかと思えばそうでもなかった。二件目の本屋は先ほどの本屋と同じぐらいの数の客が点々と存在している。まあ近日は若者の活字離れがどうのこうのとか話題になっているくらいだから、本屋に入る客の数も少ないのだろう。まあ、ここの本屋は外装からも伺えるように比較的年齢層が低いようにも思える。十代から二十代前半の客の影がよく目に付いた。と、そこで私は不破君と一緒に即座に目当ての本がおいてあると思わしきコーナーへと向かったのだが、どうやらもう既に誰かに買われてしまったようだった。そんなに人気の高い書物だったとは思えなかったので、今回は運がなかったね、なんて彼と話しながら次の本屋へとハシゴする。しかし、その次の本屋も似たような結果に終わり、最終的に今回の最終目的地である六件目の本屋まで彼をだらだらと連れ歩く事になってしまった。 「不破君、ごめんね。何か凄く見つからなくて」 「なぜ謝る必要がある、は悪くは無いだろう」 「いや、だって私が案内させてるでしょ?」 何だか見つからないと申し訳ない気がするの、と私が言えば彼は分からないと首をかしげた。 「では休めばいいだろう」 「あ、いや、そういうことでもなくって!」 「ではどういう事だ?」 「え、えっと、不破君迷惑じゃないかなって思って!」 「何がだ」 ぐいっと顔を近づけてくる不破君。威圧感がある。が、しかしそれ以上にそんな事をされてはこちらの心臓は持ちそうも無かった。私は、その一言に降参の白旗を揚げて不破君に話しかける。私の負けです、だってもう近いんだもん! 「不破君が疲れてないかと思って…! その公園に自動販売機があるから、ちょっと休んでいこうよ」 「やはりな。心配は無用だ。そういうことなら初めからそういえばいいだろう」 不破君に完璧に打ち負かされた気分である。しかし、悪い気はしない。私は自動販売機の前に立ち、ホットの缶コーヒーブラックのボタンを押す。不破君も私と同じコーヒーのボタンを押して、缶のフタを開ける。パシャ、という缶を開ける音がして中から湯気が出てきた。そういえば手の感覚が無くなっていたな、なんて思いだす。急激に変化した温度に耐え切れず、じんじんと手がかじかんだ。コーヒーを一口啜ると、その独特の香りと味が口の中に広がった。美味しい。 「あったかい」 「ホットだからな」 「手がね、冷たかったから」 私が右手を『ぐー、ぱー』と握ったり開いたりしていると、ふいに不破君の左手が私の右手を掴んだ。 一瞬の出来事に思考回路がショートする。コーヒーの味も分からないくらいに味覚まで混乱している。 「え、っと。どうしたの不破君」 私は今ある語彙を繋ぎ合わせて何とか言葉に搾り出した。不破君は当然だとでも言うように私の手を平然と握っている。私の頬が高潮しているような体温が上昇しているような恥ずかしさのあまり何なが何だかもう分からなかった。 「握っていたら暖かくなるだろう」 「え、うん、そうだね」 「しばらく、こうしていれば暖かくなる筈だ」 私は言葉を出す気力も、余裕も無くなって、俯いたようにうなずいた。顔なんて上げられるわけが無い。だって不破君が近くにいるから。 其れでも私は幸せだった。 理由はさておき、大好きな人と手を繋いでいるんだから。 (20091027:ソザイ |