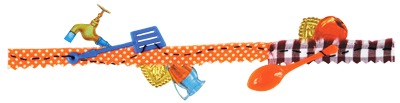 「トリック・オア・トリート」 信じられないと言う言葉が真っ先に出てきた。まず目を疑った。俗物的な話題にこれ以上不釣合いな人がいるだろうかと聞かれれば即答するだろう、イエス。まさしく不釣合い極まりなく、何だコイツ、と言わんばかりの目で私は彼を見ていた。 信じられない、まさか本当に来るなんて思いもしなかった。 彼はニヤニヤといやーな笑みを浮かべている。(どうしようかな、お饅頭まだあったかな)なんて思っていると「何だ、いたずらしてもいいのか」なんてつけあがった彼が言うので私はイライラとしながら部屋にあったお饅頭を彼に向かって投げた。ぱん、と左手で彼はお饅頭を受け取る。 「なんだ、つまんねェじゃねぇか」 「うるさいな、もう」 みんなもう来た後で、お饅頭も残り少なくなってきていて(というよりもみんなわざわざ来ると言うのが信じられない、)こういった俗物的な行事に対しては驚きの出席率といったところで、あのイタチまで来たのだから他の奴らがこないはずが無いと思って構えていたら、このサソリが来た時点で全員出席だった。 なんてことだ、予想外だ。 「オレで最後だそうじゃないか、ククク」 私は相当むすうっとした顔をしていたらしくサソリはヘラヘラっと笑う。見てくれがこんな幼いくせに、オッサンだなんてとんだ詐欺だとたまに思う。まあ、そんな事を言ったら私の家族は全員が全員年齢詐称の罪で起訴されてしまってもおかしくはないのかもしれない。一番可笑しいのはおばあ様だ、なんて思うと少しだけ表情が和らいだ。 「まあ、そうね」 私が言うと、「ほらよ」とサソリが何かを取り出して投げてよこした。なんだこれ、と思ってみれば何かの包みである。 「団子だ、オレは別に食っても消化されねェからな」 じゃあなんでお菓子を要求するんだ、という頭の中の突っ込みは誰にも聞こえることも無かったけれども、まあありがたく受け取っておくとしよう。 「じゃーな」 「うん、」 去っていく後姿をぼんやりと追いながら、少しだけいいところもあるのかもしれない、とか思ってしまった自分に少しだけ自己嫌悪する。悪い悪いと思っていた奴が少しだけいい事をすると何だか途端にいい奴に見えてしまう効果を映画版ジャイアンの法則、とかなんとかどこかの書物で読んだような気もするけれど、これじゃあ。 まるで、喜劇じゃないか。 私はそのままドアを閉めて、ベッドにごろりと寝転ぶ。あまりふわふわではない、その少しだけ硬いベッドにも慣れてしまった。ああ、なんて皮肉なものなのだろう、こんな生活に慣れてしまうなんてなんて悲劇なんだろう。けれども一度決めた道だ、私は彼を守る為なら何でも出来る覚悟でいるつもりだ。 騙されやすくなったものだ、と私は哂う。 それでも、せめて (20100409:ソザイ |