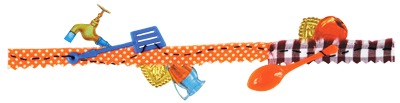 運命と言うのは一体誰が決めているのだろうか。そんな事は誰も知る由も無い。 運命は生まれた頃から定められているという云われがあるが、そんな確証は無く、ただの根拠の無い言いがかりに過ぎない。無能無能と連呼する向かいのネジが私の事をどう評価した所でそれは私の知った所ではなく、秀才が秀才であることの何が悪いと文句をつけたくなったがやめておいた。下手に言いがかりをつけてまで彼に喧嘩など売る必要も無い。そもそも、そのような無益な行為をすること自体が私にとって損害だった。よって、私は今も平凡な一般家庭の忍として目立つ事も無く非難されて罵倒される事も無く暮らしている。 それが普通だからだ。 究極に究極を重ねた普通を求めて何が悪いと一度恐れ多くも彼にけんかを売った事があったけれど、それは私が何も知らなかった頃の幸せな話。唯一普通ではない所が、私の家は日向家の向かいにある一般家庭だったということだった。どんなにそれを恨めしく疎ましく思ったか知れないけれど、物心つく前の私は何の疑いも無く、何の穢れも無くただただ彼が「すごいひと」だということを信じきっていた。 実際問題、私が彼と話したことは無かったけれども何となくクラスでも浮いたような存在だったし、私も彼とは違った意味で浮いた存在だった。彼については語るまでも無くきっと周知の事実だろうが私の事は別段どうって事もなく、唯の『グライダー人間』にすぎなかった。言われた事しかできない、言われた事しかやらない。それ以上でもそれ以下でもなく、応用発展機転を利かせない。ただ唯一、先生を唸らせたのが『教科書通りの事をまるでそっくりそのまま完璧に出来た事』だった。 「じゃあ次の『変化の術』の見本を、さんにやってもらおうか」 「「お願いしまーす」」 いつも、私だった。テストの一番難しい所は、決まって私に順番が回ってきた。まるで先生が仕組んだかのように、いや実際のところ本当に仕組んでいたのだろうが、誰かが回答に詰まるといつも私の出番だった。くのいちではずば抜けた才能を持っていると言われ、何かと先生の間では私の事が話題になっていたとかいないとかそんな話だけれど。 さて、そんなごく普通のくのいちである私と、彼が初めて話したのは一番初めにあった合同授業の事だった。当然、実力差によって班員は振り分けられ、全員の実力が平均的に同じぐらいになるように調整される計算となっていたので、私はもちろん日向家の天才様とは違う班だった。同じ班になった班員と適当に自己紹介をして何となく苗字だけ覚えたような覚えてないような、その場限りの記憶力を発揮させる。もう今は思い出せないけれど、この実習は三人組で走りながら的に起爆札を命中させるという、至極簡単なものだったという事を覚えている。 「いっくよー!」 そんな無駄に元気な男子と一緒の班になってしまって、「うん」と頷く私。 「僕に出来るかな…?」 とか最初に声を上げた男子とは正反対の、短髪の地味そうな男子が不安げにこちらを見てきた。 「大丈夫じゃないかな?」私は適当に笑顔を見繕う。「やればできるよ」 私の成績にまでこれが影響するなんて信じられない、そんな事を思いながら足を引っ張るなよ。なんてずるい事を考えながら私はこの試験に臨んだ。まあ結果は私一人でやるよりもはるかに点数が劣っていたが三人の連携が取れていたとかいう先生のとても優しい心遣いによって、随分と点数が跳ね上がったことに私の心は躍った。 「やったね」地味な少年が私に微笑みかける。私も嬉しかったので笑いながら頷く。 その横を「くだらない」なんて通り過ぎていったのが、日向ネジだった。 「え」地味な少年が表情をゆがめた。日向ネジの後姿が遠ざかっていく。 「気にする事無いから」私はここで泣かれたらまずいなんて思いながら彼を慰める。「きっと負け惜しみだよ」 「でも、」地味な少年は首を振る。「ネジ君、僕たちより点数高いよ」 彼の点数を聞けば、私たちの班の点数よりもはるかに高くて。その時の私は悔しいと思うよりも先に、凄いと思ってしまった。と、同時になんて奴だとも思った。皆一様に彼の事を羨望と嫉妬のまなざしで見つめているようなそんな感覚が脳裏をよぎって、其れでも私は単純に『すごい』としか感じなかったのだからなんて語彙の少ない頭の弱い子供だったんだろうと今でも悔いる事がある。 そこで、私はあろう事か彼に話しかけてしまった。一生分の後悔とはこのことを言うのだろう。 「すごいね!」 「当たり前だ」今思えば、子供の癖に生意気すぎる!なんて思うけれどその時は特に何も思わなかった。 「うん、でもすごいよ」 「少し黙っていられないのか、」 口ではそういいながらも、すごいすごいと捲くし立てられて、ちょっと気分を良くしたのか悪くしたのか分からないが、彼は私の名前を読んだ。当時の私は嬉しかったのだろう、嬉しさと名前を呼ばれた恥ずかしさとでよく分からない表情をしていたと思う。 「ごめんね、五月蠅いよね」 「目障りだ」 そしてまたしてもあろうことか私は人生最大の過ちを犯した。 「うん、でも自分に出来ない事ができる人ってすごいひとだとおもうの」恥を知らない私はにこやかに続ける。「だから、ネジ君ってすごいひとだよね」 そんなアカデミー時代の私の阿呆な一言で今この良く分からない状況に追い込まれているなんて私はどうしたらいいのか分からなかった。だから子供時代ってのはイヤだったんだなんて思っていても、なんだかまんざらでもないなあなんてしみじみと思っている自分がいた。 「返事を聞かせてくれ」 「そんな事、……急に言われても困るよ」 「駄目なのか?」 「いや、そうとは言ってないでしょ」 先ほどから同じような言葉の押収が続いている。これではキリが無いのだが、まあこれって俗に言う告白とかそんなやつで。そんな昔のことをきっかけに、惚れられてしまったとか急に言われても私は困るわけで。ずっと片思いをしていたとか切実に打ち明けられた所で私はなんとも思っていなかったというかただのすごい人だと思っていただけと言うかそんな感じだったわけで。 「、お前が好きだ」 「考えさせてください!」 私はその場から急いで立ち去る事しか出来なかった。 それにしても、何でこんなに心臓がバクバクとしているのか皆目検討がつかない。理解不能だった。わたしは部屋のドアにもたれかかって座るように崩れ落ちながら床にぺたんと座り込んだ。全く。不意打ちもいいところだった。 やっぱり天才の考える事なんて理解の範疇を超えている。 (20091027:ソザイ |