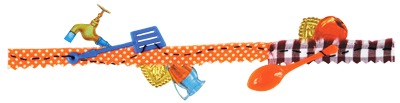 それが我侭だと知っていたから、私は首を振ってその思考を停止した。 だって、彼に迷惑をかけるわけにはいかないのだ。私はため息をついてベッドへと倒れこんだ。いつものように定時調査の時間がやってくる。定時調査とは名ばかりで事実上の尋問検査のようなものだった。私はまた同じ質問の繰り返しに同じ答えを返す。だって答えようも無い。いくら同じ質問をされた所で、同じ答えしか見つからない。アジトの場所はどこだとか、敵は何人いるのかとか。 そもそもわたしはアジトの場所なんてせいぜい二・三箇所しか覚えてはいない。ほとんど外出も許されていなかったに近い状況下だったのでほぼ軟禁状態に近い感覚だった。自ら望んで暁に入ったわけではない。けれども、世話になった義理を返す恩義すら私は持ち合わせていなかった。 私が、部屋に近づいてくる足音に耳を傾けながら、もうきたのか、とベッドから半身を持ち上げた。 しかし、その軽いノックの音は定時調査にくる人のものとは思えないほどに柔らかな音を出している。そして私はささやかな、懐かしいような香りに少し酔いしれた。これは、このドアの向こうにいるのは、おそらく彼だ。私は寝癖がついていないかどうかを確認する。定時調査の人間が来たのならば特に気にしない事ではあるが、もし予想が当たっていたとして仮にドアの前に立っているのが彼だとしたら私はどうしようもなく恥ずかしくて死んでしまいそうになる。 「、いるか」 案の定、その恍惚な声はドア越しに私の鼓膜を振動させた。一気に心拍数が上がるのがわかる。やっぱり彼が好きなんだなとか、今さらすぎる事を考えた後で部屋にいることを、平静を保ちながら彼に知らせる。彼は入るぞ、と言ってドアノブを回してカチャリと開けた。 「どうしたの、我愛羅」 「お前が、元気でいるかどうか見に来た」 カチャリとドアを閉めると彼は柔和な笑みを浮かべた。ぎゅう、っと胸が内側から締め付けられているような、いつも通りの感覚が襲ってくる。彼が天然なのか意図しているのかはともかくとして、それでもそんな事を言いながら暇さえあれば私に逢いに来てくれている事実が嬉しくてしかたなかった。私は少しで模糊の時間が止まって長く続けばいいのになんて甘い考えを脳裏によぎらせながら、彼のほうを見る。 「元気よ、外に出られないけどあなたが来てくれるから退屈もしないもの」 「そうか」 よかった、と表情をほころばせながら呟く我愛羅。私も自然と彼につられて顔がほころぶ。 本当に彼は丸い性格になったように思う。周囲の環境、取り巻いている人々や今現在里長として風影と言う大役を引き受けているという事実が彼に笑顔を与えてあげたんだろうと思うと私は幸せな気分だ。でもきっと、一番彼の事を理解してあげられていたのは、私ではなく木の葉の人柱力であるナルトとかいう奴なんだって思うと少しだけ彼に嫉妬の情が生まれた。私は、次に何を話そうか迷って結局いつも通り他愛のない話題へと切り替える。 「今日も、…いい天気よね。街が平和だわ」 「ああ、本当だな」彼は窓の外を見る。「あれ以来、まだ街への襲撃は無いからな」 「そうね、」私は一連の事件を思い出す。「あなたも元気になってなによりだわ」 「…ありがとう」 ああ、なんて素敵な笑顔なんだろうなんて彼の照れたような笑顔を見て私も微笑んだ。大好きすぎてしょうがないくらい大好きだけど、やっぱり恥ずかしくて言葉に出来ないなんて自分の性格を呪いたくなる。だけどやっぱり私にはこの人がいないと駄目だった事を思い知った。 せめてこの時間が少しでも長く続きますようになんて甘い考えをもう一度持ってしまった私はもうどうしようもないくらいに彼に依存していた。 (20091022:ソザイ |