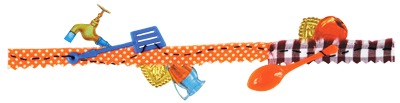
どれくらいの時間、 どれくらいの距離、 どれくらいの想いで。 私にとって明らかに足りないのは時間だった。 引っ越すまで、今日を入れて後三日。 それを告げられたのが、今日。 引越しをすることを私が知ってから、引越しをする日までの日数が明らかに少なすぎた。 全て親の都合で決められる訳にはいかない。 だから私は、引越しの準備の最中にこっそりと抜け出して、幼馴染である彼の家に向かった。 今日が金曜日だから、ここを離れるのが日曜日だ。 下校してから知った事実。今からクラスの友達に知らせるのは、少々私にとって荷が重すぎた。 だが、彼ぐらいには別れの言葉ぐらい言っても罰は当たらないだろう。 私はそう高をくくったらしい。 彼の家の前でたちどまり、ドアホンを鳴らす。 普通の金銭感覚を持つものから見れば、この家はなかなか良い家の部類に分類されるものだった。 だからと言って、豪邸と言うには少し劣る。そんなつくりの洋風な家だ。 『どちら様でしょうか』 彼の母親のふわりとした声が、ドアホンのスピーカー部から聞こえる。 私は一拍置いて、名前を名乗った。 「です」 『あら、ちゃん。待っててね、今開けるから』 のほほん、と言う表現の行動のもと、ぷつんとドアホンが切れたような音がして、30秒ほどで玄関が騒がしくなった。 そして、ばたばたと言う音とともに、彼の母親は現れた。 「いらっしゃい! さ、入って入って」 「はい、お邪魔します」 私は、彼の母親、――もとい、杏奈さんが空けてくれた玄関先の門扉をくぐり、ドアを抜けて玄関へと入った。 「その辺に座って待っててね、今紅茶入れるわ」 「あ、はい」 「砂糖とかミルクはいらないんだっけ」 「あ、はい」 私はお言葉に甘えることにして、すっかり座り慣れたリビングのソファーに腰掛ける。 と、目の前にはやはり見慣れた30インチぐらいあると思われるテレビが堂々と控えていた。 「英くん、もうすぐ練習から帰ってくると思うわ。ごめんねー、帰りが遅くて」 「いえ、いいんです。私が勝手におしかけてしまっただけですから」 少しして、杏奈さんが紅茶を運んでくる。 「はい、これローズティーなんだけど」 こちらに可愛らしい金縁のティーカップを差し出してきた。私は、「ありがとうございます」と恭しく受け取る。 と、杏奈さんが時計を見て焦ったように口を開いた。 「あ、見たいドラマ始まっちゃうわ。ちゃん、見ても良い?」 「どうぞ、お構いなく」 そういって私が答えると同時に、杏奈さんはテレビの電源を入れてチャンネルをいじっていた。 ドラマ、と言うのはよく昼頃にやっている火曜サスペンスのような刑事ドラマだったようだ。 私の母親もよく同じシリーズの刑事ドラマを見ていたのでなかなか人物関係についていくことができた。 杏奈さんは、テレビに夢中で真剣なまなざしでテレビに釘付けになっている。 それをまるで子供のようだなと思ったのは、まあ、気にしないでおこう。 「ただいま」 と言う声とともに、この家の息子が帰ってきたようだ。 「あ、英くん。お帰りー」 ぱたぱた、と席を立って玄関に向かった杏奈さんのスリッパの音が木霊する。 ドラマは今丁度、宣伝にはいったところだった。 「ちゃん来てるよー」 「…が?」 「英くんに会いに」 「ああ、そう」 「えー、もう少し喜びなさいよー」 そんな会話をしながらリビングに杏奈さんと、取り敢えず目的の人物である『英くん』こと郭英士が入ってくる。 スポーツバッグが床に置かれたぼすっと鈍い音がした。 「何でいるのさ」 私の座っている三人掛けのソファの隣にある一人掛けのソファに腰掛けながら彼は言う。 私は単刀直入に理由を述べた。 「引っ越すから報告に来たの」 「聞いてないよ」 「私も今日聞いたの」 「無責任でしょ」 彼はそこで溜息をついた。私も本来なら溜息をつきたい気分だ。 「私の両親が、ね」 全く、なにが悲しくて親の都合で引っ越さなければいけないのか。 新しい土地で交友関係を作るのは難しい、と言うよりも面倒臭い事は今までの転校生たちを見ればわかる。 転校してきて数日間、質問攻めにあうのだ。私は自分がそんな事になるなどとは考えもしなかった。 転校生などと言うのは、遠い世界の存在だと思っていたのだ。まさか自分がなるとは、予想だにしない出来事だ。 まあ第一印象が恐ければ寄って来る輩も少なく済むのだが、そうなってしまえば逆に学生として生活するのが大変だ。 生憎、私はそんな位置に落ち着く気はないので普通に目立たないよう、小市民のように生活する気でいる。 しかし考えると心底憂鬱だった。そして面倒臭い。胸に、もやもやとした気分が募る。 どうしようもない、この気持ち。 「で、どこに引っ越すの?」ティーカップを右手に持って紅茶を啜りながら、彼は言う。 「仙台」 「……遠いね」 「でしょう?」 私は苦笑した。 「でも、国内だから会えなくなるわけでもないでしょ」 「それはそうだけど、今よりも減るよ」 「仕方ない事だよ」 彼は、コツン、と私の頭を叩いた。 そもそも、私が郭英士と比較的仲がいいということは、クラス内でとても有名だった。 郭英士というヤツは、――私は知らなかったのだが――どうやら女子に人気の出る体質らしい。 そんな彼に私が近付いて、取り巻きの女子たちに何も言われなかったと言えば嘘になる。 しかし、そこまで酷いことを言われなかったのは、私の性格に少々原因があったらしい。 人に言わせれば、「女子なのに付き合い方が大雑把だ」とか「さばさばしている」とか。 私は人に依存して生きる方ではないので、周りと無理矢理合わせようとは思わない。 そして、人の意見に流されず、左右されない。 それに加えて私が彼を特に男として意識しているわけではないことを察知して、 取り巻き達は『郭英士のただの友人だ』と私を認識したのだろう。 まあ、直接的被害が加わらなければ、私は別にいいのだが。 何もされないに越した事はない。 「じゃあ、私帰る」私はソファから立ち上がる。 「あら、もう帰るの? ――じゃあ英くん、ちゃんと家まで送っていきなさいね」 ぱたぱたとスリッパの音を響かせながら、杏奈さんが顔を出した。 「何言ってるの母さん。一人で帰れるでしょ」 「女の子の一人歩きは危ないのよー」 「はいはい、――じゃあ行くよ、」 「言われなくても、元々そのつもりだから」 こんなやり取りでさえ、遠く離れてしまうのかと思うと、少し切ない気分になったりした。 「寒くなってきたね」 「まあね」 夕方になってきて段々と気温が冷えてきた。 日中はそれほどでもなかったのだが、季節の移り変わりというものは面倒臭いものだと思う。 「」彼が私の名を唐突に呼ぶ。私は、彼を見る。 「何?」 「鈍感だな」 「私が?」少し私は顔を顰めた。 「当たり前でしょ、他に誰がいるんだよ」 「何でよ」 「気付いてないだろ」 「何に?」 いつもに増して、真面目な彼に少し私は戸惑いを感じていた。 「――― 」 それは、一陣の風のように私の耳の左から右へと通り過ぎていった。 「いくら遠くでも会いに行ってやるよ」 「――私だって、会いに戻ってくるわよ」 自覚をしてしまったのは、幸運か不運か。 私が引っ越すまでの時間、どれだけ一緒にいられるかしら。 貴方の側に、いられればいい。 そんな感情を、無駄に自覚してしまった。 別れが辛くなると知りながら。 また、会える日を信じて。 (20070924:ソザイ |