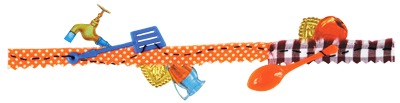
何時だっただろうか、 君と、約束を交わしたのは それは、俺が中学に上がったばかりのある晴れた金曜の午後。 誰も信じていなかった、誰も信じられなかった。俗に言う人間不信というものに俺が陥っていた時のこと。 いつものように学校からの下校をする最中、いつも通りの道をいつも通りのペースで歩いていた。 見慣れた風景や建物、信号、横断歩道。行き交う人の群れ。変わるはずの無かった、日常の風景。 俺が、とある建設中のマンションの前を通り過ぎようとした時のことだった。 何か音がして危ないと思った瞬間には、もう遅かった。頭上から、鉄骨が2・3本加速しながら落ちてくる。 どちらに避けても避けられないような、焦りと死の恐怖。走馬灯が過ぎり、鉄骨がスローモーションのように落ちる。 体が動かなかった。その場に根が生えたかのように足が動かない。 もう鉄骨は目前まで、迫っていた。死ぬのか、と思って目を瞑る。 「危ない!」 俺が「死ぬのか」と諦めた瞬間、叫び声がして僅かな衝撃の後に俺の体はふわりと浮いた。 続いて、がらがらがしゃんと何かが破裂したような、爆発音が響く。 気付けば、俺は生きていた。 真っ先に目に入ったのは、無残にも捻じ曲がった鉄骨。 そして、次に俺の目が捕らえたのは、腕から血を流した同い年ぐらいの少女の姿だった。 「おい、大丈夫か」 俺は少女に向かって声をかける。反応は無い。 「おい、大丈夫か」 同じ台詞を繰り返し、今度は体を揺すってみる。 もう一度同じ台詞を繰り返そうとした所で、少女が、「うー」と呻いた。 生きているらしい事を確認して、安堵する。良かった。 そして、混乱も収まってきた俺の脳は、今の状況について冷静になって考え始める。 そもそも、この少女。何故俺を助けた。顔を見る限りでは、この少女の事を俺は知らない…筈だ。 俺を助けてこいつに何のメリットがあると言うんだ。自らを危険に晒すだけだろう。 理解できない。――こいつは、偽善者なのか。 ただ、座って眼前の凄惨な風景を眺めている俺の元に、工事をしていた若い男が駆け寄ってきた。 「君たち大丈夫かい? 救急車を今呼んだから傷の状況を教えてくれ」 「俺は、大丈夫だが…」そして俺は目を少女に向ける。「こっちが気を失って腕を怪我してる」 男の、少女の傷への処置は早かった。 何処からとも無く救急箱を取り出して、少女の血が流れている方の腕を消毒してから止血をしていく。 「コンクリートでの掠り傷だ。骨折はしていない」 「そう、か」罪悪感からか、自分の情けなさからか俺は視線を上げられない。 「全く誰がやったんだか知らないが、銃弾なんぞ何処で手に入れたんだ」 俺は男がボソリと呟いた言葉に反応する。 「え」 「聞こえなかったか、銃声」男が、驚いたような顔でこちらを見た。 ――そういえば、それらしき音は聞こえたような気がする。 ドラマや映画でしか聞いた事のないような破裂音。パン、と言う乾いた音。 頑丈だったはずの鉄骨を運んでいた紐は穴が開いたことによって、その重量に耐え切れずに切れる。 「…聞こえた、気がする」 俺が言うと、「だろ? 乾いた音がパンってなったろ?」と男はうんうんと頷いた。 少女の治療が終わった男は、立ち上がり道路を行く車を眺める。 「このマンションになんか恨みがある奴の犯行か、愉快犯か」 男は腕を組んで考えながら真面目そうな顔でやはり呟くように言う。「はたまた、君に恨みがある奴か」 そしてこちらを見ると急にケラケラと笑って、「まあ考えすぎはよくねえな」と砕けた口調になった。 「俺は盛永直哉、20歳だぜ。よろしく」 「天城僚一」 俺と盛永さんは、応急手当をした少女を回復単位で横にしておいた。 「テンジョウ? 天に城か?」 「ああ」俺は頷く。 「空飛んでる天の城の映画があったよなー」男が笑う。「金曜9時にやってる映画で見た」 「はあ、」俺は適当な相槌を選んで打つ。「そうですか」 「主人公がトンネルとか通り抜けるたびにだんだん荷物が減っていってもったいないなって思って…」 隣の男、盛永さんではなく背後から響いてきた声に俺と盛永さんは後ろを振り返る。 「こんにちは。大丈夫ですか?」 その少女は、近くの鉄骨に座りながら、ふわりと笑ってそう言った。俺は少し警戒心を抱きながら頷く。 よく見れば華奢な体だった。細い腕に細い足。折れてしまいそうな雰囲気さえ醸しだしていたが、 先程、俺を突き飛ばすだけの力があったということもあり、腕力は意外と強いのかもしれない。 少女が立ち上がると、長いこげ茶色の髪が風に靡く。 同じように少女の着ていた白く、丈の長いワンピースも風に揺れた。白い布地に赤褐色の錆が目立つ。 「そう、ならいいの」 少女は、ワンピースの裾に付いた汚れを払って軽く落とし、何事も無かったかのように立ち去ろうとした。 「ちょっと待った、一つ質問」 と、唐突に盛永さんが少女を呼び止める。 「君、何か恨まれたこととか危険に陥ってるとかそういうこと無い?」 すると少女は少し考えるようにして、 「毎日が危険ですよ」 と、いかにもそれが普通であるかのように、当たり前のことであるかのように言い放った。 「それでは、私は立ち去ることとします。皆さんがもう不幸に見舞われることのないことを願っています」 そして少女は続ける。「私には関わらない方が幸せです」 「あ、あの」気付けば口を開いていた。「名前は?」 「…――」 そして少女は風のように去っていった。 その姿はとても凛として気丈だった記憶がある。その走り去る後ろ姿に、俺はいつの間にか見入っていた。 その後、俺は騒動に巻き込まれないように盛永さんに裏道から逃がしてもらった。 一言礼を言うと、盛永さんは、「いいって気にすんなよ若造!」とか言って手を振ってきた。 そんな事をしたら目立つじゃないかと思いながら、俺も思わず手を振ってしまっていた。 何故そんな事をしたのかはわからない。 でも少しだけ、あの人なら。 あの人なら、他の大人とは違う気がした。 根拠は無い。 ただの、第六感だ。 翌日、俺は学校が休みだったので、俺にしては珍しくぶらぶらと外に出ることにした。 先日の事件現場には警察の現場検証が入っていて蒼いビニールシートと黄色い『KEEP OUT』と書かれたテープが そこかしこに点在している。ようやく、俺は事件だったんだな、と実感した。ただの事故ではない、仕組まれた犯罪。 俺は、気になっていたのかもしれない。 俺を突き飛ばして助けてくれた命の恩人である少女の事が。 あの少女は、一体何者なのだろうか。生まれ持っての不幸体質なのだろうか。 俺には、わからなかった。だからこそ、気になって探した。 けれど現実にそんなとんとん拍子に上手く見つかるはずも無く、彼女に対するどんな些細な情報も俺には分からなかった。 分かっているのは、彼女の名前のみだ。年齢も、何処に住んでいるのかも分からない。 なにも、分からないんだな。 秘密主義者なのだろうかと首をひねる。何か隠さなければいけない理由があるのかもしれない。 「――ち、リョウイチ、僚一!」 物思いにふけりすぎていて気が付かなかった。どうやら後ろから俺の名前が呼ばれていたようだ。 「おーい、僚一!」 振り返れば、俺先程通りかかったばかりの公園のベンチの付近に盛永さんがいた。やはり手を大きく振っている。 その傍らには、先程まで俺が考えていた彼女の姿があった。 ――、 今日は、全体が薄紅色で胸部に白いリボンの付いたワンピースを着ている。 俺はそちらに近寄っていく。 彼女の半径1m程にたったところで、彼女は閉じていた口を開いた。 「こんにちは、天城」 「ああ」俺は思ったように声が出なかった。 「今日は会えると思ってたの」 ゾクリ、と一瞬身の毛がよだつ。全身の体温がサアっと音を立てて引いた様に思えた。 彼女の中の異質、彼女の持っているものが垣間見えたような気がした。 俺は、できるだけ感情を出さないように心がけた。 「ね? 私の言った通りでしょう?」は盛永に向かってにこりと笑った。 盛永は「スゲエな」といいながら、うんうんと頷いている。 俺は、そこで気付いた。 彼女は、何は普通の人とは違うものを持っている。 それで何者かに付け狙われているのではないか、と。 もしかしたら、一人ではなく団体や組織ぐるみで彼女を追っているのかもしれない。 そんな、そんな事が、実際に、―― 「私、未来が見えるの」 実際に、あることを知った。 「私ね、追われてるんだ。ヤクザとか科学者とかそういう人たちに。実験台にされるのが嫌だから、逃げてるの」 は、すとん、とベンチに座って続けた。 「だからね、私の周りには不幸しかないの」は寂しげに笑う。「ま、自分の未来は見えないけどね」 俺は、何も声をかける言葉が見つからなくて、ただ呆然と立ち尽くしているだけだった。 なにか、言葉をかけなければと思っても、何もかける言葉が見つからない。 なにか、言葉をかけてあげたいと思っても、頭が白くなってしまっていて、てんでダメだ。 何も無い。 何も。何も。 「天城、だからね」彼女は俯いた。「私の事は、もう忘れて頂戴」 ――……! 「あなたが私に関わって、自滅するのは分かりきったことよ」 「…そんな事、分からないじゃないか」俺は決め付けられるのが嫌いだ。 「いいえ、――分かるの」彼女はキッと俺を睨んだ。「何も分からないくせに意気込んでんじゃ無いわよ」 「…え」 まさか逆上されるとは思っても見なかったので、俺は一瞬呆気に取られた。 「ごめん」彼女は謝って、席を立った。「私情が混ざったわ、謝る」 「だから、私に関わらないと約束して。お願い。もう関係の無い人を巻き込みたくないの」 彼女は俯いたまま静かに涙を流しながら、歯を食いしばって泣いていた。 涙が、ぼろぼろと地に落ちていく。 近所に住む少年、巳鶴ちゃんが幼少の頃の私の友人だった。よく、公園で遊んだりした記憶がある。 彼はスポーツ万能な上に勉強も人一倍覚えるのが早かった。だから私は彼に負けないよう、頑張っていたつもりだった。 けれど能力の差というものは、それほど簡単に埋まるものではなかった。 もてはやされる彼の傍ら、私はいつも疎外感で一杯だった。いつか越えてやろうと思っていた。 ある日のことだ、私は夢を見た。 自分が、親から好きなものを買ってもらえる夢だ。ちょっと嬉しくて、朝から気分が良かった。 巳鶴と午前中に遊んで家に帰ると、お母さんが私を呼んで、車に乗せて何処かに向かいだしたのである。 私は何だろうと思い、暫くお母さんの様子を観察していた。 お母さん越しに外の景色を見ていると、どうやら近所のデパートへ行く時に通る道である。 ――もしかしたら。 私の中をある予感が過ぎった。もしかしたら、これは正夢かもしれない。 予感は、的中した。 お母さんは、私の欲しいものを一つ。誕生日でもクリスマスでもないのに突如買ってくれたのである。 「お父さんのぼーなす、入ったの?」と不思議に思って私が聞くと、母さんはにこりと笑った。 「お母さんのボーナスが入ったの」お母さんはニコニコと笑っていた。少し不気味に思えた。 「ありがとう!」私は取り敢えず嬉しかったのでお母さんにお礼を言った。 お母さんは「どういたしまして」とお決まりの定型句を並べる。 私は夢の事などこの時にはもうすっかり忘れていた。 巳鶴ちゃんの家に行って遊んでいる時に、それは起こった。普通にゲームか何かで遊んでいただけだった。 それまでは、何事も無かった。だが次の瞬間、突如フラッシュバックのようにある光景が、目の前に広がった。 夢の事が脳裏に蘇る。今回も、あの夢と同じ感覚だった。危ないという危険信号が頭の中で警鐘を鳴らす。 「うあああああああああああ」 気付けば私は叫んでいた。叫びながら頭を抱えて震えていた。 「ちゃん、大丈夫? ねえ」 巳鶴ちゃんは心配そうに私を覗き込んでいた。怖い。怖いよ。 「巳鶴ちゃん、離れちゃダメだよ」 「え?」 「お外に出ちゃダメ」 「…え」 「絶対ダメだからね、約束したからね」 「…うん」 「ゆびきりしよう」 「「ゆびきりげんまんはりせんぼんのーます ゆびきった」」 今思えば、それも気休めに過ぎなかったのかもしれない。 「巳鶴、今日は塾の日よ」巳鶴のおばさんが言った。私には、それが無慈悲な女神の言葉のように聞こえた。 「ごめん、ちゃん」 こちらを、申し訳なさそうな表情で巳鶴は見た。 ――だめだよ、待って。行かないで……いっちゃだめだよ。 「待って、私も途中まで行きたい」 私は、結論としてそう答えた。 結局、私は救えなかった。ギリギリのところで格好悪く救えなかった。 自分のものではない他人の返り血が、全身を真っ赤に染めていた。 方向感覚を失って横倒しになったトラックのタイヤが、くるくると間抜けに廻っていた。 運転手も、多分もう息は無いだろう。私は眼前に広がる光景は夢だと思いたかった。 でも、返り血のもつ微弱なぬくもりも、ねっとりとして頬を伝う感触も夢と思うにはリアルすぎた。 巳鶴のおばさんが、放心状態でその場にへたり込んでいる。 それは、段ボールの箱に入っている捨て猫を見つけた巳鶴がそれに駆け寄っていこうとして、 私たちよりも十歩ほど前方に出てから起こった数秒間の出来事。 巳鶴に向かってトラックが容赦なく突っ込んだのである。もちろん私はその前に、止めようとしたのだ。 しかし、幼い体の反射神経がそんな偶然の突発的な出来事に対応する筈も無かった。 そして、無慈悲にも神は彼を葬った。 「あ…ああ……これは嘘よね、……夢だわ、夢よ」若い巳鶴のおばさんは、私にしがみついてきた。 「ね? ちゃん。これは夢なのよね、私が見た悪い夢なのよね」 私には答えられなかった。 これは現実であり、巳鶴は私の運動神経が足りなかった所為で死んだ。 「ちゃん、ねえ……嘘だと言って…」 巳鶴のおばさんは最後にはもう啜り泣いていた。私は自分の不甲斐無さに憤っていた。 私が、もう少し能力的に恵まれていたら。私は彼を助けられたのかもしれない。それなのに。 私は、無力な左手を握ってわなわなと震えていた。哀しくて泣いたのではない、私自身悔しかったのだ。 奥歯を噛み締めながら、血に濡れた私たちは泣いていた。 二度と、他人を巻き込みたくは無い。 その想いから毎日走りこみをして腹筋をしてその他の筋トレをして反射神経を鍛えた。 後日、私は私の祖母も私と同じように未来が見えていたということを知った。 代々私の家系には、ニ・三代に一度未来の見える子供が生まれてくるのだという。 しかも運の悪いことに、私の家系のことは既に祖母の代からアチラ側の人間にばれていたようだ。 それからというもの、私の家族は逃げるように暮らしてきた。 人とのかかわりを極限に少なくする。そうすれば、もう哀しい思いもしない。 そう思って、人とのかかわりを避けていたはずだった。しかしだからといって、学校に行かない訳にはいかない。 そうなれば、自然と、私に話しかける人だって出てくる訳だ。 私は、明るくて可愛らしい面立ちの少女と次第に話すようになった。 彼女は、その容姿からも性格からもクラスのみんなに人気だった。 少し頭の方は悪かったようだが、そんなコトは微塵も感じさせなかった。 そして、彼女は学級委員を務めていた。クラスをまとめ、クラスを仕切り、クラスを一体にして動かしていた。 まさにリーダーの才能を持った少女だったといえよう。彼女はいつ見ても輝いていた。 その光さえも、私はまた奪ってしまった。 ヤクザが、学校に乗り込んできたのである。教師たちは慌てふためいていた。 私は、この特異体質を呪っていた。やはりこれも予想済みだったのだ。 私は、一人になる為に校舎裏に逃げた。一人になれば、狙われるのは私一人で済むはずだったからだ。 しかし無常にも予想は外れた。 「ちゃん! 危ないよ」 追いかけてきたのである、――学級委員長の少女が。 スカートをひらひらと揺らして、こちらに近付いてくる。 その隙間から、ヤクザが見えた。パアンという破裂音が響いて少女の動きがぐらりと乱れた。 「――っ!」 どうやら太い血管や急所は外れているようだ。息はある。 私は彼女に簡単な止血の処置をしてやると、ヤクザとにらみ合った。 ヤクザは、ヤバいとでもいうように逃げ去っていった。まさか私以外に当たるとは思わなかったのか。 自分の強さを過信していたのかは分からない。 だが、――命に別状は無いとはいえ、銃弾は彼女のひざを貫通していた。 私が巻いた水色の木綿のハンカチは、既に鮮血に染まりつつある。 まただ。また守れなかった。 私の所為だ。私の所為で巻き込んでしまった。 二度と誰も巻き込まないと決めたはずなのに、怪我一つ負わせないと誓ったのに。 悔しかった、守れなかった事が。 情けなかった、守られた事が。 だから今度は、私が守ると。深く心に刻んだんだ。 「馬鹿だな、お前」 「え?」 「もう、一人でそんなに背負い込まなくていい」 急に目の前が暗くなる。気付けば抱きしめられているのだと、自覚する。 妙に心地よかった。安心感が、あった。 「俺が、お前を守ってやる。だから、――」 だから、――絶対に泣くな。 「約束だ」と。 彼は言った。 気付けば、私は彼の腕の中で力なく笑っていた。 (20070403:ソザイ |