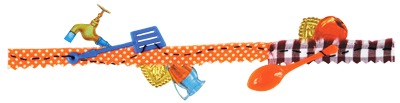 消して、消して、 全てを、消して。 非常に平凡極まりない考えだが、私にとって「恋」という名のものは未知の存在といっても過言ではない。 身近にいる女子にその何が面白いのかと問いかけてみたものの、たいして為になる回答は返ってこなかった。 聞き込み調査によって判ったものが、「ドキドキする」などの不確かな感情だ。 一言で言ってしまえば解り難い。そして私はそのような感情を持ったことは無い。 よって、私にその感情を理解することはできない。 と言う結論に達したところで、私は数学の宿題を終えた。 私の名は。 苗字からも推測できるように、不破大地のはとこだ。 現在、大地の家に居候の身である私は、やはり同じ学校に通うはめになった。 大学課程を終わらせている私は、わかりきった授業をされているので非常につまらないと思うのだが。 日本では義務教育制度があるので、つべこべ言わずに取り敢えず学校に通っている。確か、桜上水中学だ。 桜上水は、公立の中学らしい。 名目上、一応は素直に通っておいて私は取り敢えず暇つぶしになりそうな考察の対象を探すことにした。 結果、中学生と言うものは不思議なことに面白く愚かな考えを持つ生き物だという事が分かった。 編入してから早々、私と仲良くしようと試みた者が何名か現れた。 取り敢えず、適当にあしらったが、しつこく付きまとってくる。 その内の一人が、小島有希だ。 「さんさん、サッカーやってたんでしょ?」 と、ひたすら付きまとってくる。体育でやっていたぐらいしかサッカーボールとは親しくない。 「いや、やっていない。気のせいだろう」 私がそう言おうと、彼女は全く引き下がらなかった。 「ほら、冗談はよして。だって、ドリブルもリフティングも初めてとは思えないほど上手いじゃない」 「これぐらい誰でもできるだろう」 「出来ないから言ってるんでしょ、ほら、女子サッカー部入ってよ」 「私はそんな気はないのだが」 「いいのいいの。その内面白く感じるから」 とまあそんな訳でいつの間にか入部届けを出されて私は女子サッカー部に入部することになったようだ。 強引だ。 それに加え大地もサッカー部に入部したことにより、私の周りにはサッカー部の知り合いが多くなった。…らしい。 クラスではあまり目立たないようにしていたのだが、目立つ奴が寄ってくるせいで、こちらが無意味に目立ってしまう。 面倒くさい。 「! 部活行こー」 平穏がざわりと乱れる。 それもそのはず、校内でもなかなか美人の部類に入るであろう小島有希がわざわざ隣のクラスにきているのだ。 「有希か」 「早く! 今日は敵状視察なんだから」 「言われなくても解っている」 兎に角急げばいいんだろう、と私は答えた。 「そう、だから急いで!」 そして私たちは取り敢えず部室へと向かう。まあ、正式な部活ではないので部室を他の部活と兼用しているわけなのだが。 それにしても、急に敵状視察とは…全くもって性急だな。 「じゃあ、がこっち。私はこっちから回るからこういう経路で回っていってね」 「在校生と鉢合わせたら、どうすればいい」私は立ち上がった有希を座ったまま見上げる。 「適当に受け流して」 私たちは草むらに隠れながら作戦を練っていた。 「ところで、この制服はどこから仕入れたんだ?」 「企業秘密☆」 ウインクで返された。正直返す言葉が無いので、仕方なく苦笑した。 有希と行動を別にして数分後、私は取り敢えず黄色い声のする集団を発見した。 いや、ただ単に五月蝿いと感じる方向へ進んでいっただけなのだが。 まあ、見つけられただけでいいだろう。と私はそれを遠巻きに眺める。 フェンスの向こうに武蔵野森の練習風景が広がる。 ひたすらボールを蹴っていたりしているように見える。まあ、サッカーなのだから仕方ないだろう。 その時だろうか、一段と大きくなった黄色い声が思考を妨げた。 何やら名前らしいものを叫んでいるらしいが、何を叫んでいるかは解らない。 どうやら、先ほどあの辺りから出てきた連中のことを呼んでいるらしい。 ふと、その中の一人に目が止まった。 別に好みのタイプだとかそんな意味の分からないものではなく、ただ顔を見た事がある程度のそんな奴だ。 ピアノか何かの塾が、一緒だった気がする。 名前が何だったかは少々昔の記憶なので曖昧だが、確か笠井何とかと言う名前だったはずだ。 まあ別に興味もないので思考をやめた。 「笠井」 「あ、渋沢先輩」 声をかけられてそちらを振り向く。 「いや、心ここにあらずという顔をしていた気がしたんだが…大丈夫か?」 「大丈夫です」 なんでもお見通しだな、この人は、と内心溜息をついた。 本来であればグラウンドにいる筈の無い見知った顔の少女がフェンスの向こう側で仁王立ちしていた。 それだけで、吃驚だ。そして元来、彼女はサッカーを進んで見に来る体質ではないので、 明らかに、よその学校からの視察だという事がわかる。 だとしても、だ。 ここの制服をどこから入手したのだろうか。やはり、情報通がいるのだろうか。 少し考えるのが面倒臭くなってきた頃に、後ろから名前を大声で読んでくる輩の声が聞こえた。 そんな事をするヤツは思い当たる中で一人しかいない。 「たっくみー!」 「誠二、五月蝿い」 一言で切り捨てると、藤代誠二は背後にガーンという効果音を背負ってあからさまに落ち込んだ様子だ。 ふと、フェンスの向こうを見れば、彼女はもういなかった。 畜生、と少し悪態をつく。 練習後、俺たちは食堂に集まって夕食を食べていた。 「おばちゃーん、Fランチ!」 「はいよー」 「Aランチ、お願いします」 「いつもご苦労さんだねえ」 おばさんがにこりとしてトレーを差し出してくる。 「有り難うございます」と言って僕はそれを受け取った。 席に着く。 練習がきつかったという話と、学校のクラス内であった出来事を一通り話し終わった後。 自然と、会話は今日の女子の黄色い声についての話に移り変わる。 「せんぱーい、今日俺日本人形っぽい子見たんっスよ!」 「あー、アイツな。腕組んで仁王立ちしてたやつ」 「何か面倒くさそうに見てましたよ」「付き添いだろ、誰かの」「じゃあ、誰かあそこで待ってたんっスね」 「さぞかし面倒臭いだろうに」「興味なさそうにしてたよなー」「結局あそこにいた目的ってなんなんだろ」 とまあ、話題に上がってるのはやはり彼女のことのようで。 「偵察っスか?」誠二が切り分けたハンバーグを口に入れながら言う。 「あー、あるかもな」三上先輩が唸った。 「どちらにせよ、校内にいなかったら外部からの偵察者って事…ですよね」 取り敢えずそう言った後に、僕は席を立つ。 気になっている人の事をとやかく言われるのは慣れていなかった。少し不快だ。 そのまま僕は逃げるようにして部屋に戻っていた。 きっと今日は気になりすぎて眠れない。 土曜日。 取り敢えず久しぶりに外に散歩に出かけることになった。 主に買い物をするためだ。こちらに来てからというもの、四六時中本を読んでいるせいか、読む本が無くなったのだ。 そのような訳で、何か適当に面白そうな本でも買おうと思い立って、今に至る。 論文、ファンタジー、SF、ライトノベル、その他もろもろ。 まあ適当に興味のある分野から買い占めていこうという算段だ。 これは多分私が読んだ後に大地が読むだろうから出来るだけ幅の広いものを買っていったほうがいい。 今までに読んだことの無い本を予算以内で買う。というのが、今回の私の目的だ。 と、まあ徒歩でのろのろ歩きながら近くの本屋まで来たところで、 「さんだよね」 と、声をかけられた。 「笠井、か」 「うん。偶然見つけたから、声かけてみたんだ。覚えてたんだね、名前」 笠井は、どうやら同じ本屋に用があるらしく、私と同じ本屋に足を踏み入れた。 「まあ、かろうじて苗字だけだな」 「そうなんだ、」少し彼はショックを受けたようだ。……まあ、それもそうだろう。「まあ、改めてだけど笠井竹巳」 「笠井、竹巳か。解った」 私は頷いて適当な本を手に取り、カゴに入れた。 「そういうの読むんだ」 「いや、こういうのは適当に買って家の中で回し読みをする」 「へえ、趣味が合うの?」 彼は首を傾げるが、私は頭を振った。 「いや、全く合わない。だから適当に買って行くんだ。まあどれか一冊か二冊は気に入る本があるだろう」 確証は出来ないがな、と私は付け足す。 へえ、と彼は感心して、一冊雑誌を手に取った。 「サッカー、か」 「サッカー部だからね、色々研究したいんだ」 と呟いた後に彼は、思い出したように言った。「そういえば、この間練習の時居たよね」 「ああ、あれか」私は、そういえばそんなこともあったような気がすると、つい口に出していた。 「やっぱり居たんだ」 「敵情視察がどうこう言っていたな。取り敢えず教師にばれなければいいという話だった」 別に生徒にばれようがばれまいが関係は無いだろう。と私は言う。 「やっぱり面白いよね、さんって」 クスクスと笑いながら、笠井はこちらを見た。 「普通だよ、私は」 そして私もつられてにこりと微笑んだ。 *** 不覚にもどきりとしたとか、それは彼女には言わないことにしようとか。 失態だと罵られようが、別にいいやとか思っていたりして。 やっぱり、意識しているのかと、少し再確認もした。 「やるせないな」僕が言う。 「何が」彼女が問いかける。 「自分が」 「そうか」 彼女は納得したようで、人間とは不思議なものだと呟いた。 僕はこれからまた離れるのかと思うと、少し空虚な気持ちになった。 僕は、「しまった」と感じる。 相当重症だと思ったときにはもう遅く、後戻りは出来ないところまで来ていた。 明日、明日だ。と意を決してみる。 まだ、今日は黙っておこうと、珍しく笑う彼女の隣を歩く。 (20071024:ソザイ |