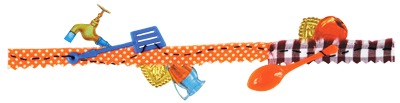
貴方に手を伸ばす。手に入れる事が出来ないと知りながら。 貴方へ手を伸ばす。必ずしも届かないという事を知りながら。 それでも私が手を伸ばすのは、ただあなたと言う陽光を浴びたいがため。 けれども私の手が伸びる先は、ただただ虚空を掴むばかり。 無償でもいい。代償でもいい。 無策でもいい。失策でもいい。 無謀でもいい。謀反でもいい。 愛しい貴方に、捧ぐ唄。 私はもうあの人の目には留まらないのだ。 そうやって自分に諦めとけじめをつけることが、私にとっての初恋の結末だった。 そう、そうやって諦めてしまえば。私はあの人から解放される筈だったのだ。 しかしそれは、無駄だった。 そんなことをしても、無駄だったのだ。 変わらなかったのだ、何一つとして変わりはなかったのだ。 何かが変わると信じて疑わなかった私は、希望を失った。 これほどまでに、彼に私が依存していただなんて思いもしなかった。自然と涙が頬をつたう。 ああ、せめてあの人に恋人でもいれば、私は諦めがついたのに。これでは、いくらたっても諦められない。 寧ろ期待してしまった。あの人は、まだ彼女がいないのだ。私にだって、チャンスくらいはあるのではないかと。 期待してしまったのだ。あろうことか、この私が。 期待など、裏切られる為にあるものなのに。 期待など、するだけ無駄だと言うものなのに。 そんなものは、あるはずのない物だというのに。 それなのに、―――どうして。 私は、先日彼の試合を見に行った。 姿など、豆粒のようにしか見えなかったものの私は彼の姿をその視界に捉えることに成功した。 友人であるアリサの誘いにわざと乗って、見に行ったのだが、それは私の失策だった。 今まで留めていたはずの想いが、まるで大河が氾濫したかのように押し寄せてきたのだ。 ――こんなに、目頭が熱くなったのは久しぶりかもしれない。 私は、アリサに「花摘に」と偽って席を立った。アリサは、こちらを見てにこりと笑う。 「早く戻ってきてね!」と一言口走ると、また試合に目線を戻した。 女子トイレにひとまず向かう。個室に入り、取り敢えず涙腺を緩めた。 私は彼を一瞬でも見れた事が、思っていた以上に嬉しかったらしい。感動の、一方的な再開だった。 馬鹿みたいだ、と思った。 別にあって話したわけでもない。彼が実は私を好きだったと言う訳でもない。そんな確証はないのに。 それなのに、正直に嬉しかったと言う気持ちが先立っていた。自分の感情が理解できない。 こんな気持ちになったのは、初めてかもしれなかった。 ああ、こんなにも。 こんなにも私は、――― 目頭を、指で押さえて静かに涙が頬を伝い落ちていくのを感じていた。 このまま、こうして涙が枯れるまでいたら試合は終わってしまうだろうか。 ふとそんなことを考えて、思考を切り替える。乱雑に涙を拭った。目が少し赤くなってしまったかもしれない。 どうしようか、と鞄をさぐりカラコンを取り出した。深紅の色をしていた。 これで誤魔化そうと思い立って、私はそれを目に入れる。さらに鞄から黒く長いウィッグを取り出して頭につける。 上が平らになっている、白い大き目の水タンクの上に鏡を置いて髪形を整えた。 なんとか、髪型も服とも合っているようだ。 これで泣いて目が赤くなっていることにも気付かれないだろうと、少し高をくくった。 少し遅くなってしまったので急いでアリサの所に戻ろうと、女子トイレから出た瞬間だった。 「かわいいね、君一人?」 「俺たち、選手なんだけどさ。まだ出場まで時間あるからそこで話そうよ」 絡まれた。 絡んできたのは、現代風の茶髪をワックスで無造作に四方に立てている強いて言えば優男風の男二人。 似たような服を着て似たようなシルバーアクセサリーをつけている。アレは相当値の張るものだ、と誰かに聞いた記憶がある。 高いブランドでは、ブレスレットだけでウン十万とするものもあると聞いた。 私はあまり興味がないのでロクに聞いていなかったのだが。まあそれはさておき。 ピンチだ。 「すいません、私、――」 とまあ私が声を作って断りの文面を述べようとした所で右側に立つ深緑の半袖Tシャツを着た男の静止の声が割り込む。 「来いよ、な?」 深緑のの男は、私の手首を掴んだ。どうやら簡単に逃がしてくれる気はないらしい。私は頭の中で舌打ちをした。 ああ、こんな事ならもう少し目立たないような格好をしてくるべきだった。まずかった、私とした事がなんてざまだ。 おばあ様にこんな所を見られたら、何と言われたか解ったものではないが。取り敢えず馬鹿にされることは確実だ。 「離してください」私は無表情のまま淡々と台詞を紡ぐ。 「離す気なんてないよ、ほら君みたいに可愛い子とかなかなかいないからさ」 ま、には劣るけどね。と、彼は変装前の私の名前を出して笑った。少しカチンと来る。 私がどういう経緯で私に劣らなければならないんだ。まあ、――所詮この男も他の男も皆同じだということだろう。 「離してください」先程と全く同じ調子で言う。 「嫌だ、と言ったら?」 「反抗でもするかい、お嬢さん?」 深緑に続いて、左側に立っていた黒いシャツの男が笑う。 ――何だ、こいつ等。 私も、絡まれた経験が初めてという訳ではない。家柄、と言うのもあるのだろうが、何十回かは絡まれている。 しかし、この目は。 こんな薄汚い目をした奴らは初めて見た。 悪意に満ちた、目。アイツと同じ色の表情が浮かんでいた。 ちくりと、古傷が疼く。 「そうそう、そうやって大人しくしてればいいの」 「俺たち何もしないって」 深緑が、ぐいっと手をひいた。自然と少し油断した私は深緑のほうに引き寄せられてしまう。 捕まれた手から、抜け出そうと思い腕を引っ張ってみたが、無駄な努力のようだった。 「あばれないでよ、じゃじゃ馬ちゃん」 「……ッ」 結果として腰に手を回された。技を使わずに抜け出せると甘く見たが、全くもって逆効果だった。 背筋が凍りつくように冷たい。その感情が恐怖だと知るに数秒を要した。 本当にどうしようもない状況になった。だから、――これなら少し技を使って倒してもいいだろう。 と思うに至ったその瞬間だった。 「ぐっ」 まずは私の腰に手を回していた男が、私が何もしないうちに泡を吹いて腹を抱えながら倒れていくのが見えた。 次に、声を上げたのは黒いシャツの男。こちらも同じように地面に向かって倒れていく。 コマ送りのように、ゆっくりと。しかしその攻撃は的確に相手の急所を狙って突いていた。 男たちはどうやら気絶したようだった。 「大丈夫かい?」 話しかけてきたのは金髪の男。私はこの人が助けてくれたのか、と思う。 「ええ、ありがとうございました」 私はその人に頭を下げる。 「――…あれ?」金髪が一瞬驚いた顔をする。「いや。…あ、えっと、…倒したのは僕じゃなくて、進だから」 「シン?」 「君の後ろの、進清十郎」 振り返ってみれば、大きな人が後ろに立っていた。 「ありがとうございました」 頭を下げる。 「大丈夫か?」 「おかげ様で。それでは、」さようなら、と言って私はその場を後にしようとした。 が、 「! こんな所にいたのー、私また絡まれてるかと思って心配したよ!」 「絡まれたけど」 「嘘! ウソだね、その証拠がどこにあるのさ!」 「そこ」 私は床にへばりついている男たちを指差す。 「うわあ! さすがだね、――ってうわあ進さんだ、すんごいよ生で見たー、ガタイでかいなあ!」 「……」 「……」 沈黙と好機の視線と変な視線がいり乱れる。 「えっと、」金髪の人が、沈黙を破る。「君は、――進のファン?」 「そうとも言うけど、正確には『全国のスポコン魂を持つ者のファン』だよ、桜庭君」 そうとも言うのか、と心の中で突っ込みを入れてしまった。 そしてアリサはどうやら彼の名前も知っているようだ。私にはアリサがこういうときだけ変態に見える。 「――変な子なので、あまり気にしないでください」 弁解だけはしておいた。隣で酷い説明だよワトソン君などと訳のわからない事を言っているがまあ気にしないでおこう。 「あ、あははは・・・・・・」 金髪、――確か桜庭君とか言っていたようなきがする――は苦笑している。 それもそうだろう。アリサのテンションはいつも、異常に高いのだから。 「うん、さすがLB(ラインバッカー)だなあ。凄いなあ鍛えてるなあ」 「トレーニングは欠かさず行っている」 「そうだよねえ、やっぱりランニングとかでしょ」 「他にも腹筋・背筋を鍛え持久力をつけるために日々精進を積んでいる」 「やっぱり腹直筋とか、上腕ニ頭筋とか上腕三頭筋とか大腿直筋とか鍛えてるんだよね」 だんだんと筋肉がどうこうという話になってきた。ついていけるが、ついていきたくない。 アリサは無駄に体を構成している筋肉と、医学について詳しい。そこのみで言えば雑学王である。 そのアリサと対等に渡り合う彼も凄いとしみじみ思った。 隣を見ると、桜庭さんが楽しそうに会話するアリサと無表情で会話する進さんを呆れながら眺めていた。 私と同じような境遇のようだ。 「あの子、いつもあんな感じ?」彼が問いかけてくる。 「――まあ、そんな感じです」 確かに今はスポーツ選手と会って少し普段よりもテンションが高いが、普段と大して大差はない。 「そういえば、」私は少し気になって聞いてみた。「桜庭さんはスポーツ選手か何かですか?」 「えっと、い……――あ、うん。…まあそんな感じ。アメフトやってるんだ、王城のWR(ワイドレシーバー)」 やはりそうだったか。道理でアリサが知っている訳である。 私は「そうなんですか」と相槌を打つ。やはりこれは敵情視察が目的らしい。 確か王城と言えば黒百合が社交的に交流をしている学校でもあるので文化祭は合同で行っているという。 今度の文化祭までにはあと何ヶ月か月日が残されているので、まだ本格的な準備は始まっていない。 しかし、後一ヶ月もすれば両校とも本格的に動き出すだろう。準備が忙しいだろうな、規模が膨大だから。 と、まあそんなことを考えながら熱心そうに語るアリサを眺める。 ああ、全く理解できない。 けれど、彼女は私の恩人であり友人。 何を私は考えているんだろう、と笑った。 「――あ、試合始まっちゃうよ」 桜庭さんが、時計を見て慌てて言った。そういえばもうそろそろハーフタイムも終わる。 「進、進、早く移動しなきゃ」 「アリサ、まだ観戦するんでしょう?」 両者一斉にこちらを向いたので、少し威圧感がこちらに漂ってきた。 「あ、もし良かったら一緒に観戦しようよ」 進があんなに話してるの見たの初めてだし、と彼はにこやかに言ってくる。 まあ、悪意は感じられないのでいいだろうと、私はその提案に首を縦に振る。 アリサが「、珍しいなー!」とか騒いでいるが、「恩があるから」と言ってふわりと笑った。 「恩を仇で返すはまだ一回しか見てないからね!」とアリサが言った。 全く、いつの間にかよく観察している。と私は少し内心冷や汗をかく。 まあそれは、それだけ彼女と一緒に行動している範囲が多いだけで。 私が他の人よりも彼女に心を許している所為でもあるのだけれど。 それは、恥ずかしいので本人には言わないでおこう。 ハーフタイムが、開けようとしている。 あの人が、グラウンドに出てくる。 そう思うだけで、気分が高揚した。 貴方と鉄馬がいなくなって、もう何年も経っていた。 もう、会えないと諦めていた矢先の出来事だった。 ふとした瞬間、思わぬ所で、貴方に逢ってしまった。 貴方が、やはりこの世界にまだいる事を知ってしまった。 知らなければ、諦めきれた筈なのに。 知ってしまった。 知ってしまったのだ、私は。 無理だと解っている。 無駄だと解っている。 あのころは政略結婚なんて嫌だったけど、今はそんな事は思わない。 だから、今からでもいい。 Ich will, das Sie zuruckkommen. (貴方に、戻ってきてほしい) 何故なら、私は……―― Weil ich Sie am meisten in der Welt liebe. (貴方を世界で一番愛しているから) (20070905:ソザイ |