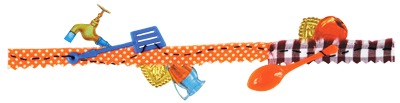
どうしても 避けられない運命 どうしても 逃げられない宿命 どうしても 抗えない天命 ああ 何故あなたは私を それまで私たちは、仲睦まじく生活していた。 生活していた、といっても一緒に住んでいたわけではない。 互いの家が主催する宴に参加しあう。親と親とが共謀しあい、自らの利益を上げるために自らの子供を差し出す。 日本でも四百年ほど前では盛んに行われていたが、現代ではあまり見なくなった政略結婚。 そう私たちは俗に言う、許婚だったのだ。 それでも、私にとって唯一の親友と呼べる存在だった。私はそれ故に彼に依存していた。 それは、ある宴の後日の物語。 時は、十年ほど前に遡る。 その日、私は武者小路家で行われていた社交パーティへ父親と共に行った。 やはりいつも通りというところなのだが、会場は盛大で華麗な装飾品によって飾りつけられていた。 出席している人たちは財界のトップや、石油王、芸能界のトップ俳優、ハリウッド、政治家のお偉いさん等ばかりで 自然とその次世代を担うことになるかもしれない娘や息子たちも集まっていた。 そんな盛大なパーティー会場の主催者である武者小路一の息子である紫苑が、私の許婚だった。 私の義理の父である惣一郎は財界でも有名な人らしく、さまざまな人に挨拶をしていたような気がする。 幼い私にはよく分からなかったが、周りの大人たちからの視線はとてつもない威圧感を放っていたように見えた。 あくまでも、それは幼い私の推測に過ぎないのだが殆どそれは確実といってもいいほどに的を射ていたと思う。 まあ、私がそれを自覚することになるのはそれから数年先の話なのだが、まだ今語る必要も無いだろう。 さて、当時私は普通に考えれば小学生の歳だったのだが、特別方針で授業が進む飛び級制のある学校に通っていた。 その時点で私が学んでいたのは中学三年辺りの学習内容だっただろうか、確かその辺りだった気がする。 そんな訳で将来かの有名なアメリカの超有名一流大学――といえば皆さんもうお分かりのことだろうが、 そこへの入学は確実という周りの適当で何の根拠も無い言い草のせいで私はそこへ行くことを余儀なくされた。 話を戻そう。 紅い絨毯の上を歩く。 いかにも高級だと言わんばかりの、金糸の刺繍の入った長い絨毯だ。 その絨毯の上、私の前に一人の男が歩く。私の父親だ。 「こんにちは、さん」 一人の男がこちらに手を振る。やはりここに来ているだけあって身なりは紳士である。 二十台前後だろうか、その若々しい容姿は何処かの俳優のように端整だった。 きっちりとまとめた少し茶色がかった髪が、きれいな色をしている。 父は、軽く腕を上げて「やあ、久しぶりだね」といって、その人の名前を付け加えた。 『こんにちは、Mr.』 何語だっただろうか、確かドイツ語辺りのような言語だった気がするが、海外の言語も頭上を舞う。 父は、グローバルにその言語で挨拶を返した。 そんなこんなで父はかなりの人数にあいさつ回りをするのをこなしていく。私も一応礼儀としてお辞儀はする。 何人かの人が、頭を撫でてくれたような気がした。 私は父にはぐれないように付いていく。私にとってこの父親はとても大きな存在に見えた。 「!」 聞きなれた、ボーイソプラノの声に振り返る。自然と笑みがこぼれた。 「紫苑!」 彼に手を振る。彼こそが私の将来の結婚相手である武者小路家の息子、武者小路紫苑である。 中世的で整った顔立ちの、可愛らしい少年はこちらに駆け寄ってきてくれた。 「来てくれたんだね! 嬉しいよ」 私は、ふわりと微笑んだ。父が、私たちに屈んで目線を合わせた。 「それでは、邪魔者は消えるとするよ。しばらく二人でゆっくりしているといい」 父はそれだけ言い残して、雑踏に紛れ込んだ。どうやらまた挨拶回りにいったようだ。 「ね、。向こうに鉄馬がいるんだ、一緒に行こう」 「うん」 「鉄馬―!」 鉄馬くんの姿を紫苑が見つけたようだった。続いて私も彼の姿をその視界に捉える。 「こんにちは、鉄馬くん」 スカートの両端を持ち上げてお辞儀をする。鉄馬くんはコクリと頷くように礼をした。 彼は代々武者小路家のボディガードをしている家系に生まれた息子であり、紫苑の数少ない同年代の親友だった。 そして、私にとってもそのころの彼は親友であって、それは高校生となった今となっても変わる事はない。 「、」私の名を呼び紫苑は少し間を開けてから言った。「僕は自分のやりたいことを見つけたんだ」 私は少し呆気にとられて暫く唖然としてしまったのだが、――まあ表情には出ていないが――気を取り直して言う。 「…そう」私は曖昧に微笑んだ。胸がざわつく。 なぜだろう、嫌な、嫌な空気が脳裏を掠めていく。 そんな私に気づきもしない彼は、生き生きとした表情で無邪気に微笑んだ。 「親に縛られたくない」 彼は周囲に聞こえないように俯いて、囁くような、呟くような、独り言のような声を漏らした。 「僕の意思で乗り切ってやるんだ」 その彼の言葉には、はっきりとした決意があって彼と私の間にどうしようもない隔たりが出来てしまったかのようだった。 それはもう、私の入る隙間など存在すらしないように。 それは既に、終わってしまった物語のように。 「だから僕は、―――」 私は怖くてそれ以上彼の言葉に耳を傾けようとはしなかった。 それは恐怖と自らの精神の脆さに気付いたせいでもあり、これ以上自分が気付くいていくのを見たくなかったからでもある。 要するに、ただ彼が自分との距離を広めて言ってしまう事が怖かった。 ただ、それだけだった。 だから臆病な私は、聞いているフリをすることしか出来る事がなかった。 「―――」 彼はその間にも言葉を並べる。 私はそれが耳を通らないように、なにか他のことを考える事に集中する。 聞いていたくない気持ちと、聞きたいという気持ちの矛盾。 それは正しい人間の欲の働きである、というような事を何処かで誰かが言っていた気がする。 「だからね、。君は、―――――」 もう、聞いていたくなかった。 怖い、恐ろしい、いや…嫌だ、私は…まだあなたと、―――― 一緒に、いたいから。 「…? どうし…」 どうしたの、と言おうとしたのだろうその言葉はつむがれることなく終わり、彼は私の表情を見て驚いたような顔をした。 何か頬をくすぐるものがあるのに気付いた私は、慌ててそれを拭った。 どうやら私は泣いていたらしい。ただひたすらに、瞳からは涙が溢れていた。 「目に、少しゴミが入ったみたい」 在り来たりな言葉で、言い訳をした。私はポケットからハンカチを取り出して涙を拭く。 ああ、なんて私は馬鹿なんだろう。 相手の言葉も聴かずに、ただ徐に涙するなんて。 ふと、そんな事を思った。 どうやら、社交パーティは、いつの間にか俗に言う『二次会』へと変化したようだ。 ワインを持ったバーテン服の20台前後だろう、茶髪で端正な顔立ちの屈強な男たちがせわしなく動き回っている。 同じくドイツビールだろう物を盆で運ぶ女たちも、小奇麗に一つに結わえられた髪を揺らしながらバーテン服で動き回る。 まるで働きアリのようだ、と私がちょっとした石段に座って、ぼうっとしながら眺めていると、私の左隣に座って 暫く沈黙を保っていた状態だったはずの紫苑が口を開いた。 「、『アメフト』って知ってる?」 「あめふと?」と、私は首をかしげた。 鉄馬くんは紫苑の隣に座ったまま微動だにしない。 「うん。正式名称をAmerican football と言ってね、ラグビーにすこし似てるんだけど、このぐらいのボールを 相手方の陣地に叩き込むゲームなんだ」彼はボールの大きさを、その限られた大きさの手で示して続ける。 「アメフトで敵陣に点数を入れる方法にはだいたい二つの方法があってね、 一つ目は敵の陣地にボールを持ってそのまま走ってタッチダウンすること。これで六点追加されるんだ。 で、二つ目はタッチダウンの後にキックで点数を入れること。大体この二つみたいだよ」 まだ、始めたばっかりだから良くわかんないんだけどね。とかれは嬉しそうに照れ笑いをした。 私は少し複雑な気分になる。けれども彼を見ていると、やはり不安になって自分に言い聞かせるように私は言った。 「そっか」そして前の庭に生えている薔薇の花を眺める。「自分の好きなこと、見つけられるのは凄いことだよ」 だけど離れていって欲しくないから。とは言えなかったけれど、後々それで後悔することになると知っていたなら 多分私はその言葉を、言っていたはずだ。まあ、絶対とは断定しきれないのだが。…恥ずかしいから。 私の居場所が、とられてしまう事など考えもしなかった。私は続けた。 「だから、大切にした方がいい」 一度きりの人生は、楽しまなければ損だから。と私は前方の薔薇を見ながら呟いた。 彼が、こちらを向いているのを人間のもつ視界の片隅に捕らえる。どうやら複雑な表情をしているらしい。 「ありがとう」彼は言った。「少し、元気が出た…気がする」やはり彼も前方の薔薇をぼんやりと見ながら、言った。 ここで交わした、何気ない言葉がこれからの運命を左右する。 そんなことになってしまうなんて。 私はやはり思いもしなかった。 考えも付かなかったから。 彼の運命も、私の運命もことごとく変貌を遂げてしまった。 「! そろそろ帰ろうか」 「分かりました、お父様。じゃあね、紫苑」 私を迎えに来た父親に手を引かれながら、もう片方の手で彼に手を振った。 彼も、じゃあね、といった後に私の名前を言う。 これが、私が紫苑と交わした最後の言葉だった。 そして歯車の螺子は外れ、歯車の回転は悉く狂ってしまうことになる。 (20070707:ソザイ |