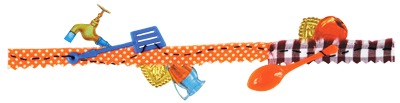
貴殿に捧ぐ物語
いつの日もいつの時代も 私にとって、あなただけが どちらにせよ、この家に生まれた時点で私の運命は決まっていた。 私などの一存で運命など変えられるはずもなく、私は自分には何もできないと言う無力さをひしひしと感じていた。 どうしようもなく、心が蝕まれていく。屋敷の畳の上に寝転がる。 どうしたのだろう、心が締め付けられてしまう。 あても無く考えを巡らせて見るものの、それは全てから回りして廻る。 胸が痛い、胸が痛い。 私が数日前に、あの人に会わなければこんな思いにはならなかったのに。 私は出会ってしまったのだ。 因果の鎖を手繰り寄せるように降りかかってきた運命的な、その出会いに。 三日前・城下町にて 私は、町人の着物を着て城下に繰り出した。ちょっとした散歩のつもりだったのだ。 取り敢えず、甘味処で団子を頬張りながら後々私はやはり父上にお叱りを食らうのだろうかと考え、 慌ててその考えを吹き消した。遊びに着たのにそんな事を考えていては、楽しいものも楽しめないだろう。 団子の残り一個を口に運んでもごもごと口を動かす。飲み込んでお茶を啜る。 ほっと息を吐き出して、先程まで座っていた長椅子から立ち上がり御代を店の娘に渡す。 娘は「まいどありー」と言うとこちらに向かって一礼した。私はそれに背を向けて街をぶらつく。 城下には、さまざまな店が出ている。久々に来たので色々と新鮮だ。 鮮やかな着物の生地を眺めたり、煌びやかな簪を眺めたり。 町の人もそれなりに良い人ばかりだった、だから私は少し気を抜いてしまっていた。 思えば、それがいけなかった気がする。 私が呉服屋の店の前で商品となるものを眺めていた時だった。何頭かの馬の蹄の音が、近付いてきていた。 誰が来たのかと顔を上げる私を尻目に、村人たちは早々に家の中に入り始めていく。 しかもその様子は尋常ではなく、皆かなり急いで慌てながら近くの家に入って行っているようだった。 「お嬢ちゃん、こっちに入りな」 呉服屋の店主が手招きをしている。人の好意を裏切る訳にはいかず、私もそれに倣い呉服屋に入れさせてもらった。 主人が閂を閉めたのを見てから、私は外の様子を窓から覗く。 馬に跨った鎧を着込んだ武士たちが、町の外に立っていた。辺りをしきりに見回している。 人の気配が無いことを悟ると、彼らはそのまま馬を走らせてそのまま去っていく。 私は主人に聞いた。 「あの武将は何をしに来ているのでしょう?」 「お嬢ちゃん、知らないのかい?」店の主人は、驚いたようにこちらを見た。 「あいつらのやっていることは下道だよ、毎日来ては外にいる町の人を殺して楽しんでおる」 店主は溜息をついて、こちらに目を向けた。 「お嬢ちゃんもあいつらには気をつけないといけないよ。…私は幼い娘を一人、あいつらに殺されているからね せめて一人でも多くの人が犠牲にならないように、していきたいのさ」 私は口を開きかけて、ショックで声が出てこないことに気付き口をつぐんだ。 そんな事が、城下で行われていたなんて知らなかった。私は少し怒りを覚える。 「酷い…なんてむごいことを」 暫くして、漸く声が出るようになって初めて口走ったのはその言葉だった。 店主は悲しそうな顔になって私の言葉に頷いた。 「しかしな、それが運命というものなのだ。あいつらに刃向かったら、また人の命がなくなってしまう」 「でも…「仕方ないんだ、諦めるしか…」 そう言った店主の横顔は、曇りに曇っていた。この世の悪に対して、正義を諦めてしまったかのような、 酷く、情けない顔をしていた。 武士連中が完全に去って行った後、私は呉服屋の店主に別れを告げた。 そろそろ屋敷に戻ろうと、帰り道を進んでいく。 町の人は、おそるおそる店や、家の中から顔を出し始めていた。 私は奥歯を噛み締める。私の知らないところでこんな思いをしている人達がいる。 世の中に怯えて、武士に怯えて、不安に苛まれている人達がいる。 この人達を放っては置けない、けれども私に出来ることなど無い。 悔しさと、無力さが押し寄せてくる。何で私は、肝心な時に何も出来ないのか。 そんな、無力な自分に対して怒りがこみ上げてくる。私は何で何もする事が出来ないのだろうか。 悔しい、と。 久しぶりに感じた。 ふと視線を前に戻す。と、私の瞳に派手な格好をした男が映る。 「なんだい、浮かない顔してるねえ…そんな顔してると、幸せも寄ってこないよ?」 「え…」 一瞬自分に向かって発せられた言葉だと分からずうろたえる。 「ほーら、もっと笑顔で。ね? そのほうがきっと可愛いって!」 「…」 何なのだろう、この男は。私は顔を顰めた。 「あ、もしかして俺のこと怪しいとか思ってる?」 男は、あちゃーと声を上げていきなり名乗り始めた。 「俺は、前田慶次! よろしくな!」 「え…あ…はい」 「ねえ、君名前は?」 ほら、お互い自己紹介ってことで! と男は馴れ馴れしくこちらに向かって言葉を発する。 どうやら敵意はなさそうなので私はひとまず警戒を解いた。 「……でございます」 「ちゃん、かー。んー、でもあんまり見ない顔だよね。どの辺に住んでるの?」 「…町外れに」 嘘をついた。 「そっかー。ところでさっき馬に乗った武士が走ってったの見たんだけど、どっち行ったか知らない?」 「え…?」 それはさっき見た連中のことではないかと、私は思い返す。 私では何も出来ないと、怒りを覚えた感覚が甦る。 「先程、町を通り過ぎていった所ですが」 「よし、きた! 俺、今からそいつ等一発殴ってきてやるからな!」 待ってろよ! と彼は意気込んで、「じゃあな」と一言残して去っていった。 後ろで縛った長い髪が、彼の走りかたに合わせてゆらゆらと踊る。 不意にその後姿が、格好よく思えてしまって。 私は、気付けばその夜から彼のことばかり考え続けていた。 それから、やはり何も考えられない日々がつづいていた。 もうあの人に合えないのだろうかという不安と、どうしようもない虚無感。 失ってしまいたくない、出会わなければ良かったという度重なって矛盾し続ける想い。 私はどうすれば、いいのだろう。 考えても考えても、答えは延々と廻り続ける。 終わりの無い迷路に、迷い込んだかのように。 果て無き旅路を、歩いているかのように。 終焉に辿り付く事は無い、終幕の無い幕開け。 それはくるくると。ぐるぐると、廻っている。 ただ、同じ所を旋回しているだけに過ぎないとしても、ひたすらにそれは渦を巻く。 実際には一歩もそこから出られないままだとしても、矛盾した考えを辿り続ける。 やがて同じ場所に戻ることは分かっているとしても、ただ、廻り続ける思考を止められはしない。 ああ、人に恋するというのは、一目惚れというのは、このことを言うのだろうか。 一目惚れなど、都合の良い嘘だと思っていた。 恋など、私には無縁のものだと思っていた。 けれども、わたしはこんなにも。 こんなにも… ああ、一つだけ、一つだけ私の我が侭を聞いてください。 ある日のこと、とある忍が父上に何事かを話しているところを聞いてしまった。 どうやら、織田かどこかの武将が数人この辺りの町に攻め込んでいた所を何者かに撃退されたらしい。 一体何が起こったのか、撃退した人間を目撃した者はいまだ見つかっておらず忍たちは頭を抱えているという。 目を少し離した隙に、敵の武将たちは気絶させられていたようだ。 息があったということで、殺すつもりでは無かった事は見て取れたみたいだが、完全には分かっていないらしい。 果たして、何者が撃退したのだろうか。 その者は、どれほどの兵(つわもの)なのだろうか。 私はそこでぴんときた。 『よし、きた! 俺、今からそいつ等一発殴ってきてやるからな!』 あの人ではないか。と。 もしかすると、あの人が、『一発殴ってきた』のではないかと。 私は、そうと決まった訳でもないのに胸が躍った。 ああ、本当に、本当に…殴ってきてくれたんだ。と。 一言でいいから、お礼が言いたかった。私の無力さを、その拳で打ち砕いてくれたあの人に。 気付けば既に、馬を引いていた。普段着のままそれに跨って、私は町へと向かう。 やはり、というべきだろうか。 案の定、彼はそこに立っていた。 「よお、ちゃん!」 「…!」 「殴ってきたぜ! あいつら」 馬から下りる。目頭が熱くなる。 私は、声を振り絞って言葉を紡ぐ。 「…ありがとう」 かすれて、上擦ってしまったが、目的は遂げた。 涙が頬を伝う。 嬉しかった。 うれしかった。 ああ、私はこんなにも、こんなにもこの人を… 「ほら、泣いてちゃせっかくの美人さんが台無しだ!」 彼は私の頭をぐしゃぐしゃと撫でた。 「笑顔が一番! 人よ恋せよ、命短しってね」 「…はい!」 報われることは無い、結ばれることは無い。 彼も武家の息子。けれども私が嫁ぐ先はもう既に決まっている。 身分など、なくなればいいと何度思ったか分からない。 けれども恋を知る前に、好きでもない人の所に嫁いで行くよりは、 恋を知った後で、好きでもない人の所に嫁いで言ったほうが、 まだ報われたような気がする。 だから、精一杯の感謝を。 この人に捧げよう。 (20070527:ソザイ |