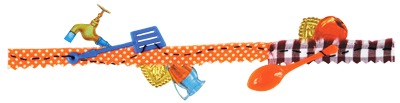
さあ、一緒に
君と、一緒に 行こう、あの丘へ 僕らの秘密基地 武蔵厳。 幼稚園から中学までクラスが同じだった幼馴染の腐れ縁な老け顔だ。 簡単に説明してしまえばそうなのだが、取り合えずどこかの道を通った時だったか。 ふと、思い出した。 ああ、この辺りでよく遊んだ。様な気がしないでもない。いや、確かここに秘密基地を作ったか? 橋の前で立ち止まって、その橋の下で秘密基地を作ったかどうかということを仁王立ちして腕を組んで考える。 ま、いいか解らなくても死ぬ訳じゃないし。はっはっは。 そして、歩き出して何か橋の下にあるのを見つけてふと立ち止まる。 なんだ、あれ。というのがそれを見たときの初めての感情で、まあ何となく気になるといった興味本位オンリーで ちょっと橋の半分まで来てしまって引き返すのも面倒臭いと思いつつ無理矢理引き返し土手を下り橋の下へ降りる。 ふと、目に留まった程度だったその白いスプレーで小さく汚い字で描かれたいたずら書きに見覚えがあった。 “とむさしの城” なんじゃこりゃ―。と思わず叫びそうになりながらも、危ないそれじゃ変な人になってしまうじゃないか。 とそんな事を思って思いとどまる。偉いぞ私! とまあそんな事は置いといて、何だこれは。 いやあ、そうかそうかそうかそうか思い出した。本当に懐かしいじゃないかコノヤロウ。 そういえば、ムサシの奴と小学生のときに遊んで何か描いた気がする。確かアレは、入学したばかりのときだったか。 入学式、翌日。 四月の幼稚園卒園から早二週間がたって、はれて小学一年生となった。 この通学路を六年間通うのかと少し憂鬱な気分になり、面倒臭いなと溜息をつく。 どうせならもっと有効的で将来使えそうな学校に行きたかったなと思ったがもう一度考え直した。 いや、それも面倒臭いことに変わりは無いな。 ふと桜がすでに葉の部分ばかりになって桃色の花弁が汚いアスファルトにぐちゃぐちゃと散乱していることに気付く。 もったいないなと思ったが、また来年も多分咲いてくれるさ。いやあしかし、入学式に合わせて咲いてくれれば。 もしそうだったらそれなりに良い場面が取れるんじゃないのかと少し期待を抱いてみた。それはないと一瞬で消える。 まあここの桜など、とうの昔に散ってしまって入学式は桜が葉桜状態なのが少しもの哀しくもあるが、まあいい。 この辺りなどは多分映画的に出てもつまらないだけだから多少はカットされるのだろう。いや寧ろ出ないかも。 そんな事を考えながら歩いているとちょうど目の前に黒いランドセルがひょこひょこしているのが目に入った。 相手に気付かれないように、ひっそりとこっそりと忍び寄っていく。距離が詰まった。――よし! ぴかぴかの赤いランドセルという可愛らしいモノを背負って私は前を歩く少年の頭を軽くどつく。 「なにするんだよ、ちゃん」 案の定少年は私がこっそりと忍び寄っていたことに対して全くと言っていいほど気付かなかったらしく、 振り返ってむう、とふくれっつらをしながら自分を殴った張本人に文句を飛ばす。 「あはははは! 細かいこと気にしてたらどっかのオジサンみたいにはげちゃうぜゲンちゃんよお!」 「な! ひどいよちゃん!」 げらげらと笑う私に対し、「はげないよ!」と抵抗する短髪少年、武蔵厳。 私はどうだかねえと考えながら、「ジョウダンにきまっとろうがあ―!」と彼を安心させようとして アッパーを食らわせながら叫ぶ。武蔵少年は、ぐっと小さく呻いてかろうじてその場に踏みとどまった。 黒いランドセルが、たんっ、と一瞬持ち上がって揺れる。 ほう、と私はそれを感心しながら眺める。なかなかの反応じゃないか、君! あはははは! 楽しいねえ! 私は声に出して「…ふふふ」と笑いながらそれを眺めた。 「もう! 早くいかないと、みんな まってるよ!」 「分かっているのさ! そんなコトはいいから早く行くのだああああ!」 とまあ、そんな訳で私たちの分団集合場所に行くとまだ2・3人しか来ていなかった。 そんなもんだろうか、もう少し今度から遅くでようか、いやまあいい。それで分団に置いていかれたら元も子もない。 それにしても、まあめんどくさい制度を小学校は設けやがったことだ。 みんなで登校、みんな一緒にみんなみんなってうざいんだよこらあああ! コホン、そんなコトはさておき遅い。遅すぎだアア! とか考えてる間に準備し始めて高学年を待たずに出発。 もちろん私もゲンちゃんも加わり三年生前後だろう女子の人と並んで歩く。 いいのか、これでいいのか! さっきまでの時間を返して欲しいと思いたいね! 講義する! 意義アリ! どう講義しようか講義の場面展開を考えていたら三年生前後の女子生徒が、唐突に口を開いた。 「ウチの分団、高学年の人たいてい来ないの。だから、このぐらいの時間にはもう出発してるのよ」 だってそれ以上待ってたらチコクしちゃうし。と彼女は私に向かってにこりと微笑みかけた。 そういう彼女の髪は肩に付くか付かないか程度の長さで前髪も同じように真っ直ぐに切りそろえられている。 横の髪の毛、ちょうどもみあげの部分だろうか。その部分一握りほどだけが肩よりも五センチほど長い。 その境目は逆階段のように段差が付いている。不思議な髪型である。 前髪から上は帽子になって隠れてはいるものの多分はげているなんてコトはない。滅多に無い、とは思う。 まあ、否定はしないが。 私はその三年生の女子生徒の言葉に、ほう…そうなのか。と多少納得して頷いた。 「そうなんですか」 「そうなのですよ」 また女子生徒はにこりと笑う。よく笑う人だな、と感心する。 「ほら、アレが学校」 彼女は、そういって校舎を指差す。 「あっちが1年から4年までの校舎で、向こうが5年と6年の校舎。ウチの学校、けっこうワケ分かんない造りしてるから、 まよわないように気をつけてね! こまったら、あ、わたし2年だから一コ上の階にくるといいよ!」 ね? とまたにこりと笑う。 「はい!」 いつものノリで了解です隊長! まで言いそうになって思わず踏みとどまる。やばいぞ、これはやばい。 こんなことまで言ってしまったら確実にこれからの学校生活に支障をきたすことになる! と思った。 で、結局めんどくさいので人前では猫を被ろうと思った。まあ、今の性格はこうこうせいになったら出そう。 軽い気持ちでそう思った。 校舎内に入る。 意外と広く見えるグラウンドと、何か2棟ぐらい並んだ四階ぐらい立ての建物が目に入る。 「ここで解散! 散れ―!」 三年生の女子生徒、いや、正しく言えば二年生の女子生徒は後ろの面子に「散れ―」と叫んでいる。 「あ、私の名前言ってないね! 私、浜岡龍己!」 「たつみ…さん?」 私はおそるおそる言ってみる。なんとまあ、珍しい名前だ。 「そうそう、『りゅう』って書いて、『おのれ』って書くの。それで龍己!」 「龍己さん、か…」 「そうそう、で、『さん』はいらないよ」 「龍己?」私は疑問符を交えて聞く。 「オッケイ! じゃあ、私先に行くね―」 ばいば―いと手を振る龍己。ゲンちゃんが私が話し終わって一人になったので近寄ってきた。 「ちゃん、あの人…」 多分「誰?」とかそんな事をゲンちゃんが聞くと考えた私は「龍己?」と答える。 「いや、あの名前じゃなくて、みょうじ…」ゲンちゃんは言葉を繋ぐ。「浜岡って言ったでしょ?」 私は少し間を置いて考える。 「あ、」そしてはたと気付く。「もしかして、近くの浜岡産業株式会社の?」 「そうそう、ウチの『オトクイ』さんみたいな人」 そういえば、ゲンちゃんの家は大工やってたようなきがするなあ、と幼い私はまだ少ない記憶を辿る。 「へえ」 私は感嘆の声をあげる。流石に同じ分団だけあって家が近いもの同士が集まる。浜岡産業株式会社は 確か家の近くにあった覚えがある。彼女はそうすると社長令嬢となるのだろうかと、考えてみる。 いや、社長令嬢になるに違いないと言う結論に私が思い至ると同時に下駄箱のある場所についた。 下駄箱のクラスと番号を確かめてロッカ―に靴を入れ、上靴を出す。ゲンちゃんも同じような動作をする。 ゲンちゃんとは幼稚園から今までずっとクラスが一緒だ。たぶん予想によると来年当たりは離れるかもしれない。 まあそんな訳で、これは腐れ縁としか言いようの無い縁に恵まれてやはりゲンちゃんとはロッカ―の位置も近い。 何故ロッカ―になっているのかというと、どうやら上靴が外部犯により盗まれると言う事件が起こったので、 保護者側から訴えがきたようで、多少の資金を投入して全校生徒分のロッカ―を設けたようだ。 何故上靴が盗まれるのかは謎だが、私としては設備が立派な事はありがたい。多分これはみんな一緒だ。 ゲンちゃんが上靴をたどたどしい動作で履くのをぼんやりと眺めながら私はぼうっと考える。 「できた―?」 「あ、うん」 と言いつつも、まだつま先をとんとんやっているゲンちゃん。 「できてないじゃんよお!」と、小声でノリツッコミ。 「今できたよ!」 「今かよ!」 ぱっとこちらに微笑んだゲンちゃんに私はまたしても小声で突っ込んだ。 時は過ぎ放課後。 なんやかんやで入学早々説明が色々とあっただけで帰れると言うのは小学生である私たちにとって好都合だった。 何故かと野暮な事を聞く輩も多いのでまあ一応端折って説明しておくが、要するに遊びにいけるから好都合なのだ。 都合がいい。まあ、遊びに行く友人等がいればの話なのだが。 そんな訳で、私とゲンちゃんはその日の帰り道に近くの川原――電車の通る土手に遊びに行った。気がする。 「よし、ちゃん。ここヒミツ基地にしよう」 開口一番にゲンちゃんの口から出てきたのはそんな言葉だった。 「秘密基地…ふうん。いいひびきだねえ、よしそうするか」 「ほんとに?」 ほんとほんと。と生返事をした私にゲンちゃんは目を輝かせる。 私は当時隠れ家とか秘密基地とかの映画よりもアクション戦闘系の映画の方が好きだったのでどうせなら地下通路とか、 そういうモノのほうが造りたかったのだけれども――せっかくの友人の頼みだ断れない。 それも、あんなに期待されては。と内心私は幼いながらにゲンちゃんに気を使っていたのだと思う。多分ね。 「じゃあさ、ここになんか印つけようよ」 適当なコンクリ―トで出来た橋の根元を指差すゲンちゃん。 「『しるし』、かあ」 むう、と幼馴染を見ながら考える。さすがに印などというものはなかなか思いつかない。 私はよし、と意気込むと「『とむさしの城』でどう?」と言ってみる。 城、というのは最近ビデオで見た天空の城を参考にさせてもらった様な記憶がある。…うろ覚えなのだが。 「え…」 一瞬、幼馴染は驚いたような初めて何か新しいものを見つけてしまったような、そんな表情をした。 その後に、その表情は歓喜のそれへと変化する。 「かっこいい! それにしようよ」 「だろ! かっこいいだろ! よしそうと決まったら書くものをチョウタツだァァ―!」 私は幼馴染の顔の前で片方の人差し指をぴん、と立てる。もちろん、もう片方は腰に当てて仁王立ち。 彼は少しきょとんとして私を見ていたが、「うん!」と勢いよく頷いてその辺りを探り出した。 私も同じようになって探す。草を掻き分けて、白いものが落ちていないかどうか。 手が大分土にまみれて茶色に染まってきた頃、ゲンちゃんが声を上げた。 「ちゃん! これ、すぷれいだよ!」 「スプレ―?」 「うん、すぷれい」 高々と、スプレ―缶を掲げるゲンちゃん。 「むう、それなら」 私はゲンちゃんからそれを受け取って、ゲンちゃんに「鼻つまんでな―」と言うと自分もハンカチを強盗のように 三角に折り曲げてその部分が口と鼻にかかるように後ろで縛る。 有害物質が沢山含まれているから、スプレーは吸うと危ない。そんなコトはとっくに映画の知識として取り入れていた。 「よし、」と私は意気込む。「始めるから」 「うん」ゲンちゃんは不安げに頷いた。 両者、一言も喋らずに無言の重たい沈黙が漂う。聞こえるのは電車が時々走っていく音とスプレ―のシュウシュウという 気の抜けた音と、土手を上がった所の歩道を通っていく学校帰りの学生や主婦たちの話し声だけだった。 シュウシュッ。 シュウシュウ。 シュッシュシュシュシュウ。 規則的な音が続く。カンカンカン、と踏み切りが何回か警戒して音を立てた。カラカラとスプレ―缶を振る。 私は額の汗をTシャツの型の袖で拭った。春の麗らかな陽気が、忌々しいほどに今は蒸し暑く感じる。 書道を幼稚園から習ってはいたが流石にスプレ―で書くのは少々キツイものが、小学一年生の私にとってはあった。 「よし、できた」 沈黙を破るように腰に手を当てて私は後ろを振り返る。ゲンちゃんは目を輝かせた。 まあ、五分ほどの出来事だったのだろうが私にとっては一時間も二時間も書いていたような錯覚に陥った。 それ程に、この文字を書くのに緊張していた。なぜだろうか、分からない。 不思議だった。奇妙だった。奇怪だった。それほど大事なものだと思わなかったのに。 どうしてだろうか分からないがまあ気に留めておくことも無いだろうなと。そのときの私はそう思っていた。 「見せてよ、ちゃん」 「ほらよ」 「うわあ」 ゲンちゃんの目がそれを見た瞬間に通常の1.5倍に見開かれ、表情は狂喜と驚喜と驚愕のそれに包まれた。 「す、スゴイ、かっこいいよ!」ゲンちゃんは壁のそれを指差して驚きながら叫んだ。 「そうか―?」私はうーんと考える。 「そ、そうだよ! すごいよ!」ゲンちゃんはわたわたと私の間違いを正すように慌てながら言った。 「こんなキレイな字かけてすごい!」 「そうか―?」 普通だと思っていたんだけどなあ、と言うと、ゲンちゃんは驚いて固まった。 「なに言ってるの! ちゃんくらいだよ! 書道家みたいだよ!」 「そうか―?」私は三度目の同じ返事を返す。そして、再度書いた文字と向き直る。「普通だぜ!」 「う―、ウマいよ! すごくウマいよ! だって、習字の教科書の字とそっくりじゃん!」 私は、再再度書いた文字に向き直る。そしてそこまで巧くないよなと首をかしげた。 「な! 何だよそのたいどはッ! お、おせじじゃないよ!」 ゲンちゃんは必死に自分の意見を述べる。 「あ―、分かった分かった」私は軽く受け流す。「おせじだと認めよう!」 「言ってること違うよ!」 「いっしょだよ!」 「口調まねしないでよ!」 「そんなコト言うなって―、楽しくないなあ」 「あう、ひどいよちゃん…」 しゅん、と萎れたように項垂れるゲンちゃん。少しやりすぎたのだろうか。 私は、コツンと軽くゲンちゃんの額を叩く。 「バカだなあ、ゲンちゃんはそれだから楽しいんだよ」 あははと爽快に高笑いしてみた。ゲンちゃんはぱちくりとこちらを見る。 「むじゅん、してるよ?」 アホか! 思わずそう突っ込みそうになって、「むじゅんはいいことだ!」とか何とか私はいったような気がする。 いや、まさかねえ、そんな矛盾なんて出てくるとは思いもしないじゃないか。 私は内心少し焦った記憶があるぞ、コノヤロ―。と、今になって思い出してみる。 それから暫く、ゲンちゃんとそこで遊ぶ日々は続いたのだが。それはやはりと言うべきか日に日に減っていった。 歳を重ねると同時に、徐々に徐々に。それはまるで、果てしなく進行していく癌のように。 絶対に直ることのないといわれた病に、身体を侵食されていくようなそんな状況。 その病に、私達の永遠の友情だったモノが、だんだん汚されて腐敗して崩れていくように。 そういえば、初めて仲良くなった子はゲンちゃんだった気がするなあと少し考えてみたりして。 ―――そんなこんなで、今に至る。 『とむさしの城』の前に私は長時間佇んでいたらしい。 私はそろそろオレンジ色に傾いてきた日を眺めながらそういえば今日はあの映画がレンタル開始だったかと思いながら、 帰りに借りに行こうかと鼻歌交じりに歩き出す。 「」 聞きなれた低音の声に私は手をひらひら振りながら振り向く。 「おうよ、ゲンゴロウ!」 「酷い言われようだな」 「おいおいおい、お互い様だろゲンちゃんよう」 私が言った後に少し間をおいてゲンちゃんは呟くように言う。 「懐かしいな、ここは」 「あ〜、ゲンちゃんがまだ可愛かったからだろ、ありえないくらいに可愛かった頃だろ。まさに可愛さのピ―クを迎えて それから徐々に爺のように老けていってしまったという…ご愁傷様」 「死んでねえよ!」 「じゃあ、必ずしも高校生には絶対に見られない外見に成長していってしまったという…お気の毒に」 「お前に言われる筋合いはねえよ!」ゲンちゃんは突っ込んだ後に溜息をついた。「お前は全く変わってないな」 「あはははは!」私は高笑いをする。「変わるわけないよ、私は私! 変わったら人格も再構成だぜもったいない、 私はそんな面倒な真似はゴメンだねぇ! ゲンちゃんみたいに無駄なことはしない主義さ!」 あはははは! と私はまた笑う。 ゲンちゃんも苦笑して、右手を右ポケットに突っ込むと白い紙切れを取り出した。 「ほらよ、蛭魔からの伝言だ」 紙切れを一枚、渡される。 「ああ?」 それを受け取って、「おお!」と思った。気が利くじゃあないか。 私のビン底眼鏡で隠れた表情を読んだのか、男は口を開く。 「で、どうなんだ」 「何が―?」私はわざと、とぼける。 「内容」 「さあね! 気になるなら本人に聞きな! じゃあなゲンちゃんよ、アディオス!!」 「じゃあな」男は普通に手を軽く上げる。 「ノリ悪いぞ―!」私は、少し走ったせいで離れた場所から男を振り返って言う。「女の子が寄ってこないぞ〜!」 「知るか!」 彼は、豪快にハハハと笑った。 私もつられて笑った。 いい事があるでしょう、悪いことだってあるでしょう。 何時だって、どんな時だって、私はどちらも楽しめる。 だから人生は好きだ。 「全く妖一の野郎め、どれだけお前は…」 私はあの金髪悪魔を思い浮かべてみた。ケケケと悪乗りして他人を嘲笑っている光景しか浮かばない 人間は儚かろうが、鳥が歌を無くそうが、月が泣こうが、関係ない。 私は私、他人は他人。 人生は立った一度きり。だとすれば。 私が主役。 他人は利用すべきもの。 ―――素直じゃない、全く。あの家族は皆素直じゃない。 それゆえにすれ違い、勘違いを起こし、家族関係は更に悪化する。 最悪の悪循環。魔のループ。バミューダトライアングル。 だから もう少しだけ 「そういやゲンちゃんも老けたよなあ。まあそれはそれで、面白いんだけどなァ。もう少し可愛さと子供らしさがほしい所だ」 うんうんと一人考えて頷いてみる。 君と一緒に、 「ま、これもありかもしれないけど」 私はやはり自己完結してレンタルショップへと足を運ぶ。 うふふ、今日は何を借りようかしら。と思いながら。 ゲンちゃんも今度見るときは誘ってみようか、と思いながら。 自らの夢と志を抱いて、 二人で夢の丘めざして走ろうよ。 (20070413:ソザイ |