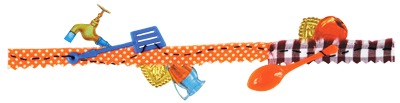 ねえ私は あなたの事をどれだけ思っていられるの
わかっていた、つもりだった。 それでもわかっていない、自分がいた。 だから、少し頭を冷やそうと思って渡り廊下に出る。広々として綺麗に手入れがされた庭が目に入る。 閑古鳥が鳴いた。その後でぱたぱたと羽音がする。どこかへ飛んで言ったのだろうか。ふと思う。 私もあの鳥のように、自由に飛んでいけたらいいのに。そうすれば――…いや、考えるのはよそう。 気がめいるばかりだ。何の解決にもならない。やはり、ここから抜け出したい。このままでは、いけない。 ぎり、と奥歯を噛み締めた。 私がここに連れてこられたのは、つい二日前の話だ。 私は、その日も茶屋の店番をしていた。 私の家は代々茶屋を営んでおり、私の母の代でもう4代目になる老舗。 いつも通りお茶を運び、いつも通り和菓子や団子を運び、いつも通り客と軽く団欒する。 そんな、いつも通りの光景の中。私は何事か起こるなど、考えもしなかった。思いつきすらしなかった。 だが、その日の客が不幸を運んできたのだ。 「いらっしゃい」 と、私はいつも通りに声をかけた。 「ほう」 その客の異様な外見と装いを見てふと違和感を覚えたが、私はさほど気にせずにご注文はと問いかける。 「団子を一つ」 「かしこまりました」といって私は団子を一本彼に差し出すために奥に取りに行った。 お母様は材料の買出しに、お父様とまだ齢3つの弟は先代様の墓参りに。 だから今日は、私一人で店番をしていた。 最初は私一人で出来るかどうか不安だったが今は別の不安に駆られている。 胸騒ぎがした。だれだ、誰なのだろう。あの人は。思い出すだけで気味が悪かった。 だから、早く帰ってくれないかと。そう思っていた。 「そち、」 不吉が、 「まろの」 近付いてくる音が、 「玩具になると良い」 からんと、持っていた盆を落とす。 ニヤリと、それはそれはニヤリと言う効果音の付きそうなほど不気味に奴は笑った。 私は、着物をぎゅっと握り締めて恐怖に負けじと口を動かす。 「…お断りさせていただきます」 それは私の発した言葉ではないかのような、冷気を帯びていた。 しかし、その言葉一つで「はい、そうですか」と引き下がってくれるほど相手もヤワじゃない。 そんなことは、予想できた筈だった。だから、逃げようと思ったけれど私の反応速度は思ったよりも遅かった。 「みなの者! この者を捕らえよ!」 おおおおお、と、何処からか歓声が聞こえて。何処からか伸びてきた手に私の両腕は捕まえられる。 私は必死に抵抗したが、戦に出る男共の体力にたかが甘味処の娘の力など到底敵う筈もなく。 あっさりと四肢を縄で縛られた私は、馬に積まれて忌々しいこの付近の城の女中にされるらしい。畜生。 私は小さく舌打ちをして、だんだん遠ざかっていく甘味処を見た。いつも通りに客が、お客様が来ているのに。 ただただ、非力な私は見ていることしかできなくて。 ごめんなさい、お母様。申し訳ございません、先代様。私がいたらないばかりに。 謝罪の言葉すら、かけることも出来なくて。 誰もいない茶屋に団子の串と割れた湯飲みがひとつ、転がっていた。 「お―い! 団子一本…ってあれ? 誰もいない?」 ここまで来たはいいものの、甘味処に誰もいないとは何事だ。と叫びそうになりながらも慶次は甘味処付近を偵察する。 いつも可愛らしい笑顔でいらっしゃいと言ってくる子の姿は何故か見当たらない。 「おっかしいな―、あのコ…いつもいる筈…ん?」 と、そこで店の異常に気が付く。 割れて転がった湯飲み、近くの土は足跡でぐちゃぐちゃと乱れており多少の争った後のようなものが見られた。 「あ、もしかして」 強盗? 「夢吉―、どうするよ」 「キッ」 肩に乗った相棒の小猿、夢吉へと俺は首を動かし視線を向ける。 夢吉は一鳴きした後に、ひょいと俺の肩から飛び降りてふらふらと甘味処を行ったりきたりしだした。 そしてまた、かるがると肩に戻る。 「キキッ」 「そうか」 結構大人数でここに攻めこんだみたいだし、計画立てて来たようだ。えーっと、これは俺が見た結果ね。 よく見ると、どうやら馬の足跡もあるみたいだから、馬で来たのは確実。 それも結構な数だから、まあどこかの変態武将がここに来てあのコ、確か名前は――ちゃん、を攫った、と。 ん―、ひとまずウチに戻って状況を整理してから助けに行こう。 「夢吉―」 「キッ」 攻めるぞ―、お―! と心の中で意気込んでみる。 願わくば、彼女が無事であらんことを。 ところ変わって、今川義元領。 「あちゃ―、大変だねえ」 猿飛佐助はいつも通り敵情視察に乗り込んでいたが、この城の異変にやはりと言うべきだろうか、いち早く気付いた。 「さ―て、お仕事お仕事っと―」 木から木へ素早く飛び移り、徐々に城の内部へと侵入していく。 ふと、人だかりが出来ている場所に目が止まって木上から様子を見る。 ひゅう、と口笛を吹いた。 「こりゃ、また。今川のとこもやるねえ」 全く、何考えてんだかわかったものではない、と馬から下ろされている女を眺める。 葡萄色の着物に白い三角巾、柳色の前掛けをしていて彼女の四肢は縄で縛られている。 「めちゃくちゃ別嬪さんじゃない」 ははん、と彼は納得する。 要するに、可愛かったから攫って連れてきちゃえばいいって考えかよ。考える事が汚いね、全く。 はあ、と溜息をついて考える。 確かに正義のヒーローのように助けなければいけないような気もするが、今自分がここにいるのは任務のため。 敵情視察という名の、れっきとした任務だ。 今の状況で、このまま任務遂行を放棄して敵に見つかりながらあの子を助けるのもアリかもしれないけれど、 それじゃあ俺の忍としてのプライドが許さない。 忘れちゃいけない。今の俺の仕事。 ちゃんと給料貰ってるしね―、安いけど。と皮肉を込めて頭の中でぼやく。 サッと、誰の目にも留まらぬ速さで城内の屋根裏に忍び込んだ。 警備の奴らもまともに城を守る気がないのかというほどにあっさりと、忍び込むことが出来た。 いや、別に罠が張ってあるわけもあるまい。何と言ってもここは今川の城。忍び込みやすいと忍の間では噂になっている。 もちろん、誰にも気付かれずに忍び込めるのは俺様の実力ってね。よく言うでしょ。 こっそりと、屋根裏から座敷の様子を見る。会話が聞こえてくる。 「ふぉっふぉっふぉ、容易いものでおじゃ」 今川義元が、扇子で自分を扇ぐ。家臣と思われる男が、一人彼の前に正座をしている。 「小娘一人ごとき、我々の手にかかれば」 「よいよい、楽しみが出来たのじゃ」 「は」 家臣が、頭を下げる。 「さがってよいぞ」 「は」 家臣はそういわれると立ち上がり、障子を開けて外に出て行った。 あの子は次の戦のときあたりにここから逃がしてやろうか。ふと、そんな事を考えてみた。 それからは、散々だった。 ここに連れてこられたは良いものの、それから倉庫のような納屋のような場所に丸一日閉じ込められたかと思うと、 急に今日になって外に出された。綺麗な着物を用意されて、取り合えず女中の人に着付けてもらった。 嬉しい反面何か裏があるのではないかと不安に駆られる今日。やはり昨日ほどではないが何か胸騒ぎがした。 ここから如何にして逃げられるだろうか。 自分の足だけでは確実に無理がある。 馬では早々に見つかって逃げ出してすぐさま捕まってしまうだろう。いや、案外捕まらないかもしれない。 厩を見せてもらう振りをして馬に乗って逃げると言うのはどうだろうか。いや、もし仮にそれで助かったとしてもだ。 私の家族はどうなるか知れたものじゃない。 助けなど待っていたら、自分の身が危うい…かもしれない。 どうしたものだろうか。 うーん、と表情に出さずに頭だけをフル回転させて悩んでいた所、女中の方が現れた。 「今川様がお呼びにございます」 「はい」 何で呼ぶんだこん畜生死にさらせ打ち首になれ大馬鹿野郎と内心ぼやきつつも女中の人は何も悪くないので 何も言わずにゆっくりと、彼女の歩く歩調に合わせて歩いて行く。 だだっ広い、これこそ税の無駄だと思われるような城の内部を眺めながら前を行く女中の人を見る。 礼儀正しく、この城にはもったいないような美人。 私のように連れてこられたかどうかは不明だが、彼女は私に話しかけた瞬間も近付いてくるときも無表情だった。 今から、ここの殿様である今川義元とか何とか言う奴にあって話をつける。 そこで「出来れば私、帰りたいのですが」と言って、「はいそうですか」と返してくれればなんら問題なく解決するのだが、 相手がそんな一筋縄ではいかない人だというのは百も承知である。心してかからなければ。 絶対に口論で負けたくは無い。だが自分の身を自ら危険にはさらさないよう、墓穴を掘りませんようにと、祈る。 と、まあそんな事を意気込んでいたときだったか。 ―――ドドドドドドドドドドドドドッドドドドドドッドドドド なにか、地響きたるものが聞こえた。 「敵襲じゃ―」 と、兵士の叫ぶ声が聞こえる。 「敵襲だそうですが」女中の方に問いかける。 「そうですね、逃げましょうか」女中の方はあっさりと、こちらを向いて微笑んだ。 なんだ、笑えるじゃないですか。 「敵さんが助けてくれないですかね」これは私だ。 「そうだと良いのですが、」不安そうに俯く女中さん。「――相手方も悪い方でしたら…」 「そんな事は今どうだっていいのです。私は家に帰る事が出来れば問題ありません」 「そう、ですか。あなたは幸せ者ですよ」 女中さんは悲しそうに微笑んだ。私は少しばかり女中さんの気持ちを汲んでみる。 「もし帰るところが無ければ、私の家に来るといいです。私の家、甘味処なんですよ」 人手が足りないので、よろしければ家に働きに来てください。と。 すると、案の定と言った所だろうか。女中さんはふわりと微笑んだ。 「お気遣いありがとうございます。もしもこの城を無事に出られましたら、ぜひあなた様の家にお仕えいたします」 「もちろんです、歓迎しますよ」 寝具と食事も用意いたします故。と私は少し楽しくなって言ってみた。もちろん、冗談などではないが。 女中さんも、精神的に元気になってきたようだ。 「ふふふ、今から楽しみでございますね」 顔がにやけてます。女中さん顔が凄く緩んでます。これでもかこれでもかというほどに好きなものを前にした人のように。 団子を喜んで食べてくれる人のように。 人が楽しそうにしている顔をみると、ついついつられて私も顔がにやけてしまう。にやにやにや。 これは職業柄そういう習性が根付いてしまうものなのだろうか。人の喜ぶ顔は何度見ても飽きない。 「撃破撃破ァ―!」 人の声が大音量で響いてくる。よくよく見れば、何か、色々と燃えている。 「ギャ―」とか「わ―」とかそんな兵士たちの悲鳴が聞こえてくるが、戦国時代には慣れてしまったもので、 私と女中さんの二人は取り合えず近い厩に身を隠し成り行きを見守る。 「あ、あれは」 ようやく先ほど叫んでいた声の主の顔を拝見する事が出来た。 「ウチに団子買いによく来る人…武将様、だったのか」 ボソリと呟くと、女中さんは首をかしげた。 「え?」 「いえ。独り言ですお気になさらず」 そして私は回答の代わりにふわりと彼女に微笑を。 ひそかに思い寄せていたなんて、馬鹿馬鹿しいにもほどがあるじゃないか。 身分が違うとなると、もはや致命的だ。 一生、この恋は報われることは無い。 けれど、少し。 「さ、収まったみたいですから、行きましょうか」 私は気を取り直して立ち上がる。そうですね、と女中さんも立ち上がる。 「馬も無事みたいなので馬で行きましょうか」と言ったのは女中さん。 「いいんですか、勝手に乗っちゃって」 「いいのいいの、遠慮は無用ですよ」 「おやかたさむああアアアア」 また、叫び声が聞こえた。悲痛の声ではなく、感極まった喜びの声。 それが敵武将の声となれば、考えられることはただ一つ。 「ほら、大将。やられちゃったみたいですから」 「先程まで仕えてた人じゃないんですか?」 私が言うと、女中さんはケラケラと笑った。 「何言ってるの、今私が仕えてるのはあなた様にございますよ」 「そうですか」 私は彼女につられて微笑んだ。 「ゆきむらあああああああ」 また、少しの間でも。 一緒にいられる時間があれば良い。 ウチに、団子でも食べに来てくれれば。 そんなことがあればいいなと、小さな願いを胸にい抱いて。 「やっ」 馬に跨り手綱を握り、足で馬の腹を蹴って馬を走らせた。女中さんも、馬に乗って後ろからついて来る。 運命は、交差する。袖触れあうも、多少の縁。 運命は、捻じ曲がる。人の恋路邪魔するべからず。 運命は、変わる。 螺子の回転が、くるくると、狂々と。―――狂い始めた。 (20070330:ソザイ |