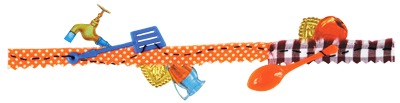
ケーキやクッキーなどの甘いものには興味が無い。
と、いうように見える彼は多分、身内以外の誰にも思考回路が分からないだろう。 俗に言うバレンタインが迫っていた。 面倒臭い行事の一つだと思う。それは所謂チョコレート業界の陰謀が混ざっている悪徳行事だ。 消費者である私たちが浮かれている所に漬け込んで、彼らはひたすらチョコレートを売りつける。 その種類は実に豊富で、高価なものから安価なもの、色彩豊かなものから普通の板チョコまである。 いつだったか、『友チョコ』をして御礼にと返ってきたのが普通の板チョコだった事が一度限りあったが、 まあそれはそれで置いておくとしよう。市販の方が安全と言うこともある。 確かに手作りの方が気持ち的にも何だか嬉しい気がするのだが、それで腹を下した経験のある私としては、 なんとも複雑な気持ちになるわけである。やはり市販の物のほうが良いのだ。 製造年月日偽造さえなければ。 やはり買わないほうが得策と考えるべきだろうか。 さて、バレンタインとは何か、その起源でもたどってみよう。 現在日本で呼ばれているバレンタインデーというのは『聖バレンタインの日』。 英訳すると『Saint Valentine’s Day』。 西暦3世紀のローマで皇帝クラウディウス二世が戦争に出ない若者等に対しに結婚禁止令のようなものを出し、 それに異議を唱えたバレンタイン――キリスト教司祭であるバレンチノ――が内密に婚礼を執り行っていた所、 それが皇帝に見つかり結婚禁止令に対する反対意見も認められずに投獄された結果、処刑された日。 つまり要約すればバレンタインが死んだ日となる。 そんな人が死んだ日に対して祭りをする人々の滑稽な姿を見ながら私は溜息をついた。 丁度テレビでニュースがやっていたのである。全くいい気なものだ。 此処まで批判しておいて言うのもなんだが、今年こそ私は何か行動に出ようと思っていた。 しかし相手が相手なのでこちらは何か相手の二手三手先を読んだ行動をしなければいけない。 それほどまでに難攻不落、攻略不可能に近い相手なのだ。 取り敢えず伝えることは伝えないと伝わらないことはわかっている筈なのだが、全く良い案が浮かばない。 そんなこんなで学校に行く時間となってしまったので私は適度に急いで家を出た。 靴を履いて玄関のドアを開ける。 バタンと閉めたドアに鍵をかける。 「あ! 先輩、おはようございまーす」 玄関の門を潜ると、向こうの道から後輩が駆け寄ってくるのが見えた。 同じ制服なので分かりやすいな、としみじみ思う。 「おはよう、桜井。今日も元気だね」 「はい!」 彼女は、元気よく返事をして満面の笑みを浮かべた。このような可愛らしい行動は、私には不可能だ。 「そういえば先輩、」桜井がこちらを見上げる。 桜井は私よりも頭一つ背が低いので、自然とこちらを見上げる形となるのである。 「先輩って、バレンタインは誰かにあげたりするんですか?」 唐突な質問に私は驚く。「いや、……まだ決まってない」 実はあげようかどうか迷っているだけなのであるが、特にこれと言って彼女に言う必要は無いだろう。 「そうなんですか、」少し桜井が残念そうに俯いた。「先輩のお菓子おいしいって評判なんですよ?」 あげないなんてもったいないですよー、と彼女はこちらを見上げて必死に私に訴えた。 だから何だ、と問いただしたい気持ちに襲われたが、「そういう桜井は?」と言う質問をして気持ちを抑える。 「えっと、……あの……」 桜井はもじもじとしている。どうやら本命がいるようだ。 「本命でもいるのか? 部活では全員に配るんだろう」 「えっと、……まあそう、と言えば、……そう……なんですけれど」 分かりやすい反応だった。 「部員の中にいるとかか? きっと、まあ貰った奴は喜ぶだろう」 と私は相変わらず適当な事を言う。 「本当ですか! ありがとうございます!」 とまあ、いつも通りになった桜井は元気を取り戻したようになって答えた。 結局、良いんだか悪いんだか分からない結果となった。 学年が違うので下駄箱の所で桜井と別れた私に、真っ先に話しかけてきたのが隣のクラスの佐藤だった。 「バレンタインはシゲちゃん期待してまっとるで〜」 などと苛立ちを感じさせる発言をしているので無視した。 「無視かいな! 姫さんのお菓子はプロ級を越えてパティシエ級やて皆言うとるさかい、 是非おこぼれを頂戴したく現れたんや」 せやから、バレンタインにお菓子つくってや〜、などと隣で言っている。 靴を下駄箱に仕舞って上履きを取り出す一連の動作の間に私は、彼に問いかけた。 「面倒臭いじゃないか、何故君に作る必要があるんだ」 「どうせいろんな人から請求されんねんから、一人ぐらい増えたところで変わらへんやんか だったらついでに、シゲちゃんのやつも作ろかな〜、なんて思うやろ?」 「思わない」 と、私はきっぱり言い放つ。 「酷いわ〜、ワタシ落ち込んでしまうわ〜」と、彼はくねくねとした動作で泣いた振りをしている。 しかも声が微妙に裏声めいているものだから、ぞわりと背中に悪寒が走った。 「私に貰わなくとも君は毎年沢山貰っているだろう、よって敢えて私から君に何か作って渡す必要など無い」 「不破センセみたいになってんで〜」 彼はからかうように、――実際からかっているのだろう――口に手を当てて小声で叫んだ。 「私の性分だ、君につべこべ言われる筋合いは無い」 「ホンマ、つれへん性格やなァ」 「君は、掴めない性格だ」 全くだ、とお互いが認めた後、並んで互いの教室へと向かう。 「で、結局姫さんは誰にあげるん? バレンタイン」 「決めてない」 「あちゃー、誰にもあげへんのかい。そりゃ全国のパティシエが泣くわ」 「別にそんな事は無いだろう」 オーバーリアクションで驚いた彼は残念そうだ。 私はそれに構わずに続ける。 「業界の陰謀に振り回されるのは嫌いだからね」 「現実味おびとって嫌やわァ」 「それはどうも」 そこで各々の教室へと散り、私はドアをガラガラと開ける。 自分の学生カバンを机に下ろす。 そして考えた。 私は、バレンタインに向けて一人でチョコレートを使ったものを作る気は全く無いが、 別に大勢で作るのには問題ない。 多分今年も有希に誘われるのできっと作る羽目にはなるのだろう。 女子サッカー部の面々で菓子等を作るのは楽しくて好きだ。 しかし、それではあの人にあげるものも義理という形になってしまう。 複雑な心境のまま、私は授業に望んだ。 授業はさらさらと川が流れていくように進んだ。 だんだんと速くなっていく教師の黒板を書くスピードに、眠気と格闘している学生たちは辛そうだ。 きっと彼らのノートはミミズののたくったような字が這いずり回っていることだろう。 読み返そうと思っても読めない。そんな最悪なノートだ。 私は生憎睡魔と闘うなどという愚かな行為はしないので、さらさらとノートをとっていた。 彼も同じようにノートをとっているのが横目で見えた。 来年の受験は此処が大事だぞーと教師が言う。 私たちは取り敢えずそこをマーカーで囲む。 取り敢えずそんなこんなで授業も終わったので、私は教室を後にした。 (20070000:ソザイ |