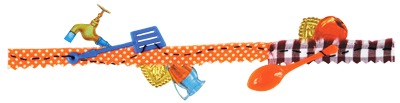
手を伸ばしても、強くもがいても、幾ら足掻いても
届かないことなんて、初めからわかっていた気がする。 雨が降っていた。バケツをひっくり返したような、土砂降りの雨が。 私は朝の晴天を思い出して、溜息をついた。折り畳み傘を持ってこなかった自分に呆れた。 そして置き傘をこの間の雨の日に使って、それきり学校に持ってきて置いていなかった自分に嫌気がさした。 これじゃあ、置き傘の意味がない。畜生め。 お天気お姉さんの今日は一日晴れるでしょう、降水確率は0%ですといった言葉の羅列をふと思い出した。 なんだ、全然当たっていないどころか的外れもいいところだ。もう一度、空を見上げて溜息をついた。 私が今いるのは下駄箱から少し出たところの、外の雨宿り所のような場所だ。 上の頼りない屋根は少し黒ずんで汚れている。目の前の土砂降りの雨に何人かが外に出るのを躊躇して屯っている。 その内の一人の男子生徒が、私と同じように溜息をついた。 彼も同じようなことを考えているのだろうか、心なしか表情が曇っている。様に見える。 お互いに雨宿り組みは話したことも、面識すらない者同士なのだから沈黙は当然なのだが何を思ったのだろうか。 その男子生徒は私に話しかけてきた。 「二年の先輩ですよね、美術部の」 「そうだけど」 何者だこいつ。と最初に抱いたのは不信感。自然とその男子生徒を睨む形になる。 「そ、そんな警戒した目で見ないでくださいよ、俺、一年の藤代ッス」 「ああ、そう」 私ははっきり言って私以外の生徒には興味がない。学校なんて勉強する為だけの場所で友人は必要最低限。 親友なんて一人いればいい。交友範囲は狭く浅くが私のモットー。 出来るだけクラスでそれ以外の至る所で目立たないように誰の目にも留まらないように。と、そう勤めてきた筈だ。 なのに、どうして。同じ学年でもなく同じクラスでもない見ず知らずの少年が私の事を知っているというのだ。 「凄い雨っスよねー、寮につく前に制服びしょびしょに…」 訳がわからない。隣の少年は何かよくわからないがベラベラと喋っている。「ミカミ先輩におこられるー」とかなんとか。 そういえばそんな奴が私のクラスにいたようないないような、気がする。まあ、気のせいだと言うこともありうる。 クラスの人の名前なんて大半は記憶にないし、顔もうろ覚えだ。前後左右がかろうじてわかる、それぐらいだろうか。 取り合えず、三年は卒業してしまったので必然的に私の学年と言うことは確かだが、クラスなど分からない。 興味がないのだから。 「あ、そういえば先輩って三上先輩と同じクラスなんスよね―」 「記憶にないけど」 沈黙。 藤代、といっただろうか少年は目を見開いたまま固まった。 「うわ―、三上先輩と同じクラスなのに知らない人が…」 藤代少年はそこまで口走った後で口を手で覆った。何かまずかったのだろうか。 『ミカミ』とか言うヤツは芸能人か何かか? 私は考えては見たが、テレビなどはニュース番組しか見ないことに気付き、 これでは誰がそいつだろうか解らないというか、考えても埒が明かないということに気がついた。 まあ、自分に関係ないのだから良いのだけれども。 「そ、それじゃ俺の事も知らな…」 「全校生徒の名前、言える筈がないでしょう」 同じクラスでも名前がわからない人がいるのに。 私が溜息をつくと藤代少年は、また私と同じように溜息をついてしゃがみこんだ。 「俺、サッカー部なんスよ」 「で」 「エースなんスよ」 「ふうん」 「…何か言うこととか―、ないんスか?」 「がんばってね」 棒読みで。 「ぐ…、ひ、酷いっすよ!」 「何か言えといったのはあなたでしょう?」 初めてかもしれない、こんなに楽しいと感じたのは。 捨てられた犬のような目でこちらを見る彼に、そう言って私は思わずクククと笑った。 と言えば、そうそうその存在を知っている人は少ない。 ショートヘアで黄土色のような髪色。左右2本のピンで横の髪を留め、表情は変わるといえば変わる。 美人といえばまあ美人の部類に入る容姿だが、その存在自体は目立たない。 同じクラスになろうとも、進んで人と話すことはなく。 挨拶をすれば挨拶を返してきたり、悩みを相談してみればじっと聞いてくれていたりする、が。 いわゆる無口で目立たない奴、だ。 授業中も喋ることはなく、真面目に授業を受け当てられればスラスラと回答を答え決して答えに詰まることはない。 テストの順位もそれなりで必ず学年3位以内には入るものの本気で1位を狙ってはいないらしくいつも2位か3位。 本気を出したら彼女は1位くらい楽に取れるのではないかと思われるほどではあるが、何故か必ず1・2点差だ。 量ったように、計ったように。 必ず2位か3位、確立は半々。 そして美術部での彼女の地位は副部長、だが実力は絵のコンテストで最優秀賞レベル。 部長である部長は肩書きのみで、彼も自分よりも彼女のほうが実力上、上だということは承知の上だ。 しかし彼女は目立たない。 計算したように、操ったかのように。 忍の如く、姿をくらます。 「先輩」 「何」 30分も立ったと思った頃だ。先程まで数人いただろうと思う人達も躊躇していても時間しか過ぎないと思ってのことだろう 意を決して豪雨の中に飛び込んでびしょ濡れになりながら走っていったせいで、ここには既に私と藤代少年しか居ない。 ふとザアザアという沈黙を破るように立ち上がった藤代少年が言った。 「いや、やっぱいいっス」 「そう?」 藤代少年は私の疑問符に考え込んで、「あ―」と間をおいた。 「…先輩って好きな人とかいます?」 一瞬私はその言葉に呆気に取られて、目を何度か瞬かせた。 いる訳がない、興味がないのだから。と、私はその愚問に答えることにする。 「いや、」呆気にとられたまま、まじまじと愚問をわざわざ問いかけた藤代少年を見た。「いない」 「じゃ、彼氏は?」 「いや、」と、少々落ち着きを取り戻した私はかぶりを振る。「いない」 「希望はあるわけっスよ、俺にも」 藤代少年はニカッと笑った。 「全く、」私はやれやれと呟く。「変な人だ」 と、藤代少年は「な、酷いっスよ先輩!」とオ―バ―リアクションで私に反論しだした。 ククク、と私はまた笑う。なんとも、面白い少年だ。と思う。表情が、コロコロと変わって虹のようだ。 藤代少年は、急に真面目な口調に戻り呟く。 「遠いなあ――、先輩」 「何が」 「いつも思うんスよ、なんだか先輩っていつも一線引いて物事を見てるっていうか。何か他人事っぽい感じで。 遠い存在のような気分になるんスよね。雲の上とか」 少し驚いた。意外と人の事解ってるじゃないかと、不思議に感じる。彼はまだ続ける。 「それでいて、人の話とかちゃんと聞いてるし。で、答えてくれた事とかもめちゃくちゃ参考になったりするんスよ。 みんなそれで尊敬する人は先輩のことスッゲー尊敬してるんスよね」 何が言いたいのだろうか、藤代少年は続ける。 「で、俺もその一人なんスよ。俺は先輩に直接会った訳じゃないっスけど、スゲ―と思ったんっス。 的のど真ん中を射たような、今言って欲しいアドバイスしてくれて、――俺感動したんっスよ」 「そうか」 そ―か、とそんな間延びした発音になってしまったが、そんな事あったろうか。 いや、あった。 一年前だったろうか。クラス内の誰か忘れたが、男子生徒だった気がする。 その男子生徒と放課後の日直の仕事をしていた所、日誌を書いている私に彼は淡々と語り始めた。 私が、結局の所話しかけられなければ話さない性質。 逆に言えば話しかけられれば話すと言う性質。彼はそれをを知ってか否か、私に語る。 聞けば、――悩みを打ち明ければ私がその解決法に近いアドバイスを返してくれる。 そんな事を以前私に悩みを打ち明けた人から聞いて、相談する機会を伺っていたのだと言う。 ペンの動くスピ―ドを緩めないよう男子生徒の言うことを一言一句聞き漏らさないように私は全神経を研ぎ澄ませる。 要点をまとめると以下の通りで。 一点目が男子生徒の後輩、まあつまり中等部の部活の後輩が悩んでいるらしいということ。 二点目が男子生徒の後輩が、スランプに陥ってしまったらしいこと。 三点目が男子生徒の後輩から、いつも通りの溌剌とした表情が消えてしまったということ。 これは私の一般的な考えからいくと、どうも重大な項目には見えてこないのだが、彼にとっては一大事らしい。 普段、活発に動き回っているらしい後輩が、途端に元気をなくしてしまった。 私としては放って置けば何とかなると思うが、一応その当時の私で出来る限りいいアドバイスに言い換えて伝えた。 と思う、多分。 一年前に言った言葉など覚えてはいないし、そんな事を覚えていられる驚異の記憶力など私は持ち合わせてはいない。 だがその男子生徒の後輩は、覚えていたようだ。 「『出来なくなったんじゃない、自分の理想が高すぎるだけだ。思ったように出来ないのは当たり前。 自分の実力が理想に追いついていないから。何かやっていると必ず壁にぶつかるそれは誰だって同じ。 それで諦めるようなら、その努力はそこで終わる。だけど壁にぶつかったら、そこで終わりなんかじゃない。 乗り越えなくちゃいけない。要するに、どん底から如何にして這い上がっていけるかどうかが大事じゃないか』って」 私は、フッと笑った。 「凄い、全文暗唱か」 皮肉めかないように、注意深く言った。 「そりゃ、当たり前っスよ! 恩師の言葉っスから!!」 クククと自嘲気味に私は笑う。まさか、こんな展開とは。 「たいした記憶力だと賞賛しましょう」 「あ、褒めてくれてるんスか、それ!」 「さあ、ね」 賞賛してるんだから褒めてるんだよ、と目の前にいる藤代少年に微笑む。 確かに、この藤代少年が落ち込んでいたら気にかかるかもしれないと、ふと思った自分がいた。 全く、変な人だな。と思いながら隣の少年を見る。 やはり彼は唐突に言った。 「先輩」 「何」 「決めてたんっすよ、俺」 何を、と私が言う前に彼は言った。 「俺と付き合ってください!」 突然の告白。 「ああ、私は君ならいいと思うよ」 突然の対応。 思わず口を出た言葉に、私も驚いた。 「え?」 これは、藤代少年。 「どうした?」 「いや、断られるかと思ったんっスよ」 「まあ、君と話す前ならね」 これは事実だ。実際、話していない段階でストレートに告白されても困る。 「先輩」 「何」 何回目かのやり取りのあと、彼は言った。 「先輩って呼んでいいですか」 「構わないね」 「じゃ、敬語もなしで」 「愚問だね」 雨が小降りになってきた。やはり通り雨だったようだ。 藤代少年は、「やりい!」と言って飛び跳ねて喜んでいる。 私は、藤代少年…――たった今私の彼氏になったらしい少年を見る。 自然と、笑みがこぼれた。 (20070329:ソザイ |